|
|
|||||||||||||
前回(ひろば118号)、バランスのよい食事とは何を食べたらよいかを挙げました。今回は更に「どれだけ」を加えればよいか考えてみたいと思います。 |
|||||||||||||
|
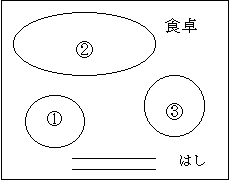 |
||||||||||||
|
③は全体的にカロリーの低いものがほとんどで、多く摂ったとしても(肥満に繋がるとか)それほどは問題になりません。また、③に主に含まれる栄養素である「ビタミン」「ミネラル」といったものは体内に長い間置けないものが多いです。加えて体内のお掃除役である「食物繊維」と呼ばれる栄養素もこの③には多いのでむしろたくさん取るぐらいに考えた方が良いかもしれません。(但し極端に多くとると下痢をします) お浸し、酢の物、サラダ等小鉢に入りそうなものはおおよそ50~80gぐらいと思われますのでそれと主菜のつけ合わせ、汁物の具等をあわせて食べれば100gという数字はクリアできると思います。 |
|||||||||||||
|
卵1個 魚70~80g(切身で1枚程度) このくらい摂れば充分です。 |
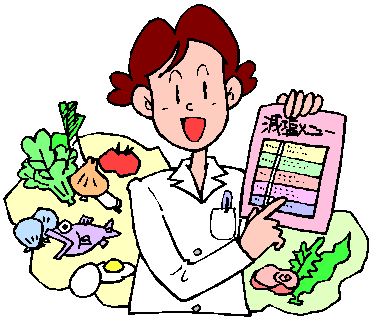 |
||||||||||||
|
①は「炭水化物」と呼ばれる栄養素が主に含まれます。これは体を動かすもと、つまり燃料としての役割が主だったものです。単純に考えればよく動く人は多めに、あまり動かない人は少なくてよいということがいえます。その人がどれくらい体を動かしている環境にあるかで異なり、目安は具体的に挙げにくいのですがあえて挙げるならば御飯で考えて
―ご注意― |
|||||||||||||