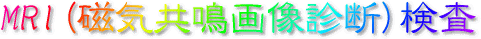
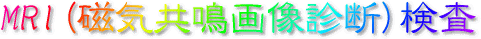
| MRIは極めて有用な画像診断技術ですがその他の検査と同様に万能ではありません。したがって患者さんによっては、超音波、CT、MRIと組み合わせて検査しないと診断がつかない場合も多々あると思いますので、医師から説明をお受けになりご協力を頂きたいと思います。 |
|
|
1.脳神経 出血は(脳出血、クモ膜下出血など)CTの方が良くわかりますので脳血管障害では、まずCTを施行しそれが除外されたときにはMRIをします。脳腫瘍、脱髄変性疾患、炎症もMRIが適応です。 2.頭部・頚部 副鼻腔癌、咽頭や口腔内癌、唾液腺癌、顎関節症などは適応です。 3.脊椎・脊髄 まず単純X線写真後施行します。椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄、外傷、脊椎・椎間板炎、脊髄炎、脊椎・脊髄腫瘍が適応です。一方、後縦靭帯骨化症や変形性骨関節症はCTの方が優れています。 4.肺・胸壁など 肺炎や肺癌はCTの方が適していますが、縦隔腫瘍や胸壁、乳房の病変はMRIが有利で、使い分けが必要です。 5.心・大血管 まず超音波が用いられますが、大動脈瘤、心筋症、心臓腫瘍、弁膜症、左房内血栓などの診断にMRIは有効です。冠動脈の狭窄の状態はまだ精度が不十分ですが、研究が進んでいます。 6.腹部 超音波とCTで診断がつかないときや、病変の性状をさらに知りたいときに施行しますので、ほとんどの疾患が適応です。肝細胞癌、転移性肝癌、胆管癌、胆のう癌、膵癌、腎臓癌など腹部臓器から発生する癌のすべてと肝血管腫など良性のものも適応です。石灰の抽出性に乏しいので胆石や肝内結石、肝嚢胞はCTの方が優れています。 7.骨盤腔 男女性器は超音波を施行しその後MRIをすることで前立腺肥大、子宮筋腫等診断つきますが前立腺癌、子宮癌、卵巣癌などはCTも併せて施行しないと診断がつかないことが、多々あります。 8.骨・関節 単純X線の次に施行しますが、殆どの疾患で有用です。MRIでは断面の設定が任意に可能ですので種々の角度から病変を抽出できます。もちろん骨や関節だけでなく、靭帯や関節軟骨、滑膜、骨髄腔の状態も解ります。 |
|
簡単にMRIの特徴をご説明致しましたが、病気の診断は診療所見、血液検査などと同時に画像を読むことで得られます。高価な機械があっても読影(画像をみて診断をつけること)が、不十分では宝の持ち腐れですし検査をなさった患者さんにも申し訳ないと思います。病気になるのは完全に防げません。とにかく早期に発見し、治療をすることが大事と肝に銘じて今後も診療に当たって参りたいと思っております。 |
|
| (所長) |