|
鉄は地球上の生命の誕生とともに、体内に取り入れられ、生命の働きには不可決の成分として、重要な役割を担ってきました。それは、鉄が2価と3価の原子価として体に存在することで、体の酸化還元反応をすすめる担い手になっているからです。例えば人体にあっては、鉄は赤血球が酸素を運搬する時のヘモグロビンに結合しています。 しかし、鉄は一方で、酸素の存在で、活性酸素を産生し、生体に不利に働くという側面もあります。殊に2価の鉄はむき出しのままでは、有害ですので、生物はこれを蛋白に結合して、有害性を緩和しています。その蛋白にはトランスフェリンとフェリチンがあります。トランスフェリンは鉄を運搬し、フェリチンは鉄を貯蔵する役割を果たしています。 鉄の過剰で、肝硬変、肝癌になるヘモクロマトーシスという遺伝病が知られています。この病気の成立と似た事情で、ウイルス性肝炎でも、肝細胞内で、鉄が活性酸素をつくり、肝細胞障害をもたらすだろうとは、古くから考えられていました。体の鉄を不足状態にすれば肝細胞障害は落ち着くのではないかと、考えるのも自然です。このため、この十年来、慢性肝炎の患者さんの血を取り捨てる瀉血が行われています。 瀉血は肝炎ウイルスの増殖には関係しないので、インターフェロンのような肝炎ウイルスを消滅させることはできませんがGOT・GPTを改善します。 GOT・GPTが正常化すれば、肝炎の活動性が沈静化し、肝硬変症への進展速度が遅くなることが期待できます。また、インターフェロン治療に先立って瀉血をしておくと、いきなりインターフェロン治療を開始するより、治療効果が高いという、データーがあります(図)。 このように瀉血は、いくつかの期待をもてるデーターはありますが、まだ、同じような肝炎の状態の患者さんについて、瀉血をしたときとしない時で差があるのかという、きちんとしたデーターはありません。 ですから、瀉血を真っ先に選択するものではなく、何回かのインターフェロン治療が奏功しなかった患者さんについては、強力ネオミノファーゲンC、ウルソなどの治療に次いで、試みることも、可能性としてはあるでしょう。 患者さんの鉄の状態を知るために、日常の検査で私たちは患者さんの鉄、総鉄結合能、フェリチンなどを測定したり、肝生検で、推測したりしています。 今、どの検査項目が瀉血の選択の指標になるか、検討を加えているところです。 (相川達也) |
||
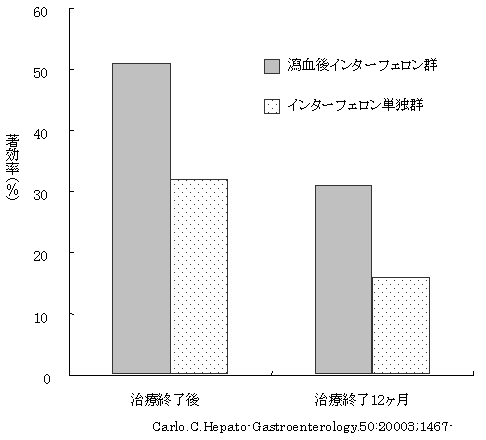 |
||