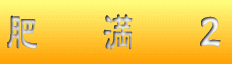
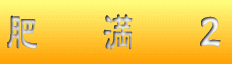
| 【脂肪肝から肝硬変まで】 | |
| 健康診断でよく指摘されるのは脂肪肝です。脂肪肝はこれまで肥満であることを言い直したようなもので、さして注意をむけることはありませんでした。最近、肝移植に際して提供された肝臓が脂肪肝であると移植後に機能が回復しないことが経験され、脂肪肝の評価は重大な問題となってきました。 |
|
| 【非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)】 | |
| また、脂肪肝と見られた人々の肝生検をしてみるとアルコールを飲まないのにアルコール性肝炎と同じように脂肪を取り込んだ肝細胞と肝細胞の壊死、線維化が見られ、これを非アルコール性脂肪性肝炎(Non Alcoholic SteatoHepatitis 略してNASHナッシュ)と名付けました。また、従来原因不明とされていた肝硬変症はいわばNASHのなれの果てであろうと推定されています。実はNASHが存在することは既に、一九八0年にメイヨークリニックの十年間の肝生検標本を調べる中で20例がみつかり、これまで知られていなかった組織像を示すことからNASHという名が提案されていました。しかし、それから20年間はあまり注目されていませんでしたが、欧米では肥満者が増加したことで、二000年から二00一年末までに主要雑誌に発表されたNASHに関する論文数は122編で、過去20年間の論文数161編に匹敵するものとなりました。 食習慣の違う日本でNASHが存在するかは議論されていますが、注意深く観察すると当院でも患者さんは見つかりました。 最初に報告されたNASHとされたヒトの90%で肥満が見られ、50%で高血糖、36%で高コレステロール血症がみられました。肥満のヒトの肝臓は多くは単純な脂肪肝ですが、そのうちの一部がどうしてNASHに進むのかは十分に確定はされていません。 |
|
| 【インスリン抵抗性】 | |
| NASHでは高インスリン血症が多いことがわかり、2型糖尿病を合併する頻度も高いことが知られています。高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満、高インスリン血症などがそろった病態をメタボリック(代謝)症候群、X症候群、死の四重奏、インスリン抵抗性症候群などと名付けて、動脈硬化症の危険因子として対策が喧しいところです。その中でインスリン抵抗性は動脈硬化症の危険因子の中心的役割を果たしていることが明らかになってきました。そしてその上流に内臓肥満があります。 知られているように、肥満には皮下脂肪が増加するタイプと内臓脂肪が増加するタイプとがあります。内臓の脂肪細胞は飢餓に備えて飽食で余剰となったエネルギーを脂肪として蓄えます。脂肪細胞は必要に応じて蓄えた脂肪を遊離脂肪酸として放出し、血中の脂肪酸は直接に門脈を介して肝に送りこまれて、中性脂肪として蓄積され脂肪肝ができあがります。肝での中性脂肪は新たな脂質の合成、糖の新生に使われて高脂血症、高血糖の状態を作り出します。内臓脂肪の脂肪細胞は内分泌機能、免疫機能を持っていることが判明しました。脂肪細胞は活発にホルモン類似の蛋白質や免疫反応を調整するサイトカインを分泌して筋肉での糖の取り込みを抑制し、インスリン抵抗性を高めます。さらに内臓の脂肪細胞からのサイトカイン(TNF-α))はインスリンの作用を妨害したり、炎症を起こすことで脂肪性肝炎の原因となります。このとき鉄も酸化ストレスの一つで、肝細胞障害の成立に関与します。 すなわち、NASHの成立の第一歩はサイトカインによる末梢のインスリン感受性の低下による遊離脂肪酸の増加、それに引き続く肝での中性脂肪の蓄積であり、第二ステップは脂肪の酸化ストレス、鉄の酸化ストレス、ミトコンドリアの機能低下、薬物代謝酵素系の活性などが関与しての炎症です(図)。 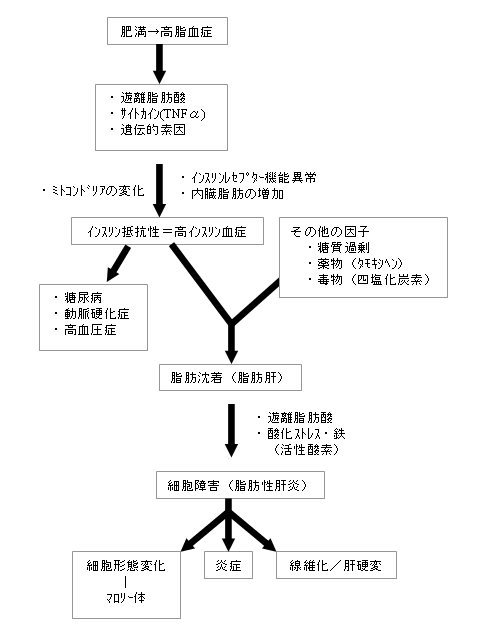 |
|
| インスリン抵抗性は動脈硬化を作り出し、高血圧、糖尿病、などの心血管系の疾患と深く関係するばかりか、脂肪肝、NASHからの肝硬変症にいたる肝臓病とも関連する、これからさらなる研究課題を提供してきています。 (次回は動脈硬化を中心に考えます。) |
|
|
(相川 達也) |