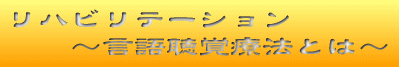
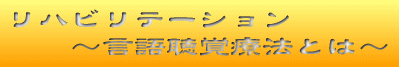
| 言語聴覚療法とは、コミュニケーションや食べることに障害を持つ人々の言語や聴覚、摂食の機能の獲得・回復・維持を支援し、最終的に「QOL」(生活の質)を高めるために行われるリハビリテーションや療育の一領域です。また、機能そのものの獲得や回復が困難な場合には、補助具(補聴器や人工内耳、人工喉頭)や代用手段(コミュニケーションエイドと呼ばれるハイテク機器などを使用した方法)を用いた代償能力獲得のための訓練を行ったり、家庭や学校・職場での社会的不利の軽減を図るため、家族、教師、職場の上司や同僚にさまざまな助言や指導を行うことも含まれています。 人間はさまざまな障害を持つ可能性がありますが、社会的存在である人間にとって、コミュニケーション障害は社会生活を送る上で最も困難な障害です。しかし、手足などの障害と異なって、その人の外見だけからは理解しづらい障害でもあります。それだけに、これらに立ち向かう人々を援助する専門家の仕事は高度の専門性を必要とすると同時に共感性に富み、かつ繊細であることも求められています。 | |||||
| 【言語聴覚士とは】 | |||||
| 私たちはことばによってお互いの気持ちや考えを伝え合い、経験や知識を共有して生活をしています。ことばによるコミュニケーションには言語、聴覚、発声・発音、認知などの各機能が関係していますが、病気や交通事故、発達上の問題などでこのような機能が損なわれることがあります。言語聴覚士はことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職です。また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。言語聴覚士は、英語表記である、Speech-Language-Hearing Therapistを略して「ST」とも呼ばれています。 ことばによるコミュニケーションの問題は脳卒中後の失語症、聴覚障害、ことばの発達の遅れ、声や発音の障害など多岐に渡り、小児から高齢者まで幅広く現れます(表参照)。言語聴覚士はこのような問題の本質や発現メカニズムを明らかにし、対処法を見出すために検査・評価を実施し、必要に応じて訓練、指導、助言、その他の援助を行います。このような活動は医師・歯科医師・看護師・理学療法士・作業療法士などの医療専門職、ケースワーカー・介護福祉士・介護支援専門員などの保健・福祉専門職、教師、心理専門職などと連携し、チームの一員として行います。 |
|||||
|
|||||
| 【言語聴覚士が活動している場所】 | |||||
| 言語聴覚士は医療機関、保健・福祉機関、教育機関など幅広い領域で活動し、コミュニケーションの面から豊かな生活が送れるよう、ことばや聴こえに問題をもつ方とご家族を支援します。 | |||||
|
|||||
|
(言語聴覚士 伊藤慶子) |
|||||