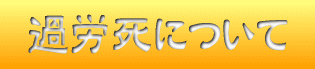
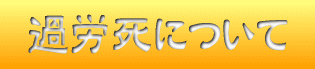
| 【過労死の定義・実情】 | |
| 過労死の定義はいろいろですが、「過度な労働負担が誘因となって、脳血管疾患や虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、永久的労作不能または死に至った状態」を一般的に過労死とよんでいます。 日本産業衛生学会での作業関連要因検討委員会が1992年に開催され、その後種々の討議がなされてきましたが、最近過労死の増加とともに大きな社会問題となってきています。 過労死の労災補償状況に関しては、厚生労働省労働局による報告があり、その件数は年々増加しています。2002年の報告では、過労による労災補償の請求数は819人(2000年は466件)脳出血や心筋梗塞など発症し労災認定を受けたのは360件でうち死亡者は160人でした。その7割が40~50代の中高年であり、ほとんどが男性で女性は16件でした。 一方、働きすぎによる自殺(未遂を含む)やうつ病などの精神障害での労災請求は341人でうち、自殺43人(全員が男性)を含む100人が認定されています。 業種別などでは、長期の過重労働が問題になっている運転手、卸・小売り業、製造業、IT関連の技術者、医師などが増加し、職種別では管理職が一位となっています。 | |
| 【認定基準の改正点】 | |
| 過労死の原因として考えられる脳・心臓疾患の労災認定については、平成13年12月にその認定基準が改正されました。 ①対象疾患を「疾患及び関連保健問題の国際統計分類10回修正」に基づいて疾患名 とされたこと。 この対象となる疾病は、 (1)脳血管疾患 脳内出血、クモ膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症 (2)虚血性心疾患等 心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む=不整脈によるものも含む)、 解離性大動脈瘤 ②長期間にわたる疲労の蓄積を業務による明らかな過重負荷として考慮することと されたこと。 「異常な出来事」及び「短期間の過重業務」のほか長期間(発症前おおむね6ヶ月間)にわたる疲労の蓄積についても業務による明らかな過重負荷として考慮されることとなりました。 その中でも最も重要な要因と考えられる労働時間の評価がなされ、その具体的な時間数が提示されました。 ③業務の過重性を客観的かつ合理的に評価するため、負荷要因と要因ごとの負荷の程度を評価する視点が示されたこと。また業務の過重性の具体的な評価に当たっては次に掲げる負荷要因について十分検討されることとなっています。 *労働時間 *不規則な勤務 *拘束時間の長い勤務 *出張の多い勤務 *交代制勤務・深夜勤務 *作業環境(温度環境・騒音・時差) *精神的緊張を伴う業務 具体的には過労死の原因となる主な疾患は、まず、循環器疾患(高血圧、虚血性心疾患)で、これらが基礎にあり、そこに過重な労働やストレスが加わると、心不全、心筋梗塞、致死性不整脈などが発症し死に至ることになり得る訳です。 脳血管疾患も同様で、その結果脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血などの形で発症します。 現在、特にこの数年、不況のため事業主も労働者もかなりの過重労働を強いられていると思われます。事業主は倒産を回避するべく、そして雇用される側はリストラの不安をかかえ長時間の労働やストレスの多い生活を強いられていると推測されます。また、いわゆるサービス残業も問題となっています。 実際、外来診療中、検査や入院を勧めても「そんなに休んだら(2・3日でもです)倒産してしまう」とか、「リストラされてしまう」という声を最近よく聞くようになりました。その結果検査や治療が遅れかつ不充分となり、種々の疾患を発症あるいは重症化させることになってしまいます。医師に検査や治療を勧められたら一度立ち止まってご自分の生命の大切さを考えていただきたいと思います。 過労死の要因として特に問題となるのが、今回の改正でも注目されている労働時間です。長時間労働が、心血管系に悪影響を及ぼすという多くの報告が今までにあります。週50~60時間以上の労働は、心血管系疾患の発症と密接な関係があり、長時間の残業を続けると過労死も増加する可能性が生じます。 1ヶ月45時間以内の時間外労働では健康障害リスクは低いのですが、月100時間または2~6ヶ月平均で月80時間を越える時間外労働では、業務と発症との関連性が強いと評価されるようになりました。 結局、長時間労働により、慢性の睡眠不足と疲労の蓄積とが関与して過労死を引き起こすような疾患が発症していると思われます。 次にストレス状況ですがストレスには職場から発生するもの以外にも、個人的要因、社会的要因など種々の原因が考えられます。 仕事面では、その内容によってストレスはかなり違ってきます。過重な内容でかつ自由度がない仕事ではストレス度は高くなり、それに職場内の人間関係や経済的な事、また個人の素因などが複雑に影響してきます。 これまでの報告ではストレスが血圧を上昇させ、その結果心血管疾患が発症すると考えられています。 また、仕事の要求度が高いのに自由度が低く、かつ 社会・職域での支援がなく孤立していると、虚血性心疾患が発症ないし増悪すると言われています。 | |
| 【当院での症例】 | |
|
最近外来で経験した症例を提示いたします。両者ともに職場での責任が大きく、ストレス、労働過重ともに大で、かつ慢性の疲労と睡眠不足の状態でした。 | |
[ 図 1]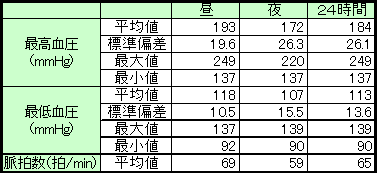 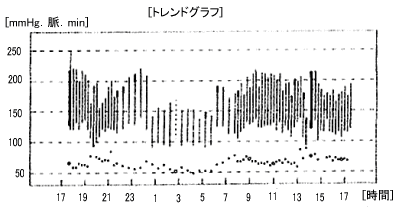 |
|
| 【今後の取り組みについて】 | |
|
過労死あるいは作業関連疾患の対策として、厚生労働省からいろいろな施策が行われています。 |
|
| (相川 礼子) |