![]()
| 亂1.僀儞僞乕僼僃儘儞乮IFN乯偲偼亃 | |
| 丂俬俥俶偼丄侾俋俆係擭偵擔杮恖尋媶幰偵傛偭偰敪尒偝傟傑偟偨丅偦偺屻偺尋媶偐傜僂僀儖僗姶愼偵傛傝懱撪偺嵶朎偐傜嶻惗偝傟僂僀儖僗偺憹怋傪幾杺偡傞嶌梡傪桳偡傞偙偲傗丄庮釃傪梷偊傞嶌梡傕桳偡傞偙偲偑敾柧偟傑偟偨丅枬惈崪悜惈敀寣昦丄懡敪惈崪悜庮丄恡娻側偳偵桳岠偲偝傟偰偒傑偟偨偑丄嵟嬤偱偼俠宆枬惈娞墛偐傜偺娞娻偺敪惗傪梷惂偡傞嶌梡傪桳偡傞偙偲傕擣幆偝傟傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅廬棃俬俥俶偵偼條乆庬椶偑偁傝傑偡偑丄俠宆枬惈娞墛偺帯椕偵桳岠偲偝傟偰偄傞偺偼俬俥俶兛丄俬俥俶兝偱偡丅俬俥俶兛偵偼揤慠宆偲堚揱巕慻姺偊宆偑偁傝傑偡偑丄俬俥俶兝偼揤慠宆偺傒偱偡丅 | |
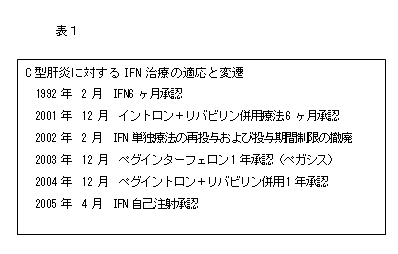 |
|
| 亂2.C宆枬惈娞墛偺帯椕亃 | |
| 丂侾俋俋俀擭俀寧偵俬俥俶偺俇儢寧搳梌偑彸擣偝傟丄寬峃曐尟偱姵幰偝傫偵堦夞偺傒偺搳梌偑壜擻偲側傝傑偟偨丅偦偺屻丄挿傜偔搳梌婜娫偺墑挿傗嵞搳梌偺昁梫惈偑妛夛側偳偱尵傢傟側偑傜傕夵慞偝傟傑偣傫偱偟偨丅偟偐偟丄暿昞侾偺傛偆偵偙偺係擭傎偳偱傗偭偲帯椕偺慖戰巿偑憹偟傑偟偨丅擔杮恖偺懡偔偑姶愼偟僂僀儖僗検傕懡偔帯傝偵偔偄堚揱巕宆侾倐宆偺俠宆枬惈娞墛偺曽偱傕儁僌僀儞僩儘儞偲儕僶價儕儞偺暪梡椕朄傪侾擭娫懕偗傞偲丄栺俇妱偺曽偑挊岠偵傕偭偰偄偗傞傛偆偵側傝傑偟偨丅俠宆枬惈娞墛偺曽偺帯椕偱偼崱屻偟偽傜偔偼偙偺暪梡椕朄偑帯椕偺拞怱偲側偭偰偄偔偺偼娫堘偄偁傝傑偣傫丅偙偙偱偼暘偐傝傗偡偔丄僂僀儖僗検偑懡偄曽偼尨懃儁僌僀儞僩儘儞偲儕僶價儕儞偺暪梡椕朄丄僂僀儖僗検偺彮側偄恖偱偼俬俥俶扨撈椕朄乮儁僌僀儞僞乕僼僃儘儞扨撈傪娷傒傑偡乯偲妎偊傑偟傚偆丅 | |
| 亂3.IFN帺屓拲幩亃 | |
| 亂a丗帺屓拲幩偑擣壜偝傟偨攚宨亃 丂俠宆枬惈娞墛偺姵幰偝傫偺恌椕偵偍偄偰変乆椪彴堛偺媶嬌偺栚昗偼娞憻娻偺梊杊偱偡丅偦偺偨傔偵丄姵幰偝傫偺擭楊丄惈暿丄娞墛偺恑傒嬶崌丄僂僀儖僗偺宆丄検側偳傪憤崌揑偵姩埬偟丄姵幰偝傫傪戝偒偔俀孮偵暘偗偰峫偊傑偡丅偡側傢偪丄嘆俫俠倁僂僀儖僗攔彍傪栚揑偲偟偨帯椕乮嫮偄帯椕偱傕偁傝暃嶌梡偑懡偄乯傪偡傞傋偒偐丄嘇俧俹俿偺埨掕傪桪愭偵偟偨俬俥俶帯椕傪峫偊傞傋偒偐丄偱偡丅偙偺偄偢傟偺帯椕偱傕俬俥俶帺屓拲幩偑桳岠側偙偲偑偁傝傑偡丅偙偺応崌帺屓拲幩偑擣壜偝傟偨偺偼俬俥俶兛惢嵻偱偡丅乮廡侾夞搳梌偑壜擻側儁僌惢嵻偼彍奜偝傟偰偄傑偡乯 嘆俫俠倁僂僀儖僗攔彍傪栚揑偲偟偨俬俥俶帺屓拲幩 丂俇俆嵨埲忋偺曽傗丄崅寣埑丄摐擜昦丄昻寣偺崌暪徢偑偁傞曽偱偼丄儁僌僀儞僩儘儞亄儕僶價儕儞偺暪梡椕朄偑峴偊側偄応崌偑偁傝傑偡乮屄暿偵偛憡択壓偝偄乯丅嫇帣婓朷偺庒偄曽偱傕峴偊傑偣傫丅偙偆偄偭偨曽偨偪偱偼丄斾妑揑懡偔偺検偺俬俥俶偺帺屓拲幩偵傛傞俀擭娫偺挿婜帯椕偺壜擻惈偑偁傝傑偡丅偙偺応崌丄帺屓拲幩偱偒傞棙揰偲偟偰丄栭娫偵拲幩偱偒傞偨傔丄暃嶌梡傪夞旔偱偒傞偙偲偑偁偘傜傟傑偡丅 嘇俧俹俿乮娞婡擻乯偺埨掕傪桪愭偵偟偨俬俥俶帺屓拲幩 丂擄帯惈偱偁傞偨傔偵條乆側俬俥俶椕朄傗丄俬俥俶亄儕僶價儕儞偺暪梡椕朄偱傕挊岠偵側傜側偐偭偨曽偱偼俧俹俿傪埨掕壔偟偰敪娻傪梊杊偟偰偄偙偆偲偄偭偨帯椕偵愗傝懼偊傞昁梫偑偁傝傑偡丅偙偺応崌偼俬俥俶兛惢嵻傪側傞傋偔彮検偲偟偰廡俀乣俁夞偺帺屓拲幩偱娞婡擻傪埨掕壔偝偣傞偙偲偑壜擻偵側傝傑偟偨丅 亂b丗帺屓拲幩偺幚嵺亃 丂奜棃扴摉堛偐傜俬俥俶帺屓拲幩傪姪傔傜傟偨姵幰偝傫偼丄俬俥俶兛惢嵻傪俀廡娫暘帩偪婣偭偰偄偨偩偒丄帺屓拲幩偟偰偄偨偩偒傑偡丅廬偄傑偟偰俀廡娫偵侾夞偼奜棃恌嶡偺昁梫惈偑巆傝傑偡偑丄捠堾偺晧扴偼悘暘偲寉尭偝傟傞偼偢偱偡丅扐偟丄弶傔偰俬俥俶傪懪偮曽偵嵟弶偐傜俬俥俶傪偍搉偟偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅嵟弶偺撪偼擖堾偁傞偄偼奜棃偱惓妋側俬俥俶偺懪偪曽偺巜摫傪偄偨偟傑偡偺偱丄偁傑傝晄埨偵巚傢傟偢偵壗偱傕憡択偟偰偔偩偝偄丅 | |
| 亂4.傑偲傔亃 | |
|
丂嵟嬤偼帯椕偺僈僀僪儔僀儞傕惍偄丄埲慜偵斾偟偰俠宆枬惈娞墛偺帯椕偺慖戰巿傕朙晉偵側傝傑偟偨丅娞墛傪恑峴偝偣偢偵娞娻傪梊杊偡傞娤揰偱暘偐傜側偄偙偲丄晄埨偵巚偆偙偲偼壗偱傕憡択偟偰偔偩偝偄丅 |
|
| 乮彫搰丂崃庽乯 |