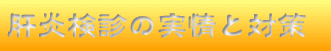
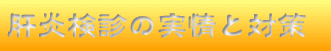
B型、C型肝炎ウイルスに感染していても、それに気付かず、進行した肝硬変症や肝癌になって初めて医師を訪れるという事例を多く経験します。また、肝炎とわかっていても病気の経過が長いために、適切な治療を施すチャンスを失ってしまった患者さんも少なくありません。今日はインターフェロンを中心として肝炎を完治させることも可能になり、あるいは肝炎の進行を遅らせ、肝癌の発生を防ぐことも現実になってきました。早期の発見が大切な理由です。 このため厚生労働省は平成14年度からB型、C型肝炎ウイルスの感染の住民検診を呼びかけています。この5年間に40歳以上70才まで、5才区分の区切りの年になったら検診を受ける節目検診と、肝炎ウイルスの感染を受けているかもしれないという条件を持つ人が受ける検診との二通りの方法で実施されてきました。しかし、実際の受診者は該当する人々の20〜30%前後でした。 検診がふるわなかった原因をいくつかあげてみますと、1)検診の趣旨が理解されにくかったこと、2)国民病としての肝炎の早期発見、早期治療の公衆衛生的目的なのに、個人の健康保持の受益者負担的発想で費用を徴収したこと、3)行政の取り組みが弱く、組織的な医療機関側の対応ができなかったことなどがあげられます。 節目検診よりも、第二の検診必要者の検診で2倍以上のウイルス感染者が発見されたように、検診を必要とする人々の条件をもっとはっきりさせなければなりません。当院での肝炎の患者さんから聞き取った事項をあげてみました。これはあくまで事例を拾い上げたもので、厳格に統計的手法をとって結論したものではありません。 |
|
| A:医療処置に関連して | |
| ・輸血を受けたヒト ・肝機能検査異常を指摘されたヒト ・出血の多い外科や婦人科手術を受けているヒト ・妊娠中、出産で大量の出血のあったヒト ・消化管からの吐血、下血の経験のあるヒト ・出血傾向のある病気とされたヒト ・注射を頻回に受けたことのあるヒト ・広い範囲のやけどをしたヒト ・皮膚移植など移植処置を受けたヒト ・新生児黄疸、先天性疾患として治療を受けたヒト ・医療従事者で針刺し事故、傷の表面に他人の血液がついたことのあるヒト ・平成6年以前に腎結石、胆石除去術、気胸の処置、骨折の治療などを受けたことのあるヒト |
|
| B:医療類似行為に関連して | |
| ・鍼治療を受けたことのあるヒト ・皮膚を傷つける、血を吸い出す民間療法を受けたヒト |
|
| C:日常生活での非衛生な行為 | |
| ・覚醒剤などの回し打ちをしたヒト ・刺青を受けたヒト ・化粧の目的で眉などに墨を刺したヒト ・素人同士でピアスをつけたヒト ・不特定多数と性交渉をもつヒト |
|
| D:社会生活、家庭生活に関連して | |
| ・母や家族に肝疾患があるヒト ・肝炎の多発していた地域に住んでいたヒト |
|
| E:20%のヒトは不明でした | |
| 趣旨の徹底には具体性が必要です。以上に掲げましたような項目に該当なさる方も積極的に検診をお受けになる必要があります。 | |
| (相川 達也) |