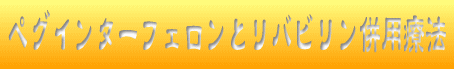
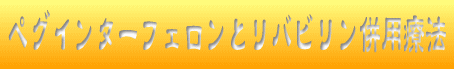
| 1992年インタ-フェロンが保険適応になってから、当院では今年の4月までに延べ、912名の患者さんにインターフェロン治療を実施してきました。この間、治療指針が何回も変更され、必ずしも福音とばかりはいえない事態が続いていました。2004年12月からペグイントロン(PEG)とレベトール(RIB)の併用療法が始められて、投与期間も延長され、大きな治療上の進歩が期待されるようになりました。 | |
| これまで本院でこの治療を受けられた方は78名になりました。 | |
| まだ48週間の治療が終了してから6ヶ月が経ちませんので治療成績の判定はできません。それで、現在、治療を受けるか迷っている患者さんや現在治療を受けていても治療結果が不安な患者さんの参考になるように今日の時点での当院での成績をまとめてみました。 治療の概要 治療を受けられた78名中治療開始から48週以上経過した方は41名で、うち11名はインターフェロン初回治療の方です。30名は二回目或いはそれ以上の治療になります。平均年齢は初回の方が57・5歳、二回目以上の方が57・3歳で、年齢構成は同じです。 全体で男女の比は24‥17となっています。 |
|
| 84%が治療終了時にウイルスが消えた | |
| スケジュールを全うした31名のうち治療終了時のウイルスが陰性化したのは26名(84%)でした。このうち13名(50%)の方は治療開始12週間以内にウイルスの消失を見ています(図)。初回治療と再治療以上の方 のウイルスの陰性化率はそれぞれ78%、86%でした。ウイルス量の多い方で80%、少ない方では100%でした。 |
|
| 追加治療もおこなう | |
|
従来の24週間のインターフェロン治療では治療を開始してから12週以内にウイルスが陰性化しない場合には完全にウイルスの排除ができた方はいなかったという経験から、今回、48週の治療が終了してウイルスが消えていても、12週以上たって遅れて陰性化した方には追加治療をおすすめしています。 48週投与の治療スケジュールを終了しても追加治療を受けている方は10名(42%)です。そのうち6名はウイルスは消えましたが、消失期間が短いために追加治療をしています。これまでの経験でいったんウイルスが陰性化し再燃した方ではさらなる治療をおこなうと究極的にはウイルスの消滅が可能であったことを踏まえ、このような治療方針をとっています。 また、48週の治療をしたにもかかわらず、ウイルスは定量法では測定限界以下ですが、わずかなウイルスをみる定性法では陽性の方が3名(10%)であり、この状態の方にも延長治療をおすすめしています。 |
|
| GPTの本当の正常値は25以下 | |
| 肝機能検査値としてGPTを目安に治療後の変動を見てみました。これまで、GPTの正常値は40以下と云う認識が世間相場としてありましたが、実際の正常値は20台、10台です。従ってインターフェロン治療中40以下でも、20台に達しない場合は再燃の可能性が高いとみられます。GPTが速やかに正常化することは治療効果に関係しています。GPTの正常化は治療終了した31人中、22人(71%)でした。ウイルスが陰性化してもGPTの異常が続き、インターフェロン治療が終了すると正常化した例もあり、インターフェロンの副作用のこともあります。 | |
| 治療中断の理由?まったくの無効は7% | |
| 4月30日現在、対象とした41名のうち何らかの理由で中断した方が10名(24%)でした。初回の治療の11名では中断した方は2名(18%)、二回以上の治療を受けた30名のうち中断した方は8名(27%)でした。 この気になる中断した10人の方の中断理由を見てみますと治療に全く無反応3名で、治療総数41名に対して7%でした。予定の治療スケジュールが終わるはずの患者さんの7%がインターフェロン治療に抵抗性であったと考えられます。全く治療に反応しなかったのは何故か、患者さん側の遺伝的、免疫学的条件、ウイルスの側の遺伝子の変異などを明らかにしなければなりません。 他の中断理由は交通事故1、糖尿病の悪化1,乳ガン1,肝癌1,吐き気など1,自己判断での中断1、他院へ紹介1となっています。 |
|
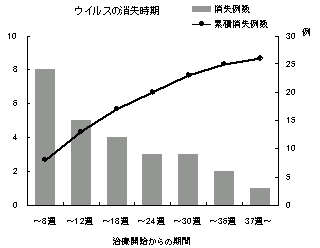 |
(医師 相川達也) |