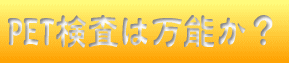
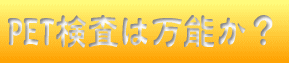
| 1:PET検査とは? | |
| a.ペットの検査ではない PETと書いて通常ペットと読みますが、犬や猫等のペットのための検査ではありません。従いまして今回の話題はもちろん動物病院での検査ではなく、人間を対象にした最近のトピックについてです。 b.PETは何の略? Positron Emission Tomography の略語です。日本語ではポジトロン(陽電子)断層撮影と言いまして、ごく簡単に表現しますと、自ら陽電子(放射線)を出す性質を持った薬剤(放射性同位元素)を、検査を受ける人の静脈に注射してその放射性同位元素の体内分布をポジトロンカメラで断層撮影する検査のことです。従来から行われてきた核医学検査の一種ですが、陽電子を放出することで他の核医学検査よりも解像度のよい画像が得られる利点をもっています。 c.X線CTとの違い CTは体外からX線を照射して体の内部の構造をみる検査です。これを形態学的画像と言います。一方、PET検査は利用する核種を工夫することによって体の中の機能を知ることができます。今盛んに行われているFDG(18Fフルオロデオキシグルコース)-PET検査は、ブドウ糖とほぼ同様の性質を持ったFDGを利用して体内での代謝活動を見ています。従いまして体内でブドウ糖をさかんに利用するような良性の病気(てんかん、虚血性心疾患)や、ある種の癌に大量に集積する性質を持っているのです。これを利用して作られる画像を機能画像と言います。 |
|
| 2:PETの特徴 | |
| a.全身の検索が一度にできる b.体内の臓器の機能を見られる c.腫瘍の増殖、悪性度の目安になる d.炎症の活動性を見られる e.治療に対する効果の判定ができる 等があげられます。簡単に表現すると、例えばある種の検診を受けたとします。その時にX線CTで体内に小さな腫瘍が見つかった場合に、良悪性の判断に困難を感じる場面でも、PET画像が加わると、それが増殖のさかんな、つまり悪性を示唆する病変かどうかの判断の大きな助けになるのです。 |
|
| 3:どのような利用をされているか | |
| 2002年4月からFDG-PET検査が保険で認められるようになりました。今はさらに対象疾患が少し拡大され、以下の疾患で認められています。 a.てんかん b.虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など) c.悪性腫瘍(脳腫瘍、頭頸部腫瘍、肺癌、乳癌、食道癌、膵癌、転移性肝癌、大腸癌 【症例1】、子宮癌、卵巣癌、悪性リンパ腫、悪性黒色腫、原発不明癌) しかしPET検査の実施に当たっては、実際はかなり厳密に制限されていまして、他の検査で有効な情報が得られない場合に実施が認められています。また、先にPETの特徴で述べました治療効果の判定などに用いることは現状では認められていません。今後はアルツハイマー型痴呆、炎症 【症例2】、サルコイドーシス、動脈硬化、骨腫瘍、神経内分泌系腫瘍等に適応が拡大されることが期待されています。 |
|
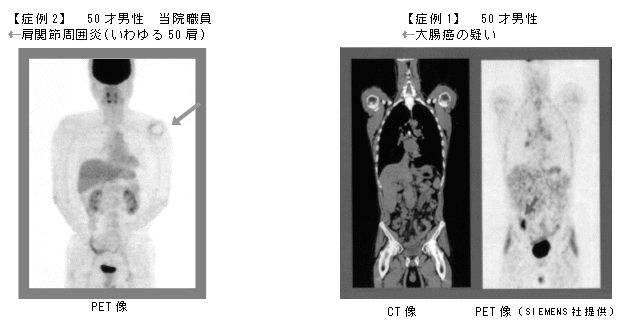 |
|
| 4:PET検査は万能か | |
| 国立がんセンターの内部調査で、PETによるがん検診では85%の癌が見落とされていたことが先に新聞報道されました。がんセンターでの約3000人の検診から150人で癌が見つかったものの、PETで癌と判定されていた人は23人(15%)しかいなかったというもので、残りの85%が見落とされ、他の超音波検査や内視鏡検査で癌が見つかっていました。 | |
| 5:PETをどう利用するべきか | |
| 国立がんセンターのデータでは、従来言われてきたよりもPET検診は万能ではなく、癌の早期発見には案外役立たないのではないかとの評価が一緒に報道されていました。私にはこれ以上のコメントを詳細に行い得るだけの自らの経験したデータは残念ながら持ち合わせていません。しかし、少し考えただけでもPETだけで万能とはとてもいえないのではないかと思います。つまり、今や日本人の4人に1人以上が亡くなる病気である癌は、基本的には各個人の老化現象に基づき、各個人ごとに全く多様な病態を見ることも決して珍しいことではありません。それを一つの検査で一括りに出来るほど癌はたやすい病気ではないのではないかと思うからです。やはり基本に従って従来の確立された検査(採血、超音波検査、X線撮影、CT、MRI)との組み合わせで慎重に診断していく必要があると思います。 | |
| 6:PET・CTの将来 | |
| 形態学的画像であるCTと機能画像であるPETを組み合わせて診断していこうという両者の長所を組み合わせたPET・CTが普及し始めています。現在はFDGという薬剤がPET検査の9割以上を占めていますが、今後はより工夫された薬剤を利用したり、他の検査手段を組み合わせて効率よく早期の癌を発見していく努力がなされていくと予想されています。 | |
| (医師 小島) | |