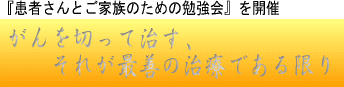
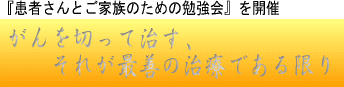
| 平成18年10月21日(土)、茨城県民文化センター小ホールにて、筑波大学臨床医学系消化器外科講師小田竜也先生と、相川内科病院院長荒崎圭介医師による講演会を無事開催することができました。 ここにご講演内容を、お忙しいなか小田先生に文章にしていただきました。 今回のタイトルを見て、「なんでもかんでもがんは手術すれば治るのだ」と言っている様に感じ方がいるかもしれません。もしくは、「何でも手術して治そうとしている“武闘派”の外科医の話か・・・」と思われたかもしれません。しかし、私が今日お話ししたい事は、そして常日頃考えている事は、それとはどちらかと言えば逆で、「手術などしないに越した事はない。ただ、それがもしもプラスマイナスのバランスを考えた上で、プラス面が一番大きな治療法ならば、逃げないで立ち向かって欲しい」という事なのです。 がんで亡くなられる方が私の回りにも増えてきました。皆さまの中にも、がんは怖い、がんにかかったら死んでしまう、と感じている方が多いと思います。しかし、人の命に限りがある事とがんは表裏一体の関係にあります。従って、不老不死の薬が無いのと同じように、がんを完全に無くす事は出来ないのだという事を、まず、お伝えしたいと思います。そうは言っても、がんは随分治る時代になってきたのも事実です。がんにかかった患者さんが5年後に元気でいる確率(5年生存率と言いますが)は全体で約50%です。さらに、がんの性質、5年生存率は種類によってまちまちで、例えば乳がんは80%以上、子宮がんは70%、大腸がん、前立腺がんは60数%といった具合で、がんにかかったからといってすぐに命がなくなる訳では無い事はお分かり頂けると思います。一方で、もちろん、油断のできる病気で無い事も確かです。6年ほど前に近藤先生と言うお医者さんが書いた「患者よ、がんと闘うな」という本が話題になりました。治療に伴うマイナス面を強調した内容で、効果が少ない割には大きな副作用を与えてしまう治療に対して警鐘を鳴らす役割を果たしました。しかし、がんと闘う事は一切意味が無いのだ、と皆さまが誤解してしまったとしたらそれは大きな間違いです。全ての治療はプラス面(病気を治す、症状を抑える・・・等)とマイナス面(副作用、合併症、後遺症・・・等)を持ち合わせていて、大切な事はそのバランスを考える事です。病気の種類によって、状態によって、個人個人によってそのバランスは全く異なりますので、治療法の選択の判断には注意が必要です。 |
|
| がんはなぜ発生するのか | |
| では、がんがどうして出来るのか、がんは遺伝子の病気だと言われるその所以についてお話いたします。我々の体は60?100兆個の細胞から出来ています。その全ての細胞の中に核(図書館)があって、その中に46本の染色体(設計図の本棚)がしまわれています。そして、その染色体には2?3万の遺伝子(設計図の本)がしまわれていて、その設計図は4種類の文字(DNA)を使って書かれた全部で30億字の内容です。お父さんの精子とお母さんの卵子から半分ずつの設計図を受け継いだ私たちの体は1個が2個に、2個が4個にという分裂を繰り返して100兆個まで増殖し、その後も古くなった細胞と入れ替わりに細胞が分裂を続けて何十年かの一生を過ごしていきます。細胞は分裂する度に設計図である30億字の遺伝子を全てコピーして次の細胞に受け渡します。紙の設計図の場合でも何回もコピーを重ねると数字や文字が読みにくくなってしまうのはお分かり頂けると思いますが、遺伝子の場合もコピーを繰り返しているうちに設計図にコピーミスが発生してしまいます。この遺伝子の傷は1つだけではなく、いくつもの傷が時間をかけて積み重なっていきます。その間違った設計図をもとに作られた不良品が、すなわちがんです。がんは生まれてからの一生の間に徐々に出来てくるもので、“がんは遺伝子の病気”と最初に言いましたが、お父さんやお母さんから子供にうつる“遺伝”とは意味が違います。 |
|
| 治療の第一歩は状態の把握から | |
| 私が専門にしている膵臓癌とその手術法の1つである膵頭十二指腸切除についてお話します。治療の第一歩は病気の状態を把握する事から始まります。①病気が膵臓の中に留まっている、②膵臓からはみ出しているが大切な血管には達していない、③膵臓の周りの大切な血管を巻き込んでしまっている、④離れた肝臓や腹膜へ飛び火(転移)している、の4つの状態です。①と②の方にはまず手術をお勧めします。それは、治療のプラス面、すなわち病気を治す力が最も高い治療だと考えられるからです。③の場合は手術のマイナス面が大きくなってしまうので放射線治療をお勧めしています。④の場合は色々な抗癌剤の治療がバランスが良いと思います。膵臓癌は結構手ごわいがんの代表ですので、手術で取り切れたからと言って決して安心する事は出来ません。ですから、①②の場合でも手術の後にだめ押しの抗癌剤治療を追加する事が多くあります。膵頭十二指腸切除という術式は時間のかかる大きな手術の1つです。従って、患者さんに与える負担も大きく、トラブルの率もそれなりに多く、術後退院まで2ヶ月、3ヶ月かかる事が珍しくありませんでした。しかし、技術の改良、経験の蓄積(それは私のという意味ではなく、長年の世界中の外科医の)によって、随分安定した手術になってきました。現在、筑波大学では膵頭十二指腸切除の手術後翌日には立って歩いて頂いています。3日目で水を飲み始めて、4日目から流動食、7日目に抜糸、14日目に点滴を抜いて、退院するのは平均22日です。平均という事は、14日位で退院出来る人もいるけれども、逆に、退院まで1ヶ月、2ヶ月かかる人が今でもいるのも事実です。昔は「この手術を受けるとひどい後遺症で寝たきりになってしまう」と言われたものですが、今は多くの方が普通の生活をし、仕事をしている方は元通りの職場に戻られる事がほとんどです。 |
|
| 最善の治療であるとと納得して闘う | |
| 医者は、医学は科学の一部でありたいと願っている部分があります。しかし、人間が金属やプラスチックでできた大きさや性質が均一な既製品でない以上、医学は科学になりにくい分野です。ですから、病気の治療方針について、こういう場合はどうする、ああいった人にはこの治療・・・という明快な方向性が示される事を期待して今回のお話しを聞いて下さったかたもいらっしゃるかと思いますが、実際にはマニュアル通りに行かない事が多々あります。いや、どちらかと言えばその方が多いと言えます。ですから、自分が、もしくは家族や知り合いががんにかかってしまったら、一般論に拘らずにその人にとってのプラスマイナスのバランスが適切な治療法はどれかを選んであげる事が大切です。治療を任せる医者は、杓子定規にマニュアル通りの治療しか提示しない医者ではなく、“その患者さんにとって”という視点を忘れずに治療にあたって下さるお医者さんが良いと思います。今はセカンドオピニオンといって、最初にかかったお医者さんだけでなく、色んな医者の話を聞くのが一般的な時代です。“ドクターショッピング”といって5ヶ所も10ヶ所もの病院を渡り歩いてしまう事は問題ですが、自分の命にかかわる事です。少なくとも2つ以上の病院で診てもらって適切な治療法を選んで、自分で“それが最善の治療である”と納得して“闘う”事をお勧めします。 | |
| ( 筑波大学臨床医学系消化器外科 小田竜也) |