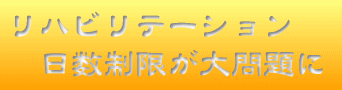
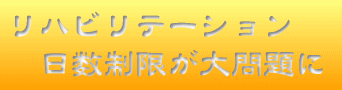
| リハビリが打ち切られる | |
| 本年4月の診療報酬制度改定で、リハビリテーション(以下リハビリと略)の日数制限が設けられることになりました。そのため、多数の患者さんがリハビリを打ち切られ大きな問題になっております。 全国保険医団体連合会(保団連)の調査ではすでに6873人以上がリハビリを打ち切られ、推計では全国で20万人を超す人がリハビリを継続できなくなるだろうと見込まれております。 日本リハビリテーション医学会で行なった専門家に対するアンケート調査でも「上限を設けるのは妥当」と答えたのはたったの7%にすぎません。56%が主治医が判断すべきこととしています。 |
|
| 4疾患に分類しリハビリ期間の上限を設ける | |
| 今度の改定によればリハビリ診療は「脳血管疾患など」「運動器」「呼吸器」「心大血管疾患」の4疾患に分類され、それぞれ180日から90日のリハビリ期間の上限が設けられました(表)。医療機関でのリハビリを終えた後は介護保険を使って自宅での訪問リハビリや通所リハビリ、あるいは鍼灸やフィットネスクラブなどを利用するほかはありません。しかし、現実には理学療法士が家庭を訪問してリハビリを行なう環境は出来ておらず、通所リハビリも個別の障害に対応できる内容にはなっておりません。鍼治療やフィットネスクラブに通うなどということも限られた人を除いては実行困難ですし、そもそもこれらはリハビリを補助することは出来てもリハビリに代わるものではありません。 | |
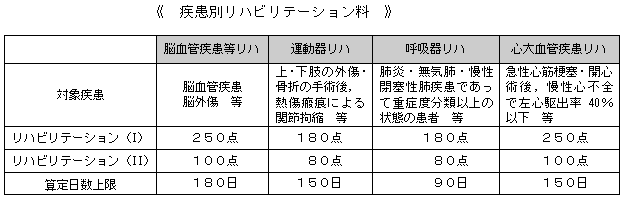 |
|
| リハビリの目的は人間の尊厳を回復すること | |
| 今度の改定はリハビリテーションの理念の根幹にかかわる重大な問題を含んでおります。疾患の種類や個人の条件によっては年余のリハビリにより徐々に回復することがあります。また、放置すればたちまち「廃用萎縮」に陥り、寝たきりになる人がリハビリにより機能を維持し、辛うじて人間としての尊厳が保てている例も多数あります。そのような人たちを機械的に180日でリハビリを拒否するというのは「180日で自立出来なかったら死んでもよい」というに等しいことです。反対・見直しの声が出るのは当然です。 現在、「保団連」などの医療関連団体や患者会などでつくる「リハビリ診療報酬を考える会」が中心となって制度の見直しを求め署名運動がなされております。すでに44万余筆の署名を厚労省に提出し、対政府要請行動や国会内集会がもたれています。 |
|
| (医師 斎藤禎量) | |