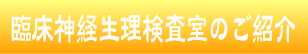
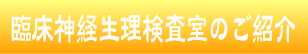
| はじめに | |
| 脳波検査、神経伝導検査などをまとめ、臨床神経生理検査と呼びます。その理由は、これらの検査が全て神経活動に伴う微細な電気現象を検出する点にあります。患者さんの病状を理解するためには、訓練された技師ないし医師が検査項目を適切に選んで実施し結果を総合的に解釈する必要があります。さもないと誤った記録が残り、優れた医師が解釈しようとも正しく診断できません。 | |
| 学会認定医・認定技師制度の発足 | |
| 日本臨床神経生理学会は2005年よりこの検査を専門とする医師・技師を認定する作業を始め、昨年8月第1回認定結果が公表されました。その数は日本全国で、脳波分野・神経伝導分野両方の認定医113名・認定技師40名、脳波分野のみの認定医128名・認定技師16名、神経伝導分野のみの認定医50名・認定技師2名です(これは「広告可能な専門性に関する資格」ではありません)。茨城県には、脳波分野・神経伝導分野両方の認定医が荒崎を含めて3名、脳波分野のみの認定技師2名が勤務しています。茨城県内で臨床神経生理検査を正しく実施しその結果をきちんと評価できる施設の一つが、当院です。 | |
| 当院臨床神経生理検査質の体制 | |
| 私たちは臨床神経生理検査をデジタル機器によって実施し、検査結果や報告書をコンピューターにより速やかに作成しわかりやすく表示しています。また、外部医療施設からの検査依頼にも対応できるよう準備を進めています。水戸周辺の先生方やその患者さんのため、安心して臨床神経生理検査を受けていただき信頼できる診断結果をお届けする体制を作るのが目的です。 | |
| 各検査項目の紹介 | |
| 臨床神経生理検査の各項目について、その目的、検査対象になりうる病気、方法についてわかりやすくご紹介します。 脳波検査(EEG) 〈目的〉意識障害、物忘れなどの症状が見られるときに実施する脳の機能検査です。脳の活動電位を頭皮上から記録します。頭部MRIやCTと併せて実施することで、脳の状態をより正確に把握することができます。 〈検査対象〉てんかん、頭部外傷後遺症、肝性脳症、アルツハイマー病など。 〈方法〉患者さんの頭部に約20個の電極を付け、ベッドに横になっていただきます。デジタル脳波計(写真1)を用い、安静閉眼状態で脳表面の活動電位波形を記録します。検査に伴う苦痛は全くなく、検査所要時間は60〜90分です。検査前日は可能であれば洗髪し、整髪剤などはつけないようにしてください。 末梢神経伝導検査(NCS) 〈目的〉しびれ感、痛み、力の低下、ふるえ等でお困りの患者さんに対し、その原因を発見するために行なう末梢神経の機能検査です。 〈検査対象〉手根管症候群、多発性神経炎(糖尿病性、アルコール性など)など。 〈方法〉目的とする患者さんの神経に皮膚の上から電気刺激を加え、デジタル筋電計(写真2)を用いてその神経自体またはその神経が支配する筋肉に誘発される活動電位波形を記録します。検査所要時間は30〜60分です。神経の電気刺激には人体への悪影響はありませんが、患者さんによっては多少の痛みを自覚することがあります。 針筋電図検査(EMG) 〈目的〉筋力低下、筋肉のやせなどを伴う運動障害の原因が、筋肉自体かそれを動かす神経にあるかを判断するために必須の検査です。痛みを伴う検査ですから、必要性を十分に考慮してから実施します。 〈検査対象〉多発性筋炎、頚椎症性神経根症、筋萎縮性側索硬化症など。 〈方法〉患者さんに力を入れたり抜いたりしていただき、検査の対象となる筋肉に針電極を刺し、デジタル筋電計(写真2)により筋活動電位波形を記録します。この検査は必ず医師が施行します。検査所要時間は調べる筋肉の数によりますが、30分程度です。筋肉に細い針を刺しますので、必ず検査に痛みが伴う点をご理解ください。 聴性脳幹反応(ABR) 〈目的〉耳(蝸牛神経)から脳幹までの聴覚路の機能検査です。客観的に聴力・脳幹機能が評価できます。 〈検査対象〉難聴 、聴神経腫瘍、多発性硬化症、意識障害、脳卒中など。 〈方法〉患者さんの頭部、耳朶に電極を付けてヘッドフォンから音を聞いていただき、誘発される電位波形をデジタル筋電計(写真2)により記録します。患者さんへの負担が全くない検査で、睡眠中も十分な検査ができます。検査に30分位かかります。 視覚誘発電位(VEP) 〈目的〉網膜から大脳皮質までの視覚路の機能検査です。視力低下や視野欠損を客観的に評価できます。 〈検査対象〉視神経腫瘍、多発性硬化症、脳卒中など。 〈方法〉パターンリバーサルVEPとフラッシュVEPの2種類があります。前者では患者さんの頭部に電極をつけ、格子柄が切り替わるブラウン管の画面を注視していただきます。それにより後頭部に誘発される電位をデジタル筋電計(写真2)により記録します。後者は光の出るゴーグルを顔に装着して同様の電位を記録するもので、意識障害のある場合に使用します。いずれの検査も30分位が必要です。 体性感覚誘発電位(SEP) 〈目的〉末梢神経から脳幹、大脳皮質までの感覚路の機能検査です。 〈検査対象〉多発性硬化症、脳梗塞、脊髄腫瘍、椎間板ヘルニアなど。 〈方法〉上肢刺激によるSEP検査では、患者さんの手首で正中神経に電気刺激を加え、頭部、首、肩部に付けた電極を用いてデジタル筋電計(写真2)により体表面から誘発電位波形を記録します。下肢刺激によるSEP検査では、患者さんの足首で後脛骨神経を刺激し、誘発電位波形を記録します。いずれの検査も30〜50分が必要です。 |
|
 [写真 1] デジタル脳波計 |
 [写真 2] デジタル筋電計 |
| まとめ | |
| 手足のしびれ感、脱力などの症状の評価には上に述べた検査が必ず必要となりますが、水戸周辺にはその実施が困難な医療機関が数多く存在します。拙書(町淳二、宮城征四郎編、日米比較に学ぶ「国民主役」医療への道、日本医療企画、375?381頁、2006年刊)にも書いた通り、このような症状にお悩みの患者さんはぜひ一度臨床神経生理検査を受けてください。正しい診断への足がかりとなるはずです。 | |
| 神経内科医師 荒崎圭介 臨床検査技師 堀江 薫 〃 住谷瑞穂 |
|