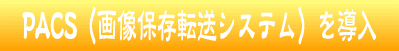
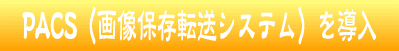
| 今日、コンピューターの進歩は目覚しく、いろいろな場所で生活を支えています。医療・福祉の現場でもコンピューターの担う役割は大きく、導入が進んでいます。日本では2001年1月に政府により「e-Japan戦略」が決定されました。これは、すべての国民が情報通信技術を活用し、その恩恵を最大限に享受できる社会の実現を目指し、基本戦略として掲げられたものです。続いて2001年12月、厚生労働省によって「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」が策定されました。これは「情報化が我が国医療の将来に大きな影響を与えるものであることを踏まえ、これを国として戦略的に進めていくことが極めて重要」とし、今後の望ましい医療の実現を目指そうというものです。これらの基本的戦略や目標の策定を受け、当院でも電子化を進めております。2006年12月に「フィルムレス」による診療を提供するために「PACS(パックス)」というシステムを導入致しました。「フィルムレス」とは、レントゲン写真、超音波の画像、内視鏡の写真など、今までフィルムや写真としてプリントしていたものを無くし、コンピューターの画面上で診断をするものです。コンピューターで画像を管理するシステムを「PACS」といいます。 | |
| [PACS画像を使用した診察風景] | 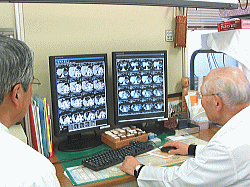 |
| PACSとは | |
| PACSとはPicture Archiving and Communication System(Picture=画像、Archiving=保存・管理、Communication=転送・通信)の略です。日本語では「画像保存転送システム」となります。CT、MRI、超音波や内視鏡など各検査室で撮影された画像はサーバーと呼ばれる画像を保存・管理するコンピューターに転送されます。そして各診察室、病棟のコンピューターから画像が呼出され、転送されます。これがPACSの基本的な仕組です。このPACSというシステムの基本概念は1985年から存在していましたが、実用的になり導入が進められるようになったのは2000年前後からです。この背景にはパーソナル・コンピューターの発展と通信技術の進歩、そしてそれらの技術の標準化があります。10年位前までほとんどの医療機器は専用の、そして各メーカー独自のコンピューターでした。高速に動作するコンピューターがまだ無かったこと、通信速度が遅かったこと(およそ今の100分の1)、医用画像について決まりが曖昧だったことが大きな理由です。PACSを使い医療機器どうしを繋ぐ事は出来たのですが、それよりもフィルムで画像を提供した方が速くて確実だったのです。画像診断の分野において各撮影装置の性能や画像の精度は年々向上して来ましたが、その性能を引き出せたのは医用画像規格の国際的統一化と工業分野の進歩といえるでしょう。各医療機器メーカーは国際規格に準拠したものを開発し、多くの部分でパーソナル・コンピューターを使用しています。PACSも特別なコンピューターを使用していません。各診察室に設置されたコンピューターもサーバーも私達が普段家庭で使用しているパーソナル・コンピューターと同じです。画像の呼出しにはインターネットの技術を使用しています。 | |
| 電子化は不可欠 | |
| PACS、電子カルテなど電子化の導入で得られるもの、提供できることは第一に「即時性」や「正確性」、そして「安全性」です。外来診察時において画像データ等が即時に、また正確にモニター等に映し出され、診療時間、及び待ち時間の短縮につながります。ただし、誰もが勝手に閲覧や保存ができるというわけではありません。画像の閲覧は暗証番号によって管理されています。また、各診察室のコンピューターにデータは保存されないため、物理的な盗難によって大切なデータが流出・悪用される心配は全くありません。そして最大の利点は「共有」できることと考えています。コンピューターを使えば同時に全ての診察室で同じ画像、同じカルテ情報を表示することが可能です。さらに院内のみの共有に留まらず、将来的には地域全体で情報を共有できるようになります。違う病院にかかっても写真を撮り直す必要はありませんし、紹介された病院へフィルムを持って行く必要もなくなります。いざという時、患者さまの情報は常に管理・保存され、いつでも・どこからでも利用可能となります。地域医療連携において電子化は不可欠と考えています。 | |
| (放射線技師 大友) | |