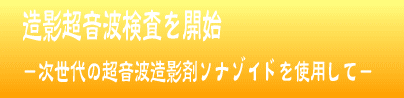
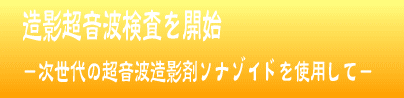
| 造影超音波検査と造影剤 | |
| 超音波検査における造影検査法は、血流に超音波造影剤としてマイクロバブル(微小気泡)を流して超音波画像上に臓器の血流動態を画像化します。装置から送信された超音波が血中のマイクロバブルに当たると、このバブルが共振、崩壊をします。この時に発生する超音波を高調波(セカンドハーモニック)といいます。この高調波を受信して断層画像をつくる方法をコントラストハーモニック法といい、通常の超音波画像よりもさらに良質の診断しやすい画像を得ることが出来ます。しかし、マイクロバブルは小さな泡のために超音波を当てると壊れて消失しやすく一過性でしか造影効果が得られず、臓器全体の走査を行うには複数回の投与が必要となる場合がありました。さらに最大の造影効果を確実に得るための条件に制限がありました。近年、より性能の優れた診断装置と感度の高い超音波造影剤が開発され、単なる造影画像の撮影だけではなく、機能的診断をもたせる利用法が検討されてきました。このような次世代の超音波造影剤の一つであるソナゾイドという造影剤が、去年10月に保険診療で使用できるようになりました。 ソナゾイドは、超音波によるマイクロバブルの崩壊が少なく、一回の投与で長時間の造影画像の撮影が可能となりました。さらに臓器血流の造影画像を得る他に、注射後に網内系細胞という特殊な細胞に取り込まれるために、超音波照射によるエコー信号でその造影画像が得られます。 |
|
| 肝腫瘍における造影超音波検査 | |
| 肝臓は造影超音波検査の中でも有用性の高い臓器です。特定された肝臓内の結節に対する検出能と診断能に優れており、さらには治療後の効果判定が可能となります。 リアルタイム画像は、注射直後はマイクロバブルが軌跡を描きながら肝内の血管の構造を造影し、その後に強い超音波を一瞬当てて一度気泡を壊しますと、再度造影剤が肝臓内を充満して特定された結節周辺の不正な腫瘍血管が造影され、さらには腫瘍の実質まで追うことが出来ます。この腫瘍血管の形態的な変化から良性悪性の鑑別診断が可能となります。また、ソナゾイドは、網内系細胞であり肝臓を構成する細胞の一つであるクッパー細胞に取り込まれて長時間細胞内に溜まる性質があります。しかし、肝細胞癌ではこのクッパー細胞は存在しないため、注射後早期に造影効果が消失し、周囲の正常組織に比べて造影画像は欠損像となります。さらにソナゾイドは、超音波によるバブルの崩壊が少なく造影効果が長時間持続しますので、特定された結節だけの走査だけではなくゆっくり落ち着いて肝臓全体を走査する事が出来ますので、それにより見逃されやすい1㎝以下の小さな病変の検出率が高まります。普通の超音波検査も比較的検出感度が高い検査ですが、さらに造影超音波検査を組み合わせると、CT,MRIと比べても肝腫瘍において感度のすぐれた検査の部類に入ります。 |
|
| 安全性が高く簡便 | |
| さらに、造影することにより肝臓癌の局所治療における病変位置を正確に把握し確実に治療を実施でき、治療後腫瘍周辺の血流動態を検査することで治療効果の判定が出来ます。 ソナゾイト使用による副作用の出現頻度は、CT,MRIで使用される造影剤にくらべて少なく、安全な造影剤と言われています。 いままで造影超音波検査は精密検査として行われていましたが、このように、薬液の取り扱いや造影剤を使用した造影超音波検査方法が簡便であり、日常のルーチン検査として取り入れることが容易となり、当院の超音波検査においてもソナゾイドを使用した造影超音波検査を導入して診療に役立てていきたいと考えています。 |
|
[症例] 原発性肝癌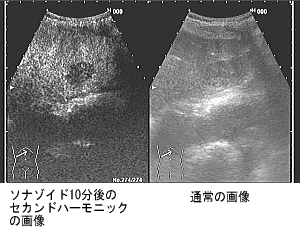 |
|
| (臨床検査技師 堀江) | |