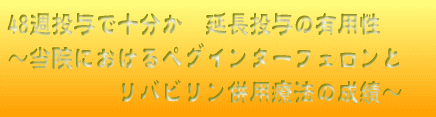
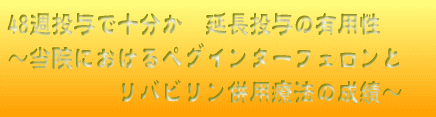
| 48週間のペグイントロンとリバビリン併用療法が、C型慢性肝炎の最近の標準治療法となっています。この治療法が導入されるきっかけになったアメリカの大規模治験で、難治性とされているウイルス遺伝子1型で著効率は46%でした(Friedら)。我が国でも、最新の厚生労働省の文書で40?50%とされています。著効とは48週間の治療後24週間してもウイルスが再出現しない状態(SVR)をいいます。公表された成績は治療導入のために行われた治療実験で得られたもので、治療を受ける患者さんは、すべて初回治療であること、各年齢層、男女が平等に含まれていることなど、厳格に選ばれています。 当院のデーターはこのような治療実験を目的としたわけではなく、初回治療の患者さん以外に、初回治療が成功しなかった患者さんや、高齢者がより多く含まれています。従って、基準とされている治療成績と直接に比較することはできません。 昨年、「ひろば」139号に治療開始後の中間報告を載せてあります。今回は治療成績が判定できる時期に至った患者さん70名について集計いたしました。 従来、インターフェロン投与後12週以内にウイルスが消失しない場合は著効を得られないとされていましたが、我々のこれまでの経験からは、初回治療で成功しなかった患者さんも再治療で著効が得られています。このような患者さんは初回治療で早期にウイルスが消失せずに12週間を過ぎた後におくれてウイルスが消えたいわゆる遅延反応を示す方々でした。このような患者さんは48週ではなくさらに治療を続けることで、著効を得られると考えて、実際に延長投与をおすすめしてきました。 表1が今回の70名の投与状況です。中止中断例が予想されたよりも多く問題になります。内訳を見ると、ウイルスが全く減少せず効果を期待できないと判定され中断した患者さんは9名で、全体の13%でした。副作用(糖尿病の悪化、吐き気、倦怠感、いらつき、湿疹)のため継続できなかった患者さんは4名(5・7%)、3名(4・3%)が乳ガン、肝ガン、交通事故で中止しています。1名(1・4%)は他医療機関への紹介となっています。 この70名名中、投与終了後来院しない8名と、IFN再投与開始の1名で効果判定が出来ず、効果判定の出来た61人で集計・分析をしました。投与中止・中断例も含めた著効率(SVR率)は36%で、通常の48週投与群は44%、延長投与1群は100%でした(表2)。
性別と年齢別のSVR率は女性7/25(28%)男性15/36(42%)で男性がやや高い傾向でした。5歳年齢区分刻みでのSVR率(図1)は、高齢の女性で著効率が低い成績でした。これは日本人で共通した成績で、原因は不明です。男性では年齢と治療効果は関係しませんでした。
さらに成績を検討する為に、効果判定の出来た48週投与36人について分析してみました(表3)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性・年齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVR率は全体で44%、女性36%、男性48%でやや男性のSVR率が高い様ですが、例数が少ないため、断定的なことはいえません。年齢区分での投与成績は61人の集計と同じ傾向でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セロタイプ別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVR率はグループ1で47%、グループ2が20%でしたが、有意の差はありません。通常成績が良いとされるグループ2のSVR率が低いのは、高ウイルス量の難治性の症例が対象とされているためと考えられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFN治療の既往 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既往無し10名(平均年齢60・3歳)、既往有り26名(平均年齢59・2歳)のSVR率はそれぞれ30%と50%で、既往有りの方がややよい成績でした。既往有りの方で、前回の成績が再燃(消失したウイルスが再出現)の人と無効(ウイルスが消えなかった)の人ではSVR率は71%、25%でした。症例が少ないため有意差はありませんが、一度ウイルスが治療で消失したのちに再燃した群では、以前の経験と同じく、成績は良好です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投与開始時のRNA量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVR群では平均1171KIU/ml、SBR(肝機能が正常だがウイルスの消失しない)群1035 KIU/ml、NR(肝機能検査異常でウイルスも消失しない無効)群2375 KIU/mlでNR群がVR群より有意にウイルス量が多いのが注目されます。(p<0.05)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイルス消失までの期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投与終了時にはウイルスが消失した方は31名(86%)であるのに、投与終了後24週の判定時には48%にあたる15名でウイルスが再出現しています。この場合、31名のウイルス消失までの期間は平均15・2週でした。これを効果判定別にプロットしてみると(図2)消失までの期間が短い方にSVRが多いことがわかります。SVR群では9・6週、SBR群では24・3週、NR群では19・9週で、SVR群と他の群ではウイルスの消失時期に有意の差がみられました(p∧0.05)。 効果が見られ、完治を目指し延長した延長投与の5名は、ウイルス消失までの期間は4週の一名を除いて、15,16,17,24週(平均18・0週)でした。48週で治療を終了すれば再燃した可能性が高いと思われますが、延長投与によって、5名全てがSVRとなりました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬剤減量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投与する薬剤量は投与開始時の体重によって標準投与量が決まっていますが、年齢や前回の投与状況などで投与開始時よりの減量や、投与中に副作用がみられ減量する事がよくあります。 今回もペグイントロンは81%、リバビリンは75%の方が減量投与をいたしました。しかし、どちらの薬剤でも減量の有無によるSVR率には差はありませんでした(ペグイントロンの減量有り群41%:無し群57%、リバビリンの減量有り群48%:無し群33%)。このことからも薬剤を減量してでも投与を続ける努力が大切です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投与開始時のALT値とSVR率は関係ありませんでした。また、ALT値が正常化するまでの期間も最終成績と関係がありませんでした。投与開始時の血小板数はSVR群では平均 16・7万、SBR群12・2万、NR群12・5万です。SVR群でやや多い傾向でしたが有意の差はありませんでした。また、投与開始時の赤血球数、ヘモグロビン値と成績とは関係しませんでした。 以上の検討よりウイルスが早く消失するほど最終成績は良いのですが、延長投与によりSVRとなることが経験されましたので、経過を慎重に見守って、無駄のない治療に心がけていきたいと考えます。また、薬剤を減量してでも治療を続けることが大切です。高齢になると成績が悪くなる女性は特に早めの治療開始が望まれます。 今後の問題として、効果が見られず中止した9名は初回投与は1名だけで、6名は2回目、2名は4回目の投与でした。このように何度投与してもウイルスの消失を見ない人たちにはウイルス学的、免疫学的、薬理学的にどのような違いがあるのかは未だ解明されていません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (医師 相川 達也) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||