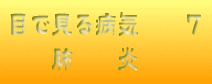
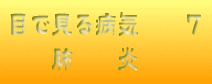
| 肺炎とは、さまざまな病原菌の感染によって肺に炎症が起こった状態のことです。一般的には、体力が落ちているときや高齢になって免疫力が弱くなってくると、かかりやすくなると言われています。
肺炎の原因となる細菌やウイルスは、呼吸をするときに鼻や口から身体の中に侵入します。健康な人は、のどでこれらの病原菌を排除することができるのですが、風邪などをひいてのどに炎症が起こっていると、病原菌が素通りして肺に入ってしまい炎症をおこしてしまいます。ただし、風邪にかかった全ての人が肺炎になるのではなく、肺に侵入してしまった細菌の感染力が人の免疫力を上回った場合にだけ発症します。 肺炎の主な症状はせき、発熱、悪寒、胸痛、喀痰、呼吸困難などで、これらの症状は数日間続きます。しかし、高齢者では食欲不振や元気がないなどの症状のみが前面に出る場合があるので注意が必要です。 身体所見としては、浅くて早い頻呼吸と頻脈がみられます。病変が高度であればチアノーゼ(くちびるや爪が青黒くなる)が認められることもあります。 平成17年の総死亡者数は108万4012人で第1位は悪性新生物(がん)、第2位は心疾患(心臓病)、第3位は脳血管疾患(脳卒中)、第4位は肺炎、第5位は不慮の事故となっています。内、肺炎の占める割合は9.9%で約11万人の方が亡くなられています。(厚生労働省:人口動態統計月報年計(概数)の概況より) |
|||
|
|||
| (放射線技師 鈴木) | |||