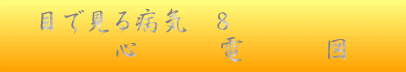
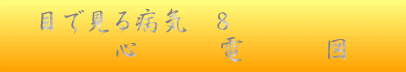
| 心電図とは、心臓の電気的活動を体表面から記録する検査です。その誘導法として、体の決められた部分に電極を装着し、さまざまな組み合わせの二つの電極の間の電位差を測定する「双極誘導」と、基準電極を設定し、それに対しての右手・左手・左足につけた関電極の電位を測定する「単極肢誘導」、関電極を胸部に装着して、その直下の心臓の電位を測定する「単極胸部誘導」があります。一般的にはこれらの合計12の誘導で検査を行います。 ◇正常心電図(図1・2) 一拍ごとに、P波・QRS群・T波の三つの波によって構成されています。 ◇期外収縮 不整脈の一種で、基本調律の心周期より早く心臓に興奮が生じるもので、その原因によりいくつかに分けられます。代表的な二つ期外収縮の例を挙げます。 ◇上室性期外収縮(図3) 心周期より早期に起こる興奮の原因がヒス束分枝付近より近位に存在するもので、異所性P波が出現しその後にQRS群が続いています。 ◇心室性期外収縮(図4) 基本調律であるP波を伴わない幅の広いQRS群が、基本調律のR-R間隔よりも早期に出現しています。 |
|
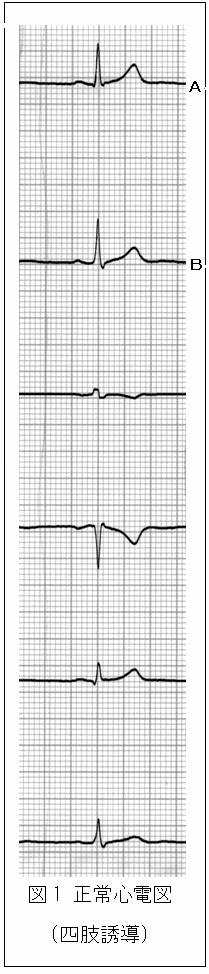 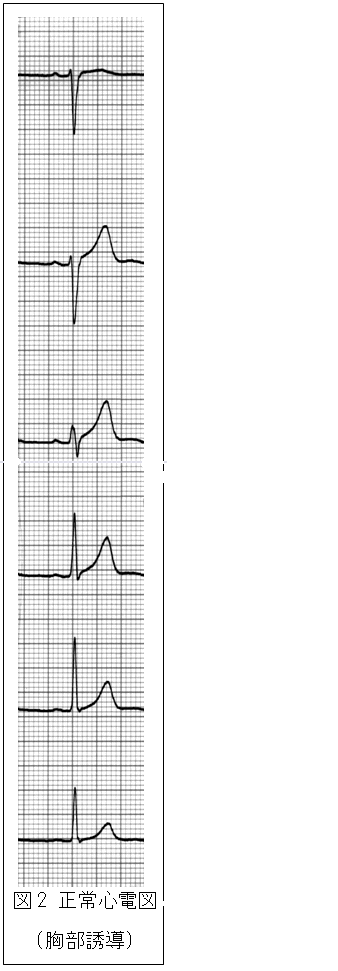 |
|
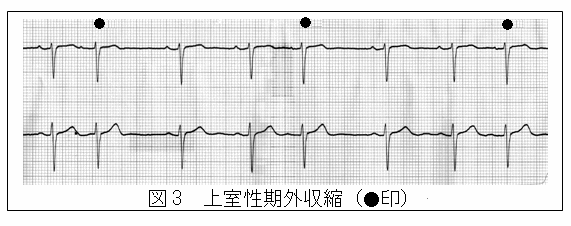 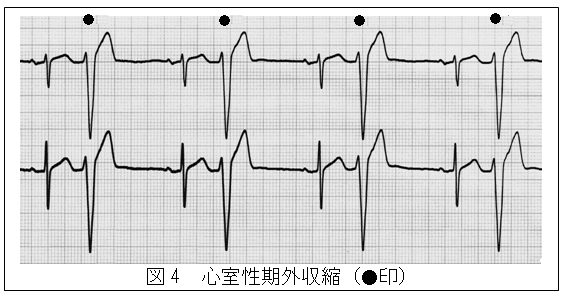 |
|
| (臨床検査技師 堀江) | |