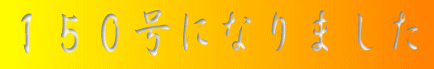
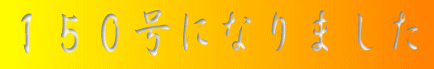
| 創刊から25年、当院の歴史がつづられた“ひろば”が150号となりました。生みの親の理事長、名付け親の 薬局長、現在の編集委員の上野が“ひろば”への思いを書きました。 |
|
| わたしにとっての“ひろば” | |
| “ひろば”はいうまでもなく医療機関としての法人相川会の機関紙です。 医師はよく言われるように時間貧乏で社会の動きに注目する暇がありません。そのため、社会と、殊に肝心の患者さんとの意思疎通が欠けてしまいます。それで、患者さんとの距離を埋めるために“ひろば”の発刊を思い立ったわけでした。そうして、決して短くない期間、定期刊行を続けてきました。患者さんが読んでいてくれたことが支えになっています。 医療の基本は患者さんと医療従事者との信頼関係が築かれているかどうかです。最近は患者さんを患者様と様付けしている医療機関が増えました。患者さんはお客様ですと規定していますが、医療の持つ多様な性質をその一面でしかない経済活動に矮小化してしまいました。患者さんから承諾書に署名捺印したかどうかが裁判での争点になってもいます。 かつて医の倫理を表す「医は仁術」という言葉がありました。この道を外れた医師をみて、マスコミなどは「医は算術」と揶揄しました。しかし、今、医の仁術を語るものはありません。算術に徹しなければ医は成り立たないなどと経済諮問会議の資本家やその意をくんだ役人、大勢のコンサルタントが合唱しています。安心して医療に専念できない環境のため、多くの医師が大切な職場から退去しています。学んだ技術や学問を捨てる辛さを資本家や当局は理解できないのです。医療は着実に崩壊の途をたどっています。 私は学生時代に国民皆保険のキャンペーンに荷担して多くの友人たちとともに東北地方の農村に出かけました。社会保障の大切さを身をもって学びました。そして半世紀、今、保険制度は壊されつつあります。老人を厄介者扱いにして、医療を遠ざけるだけでなく、年金から保険料を天引きしてお年寄りの生活をも圧迫しようとしています。 “ひろば”150号はそんな時代をも記録していきたいと考えています。我々がその日その日の現場での体験を記録するとき、やがて、意図したわけでなくとも、大切な歴史の証言になることでしょう。 今後も、患者さんとの信頼を大切にして、知り得た知識を皆さんにお届けいたします。 (理事長 相川達也) |
|
| 創刊当時の思い出 | |
| 創刊号以来、隔月発行を続けた“ひろば”は今回150号となりました。年6回の発行ですので、延々25年間続いたことになります。休刊することもなく発行し続けられたのも、代々編集に携わった方々の地道な活動の結果だと思います。 今、私の手元に創刊号がありますが、タブロイド版1枚2ページの新聞で、発行年月日は昭和58年8月1日となっています。 昭和58年は相川内科病院が開設してから5年がたった年です。当時はまだ職員の数も少なく、現理事長の相川先生が院長でした。25年も前の事ですので記憶も定かでないのですが、院長の発案で5年を1つの節目として新聞を発行しようという企画がだされ、まず新聞の名前を職員に募りました。私も応募した1人ですが、新聞をつうじて職員と患者さんとが交流し、医療に関する情報を共有できる、そのような場になればと思い“ひろば”と言う名前を書きました。結局この名前が採用され現在に至っています。賞品としていただいた本は今でも我が家の本棚に並んでいます。 創刊号以来の“ひろば”をめくっていますと、医療に関する時代の流れや、時々の医療現場の様子などを読み取ることができ、なかなか面白いものです。最近は病院からの情報発信のみとなっていますが、患者さんからの窓口も開いています。一緒に“ひろば”に参加しては如何でしょうか? (薬剤師 増田照子) |
|
| “ひろば”の歴史 | |
| 相川病院は医院として昭和53年に開院しました。落ち着く間もなく待合室や受付、薬局の増改築、検査室の移転など診療や施設の整備に追われた5年間だったのだと思います。やっと少し日々の診療を振り返る事が出来るようになり、昭和58年に第1回糖尿病教室を開催し、8月1日には“ひろば”を創刊しました。 当初は裏表の2ページでしたが、情報を載せきれなくなり第6号から4ページとなりました。編集は山本たまえさんを中心に4、5人で組織するひろば編集委員が担当していましたが、実質的には平成12年(102号)まで山本さんがほとんど編集をしていました。その後磯野由岐子さんが引き継ぎ、大縄明子さん、長谷川智子さん、そして現在上野ちさと、川又直美が割り付け編集をしています。 創刊当初は国立水戸病院の現役バリバリの先生方や東北大学の高名な先生の記事も多く、医学知識の啓蒙的な役割を果たしていたように感じます。現在のように最新の情報が簡単に得られる時代ではなかったのだと思います。肝炎についてはアルコール性肝炎や禁酒指導の記事が多く、その後脂肪肝、薬剤性肝炎、ウイルス性肝炎と移ってきています。小林さんが編集していたころは患者さんの投稿記事、患者さんにアンケートをとり集計した記事、患者さんへのインタービュー記事、職員の各職場の記事や働いているときの写真もたくさんあり、みんなで創っていることを実感させるような暖かみのある“ひろば”です。 次に引き継いだ磯野さんは美術を専攻していただけに、とてもすてきな挿絵や吹き出したくなるようなユーモアのある挿絵を上手に取り入れています。文字のスタイルや背景模様なども、常に新聞などから集めていたのを記憶しています。介護老人保健施設「つねずみ」や病棟の行事がふんだんに掲載され楽しい“ひろば”です。 大胆に割り付け編集を知る大縄さん、記事を区切る一本の線や余白にまでこだわりきれいな仕事をする長谷川さん達を経て現在に至っています。 昨今は患者さんも専門的な最新の医療情報をご存知で、“ひろば”に掲載する医療情報も高度な内容になってきています。出来るだけ雑誌やテレビからでは得られない病院で独自に研究集計したデータを載せるように努力しています。また、病院の広報誌であっても社会問題抜きには語れない時代だと考え、くるくる改悪される医療制度、介護保険制度、社会問題も情報として載せております。ただ、以前と比べ編集にゆとりがなく、患者さんと職員とがみんなで集うと言う雰囲気が希薄になっていると感じています。これからも試行錯誤しながらみんなの“ひろば”を発行し続けたいと思います。 |
|
 |
(ひろば編集委員 上野) |