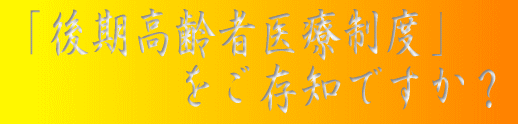
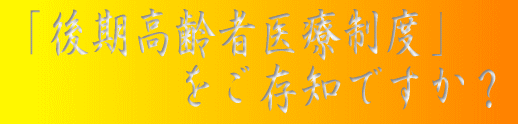
| 本年4月から「後期高齢者医療制度」がスタートすることをご存知でしょうか。 この制度は2006年6月自民、公明両党が強行採決した「医療制度改革関連法」の一つとして行われるものです。この制度が実施されますと75歳以上の高齢者に極めて深刻な事態が生じます。制度の内容が知れるにしたがい、中止・撤回を求める運動が各地に広がり、運営主体となる市町村からも次々と手直しや中止の意見書が提出されています(水戸市議会でも「意見書」を採択しました)。どんな制度か、その問題点を見てみましょう。 |
|
| 強制加入と高額保険料−年金から天引き | |
| 75歳以上の高齢者は、それまで入っていた国保や健保を脱退させられ、あるいは家族の健保の扶養家族の資格を停止され、すべてこの制度に組み入れられます。そして該当者すべてから新たに「後期高齢者医療保険料」が徴収されます。 保険料は、月額1万5千円以上の年金受給者は否応なしに年金から天引きになります。茨城県の場合は1人平均69,355円(月5千8百円)と見込まれています。介護保険料と合わせると月1万円近くになります。特に保険料増額が著しいのは、それまで保険料負担のなかった75歳以上の「扶養家族」の場合で、一挙に4万5千円/年も新たに徴収されることになります。夫が75歳以上、妻が74歳以下の場合は、夫が「後期高齢者保険」に入り、妻が「国民健康保険」に加入し、両方の保険に保険料を払う事になります。 今回の制度導入にあわせ、国保に入っている65〜74歳の年金生活者も国保料の年金天引きが予定されています。こうなると「分納」や「猶予」の相談も出来なくなり、75歳以上と限らず、すべての高齢者が生活困窮に陥る心配が生じます。 |
|
| 増える自己負担と「包括払い」で医療の制限 | |
| 保険料負担が増えるだけでなく、高齢者が医者にかかりにくくする仕組みも作られようとしています。 まず、窓口の自己負担が1割ないし3割に増えます。同時に、74歳以下の人も窓口負担が原則3割に増額される予定です。自己負担が増えるだけではありません。この制度の発足にあわせ、「包括払い」の実施が検討されています。 「包括払い」というのはどんな検査や治療をしても医療機関への保険上の支払い(診療報酬)は同じ額になります。つまり、病院・診療所は検査や治療をやればやるほど持ち出しになってしまいます。そのため必要な検査や治療もなされず、手のかかる患者は敬遠され病室から追い出される事になりかねません。患者さんはもちろん、医療機関にとっても重大な問題です。 |
|
| 保険料を払えなければ保険証の取り上げを | |
| 高齢者においては家計の実態と人道的な観点からこれまで保険料が払えなくとも保険証の取り上げは行われませんでした。しかし、本制度のもとでは保険料が払えなくなれば情け容赦無く保険証を取り上げられます。そうなると受診の際には医療費全額を自己負担しなければなりません。金銭的に困窮したうえに、保険証も取り上げられては悲惨な結末を待つばかりです。 |
|
| 現代版「姥捨て山」の医療制度−中止、撤回を | |
| 有無を言わせず保険料を納めさせ、制限を設けて医療を受けさせない。さらに現役世代個々人の給与明細書に高齢者のための特定保険料という形で「後期高齢者医療制度」の分担金として移行する割合分を別記し、世代間の対立を煽り、高齢者に肩身の狭い思いをさせる「いじめ」のようなことまで折り込んで制度の執行をはかる。まさに現代版悪質な「姥捨て山」と言っても過言でないでしょう。このような人道にも反する制度は中止、撤回すべきです。 | |
 |
医師 斉藤 禎量 |