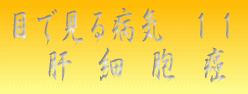
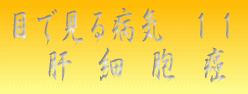
| 肝細胞癌の早期診断のためには、肝硬変などの慢性肝障害患者に対し、定期的に画像診断の検査を行う事が重要となります。また、近年、目覚しい進歩を遂げた各種画像診断を複数組み合わせることにより、スクリーニング検査から確定診断にいたるまでの早期診断体系の成果が確実に上がっています。 当院においても、超音波検査、CT検査、MRI検査、血管造影検査を組み合わせた診断体系で、肝細胞癌の早期診断に努めています。 ここに当院においての肝細胞癌の症例を提示します。 |
|||||||||||
| 【症例 Ⅰ】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 【症例 Ⅱ】 | |||||||||||
|
|||||||||||
| (臨床検査技師 堀江) (放射線技師 大友) |
|||||||||||