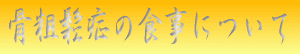
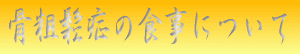
| さる5月17日看護の日・健康フェアーがコアクリニックにおいて開催され、なかでも骨密度の無料測定には順番を待つ方で常に行列ができていました。骨密度の測定後、数値の低さにショックと困惑の表情を浮かべて栄養相談に来る方もいらっしゃいました。そこで、今回は骨密度に関係した骨粗鬆症の食事療法についてお話したいと思います。 骨粗鬆症とは骨量の減少を示す全身性疾患で、骨微細構造の劣化により骨脆弱性と易骨折せいを示す疾患であると定義されています。(国際骨粗鬆症シンポジウム) 骨量減少による自覚症状はほとんどないのですが、日常の小さな外力が加わっても容易に骨折してしまう骨状態です。成因としては遺伝的要素に加え加齢に伴う骨量の減少、閉経によるエストロゲン(ホルモン)の減少、運動不足による骨への負荷不足、カルシウム摂取の不足、ビタミンD不足によるカルシウム吸収障害、その他飲酒、喫煙、過度のダイエット、食塩・インスタント食品の過剰摂取などです。 食事療法としては、カルシウム目安量(18〜29歳男900mg・女700mg)を十分摂取すること。カルシウム吸収に必要なビタミンDと、骨量増加作用のあるビタミンKを積極的に摂取すること。インスタント食品、加工食品に多く含まれるリン(保存料や結着剤に使用されている)はカルシウムの吸収が障害されるため控えること。食塩の過剰摂取はカルシウム排泄を促進するため10g以下/日にすることが主なガイドラインです。 献立としては、吸収効率の良い牛乳・乳製品を積極的に活用し、献立が偏らないようにカルシウムの多い小魚、大豆食品、緑黄色野菜、海藻類など、また、ビタミンDを含んだ魚介類(かつお、ぶり、いわし、さんまなど)も併せて取り入れます。よくカルシウムの多い食材でほうれん草が挙げられますが、シュウ酸が多く吸収効率はよくありません。ご家庭の料理で、牛乳を使ったシチューやグラタン、ヨーグルトドレッシングなど、オムレツにチーズを混ぜたり、スキムミルクを肉団子や小麦粉にまぜたりしてみてはいかがでしょうか。また、切り干し大根やひじき煮を献立に多く取り入れたり、桜えびやごま、じゃこなどのふりかけもいいでしょう。 同時に運動で骨に刺激を与えて丈夫な骨を作り、日光浴でビタミンDを活性化させます。ただし、カルシウムには強化食品やサプリメントが多く市販されており、治療薬を服用する場合などカルシウム過剰摂取(2300mg/日以上)にならないよう注意が必要です。 |
|
| (管理栄養士 高野) |
|