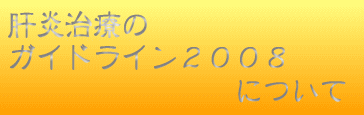
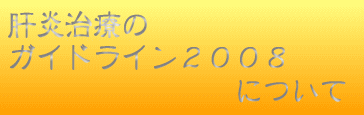
| 【はじめに】 | ||||||||||
| 病気の治療のガイドラインは古くから存在しました。しかし、現在様々な疾患で作成されている“治療のガイドライン”とは、日本国内の医学系各学会や厚生労働省の研究班などによって、なるべく客観的な証拠に基づいて、専門医、一般医のみならず患者さんにも分かりやすくまとめられたものを指すことが多くなってきました。また、分野によっては米国やヨーロッパで策定されたガイドラインを話題にすることもあります。このような背景には医学が各分野で急速に進歩し、専門医といえども中々最新の有効な治療を熟知することが難しくなってきたことと、治療に際して患者さんへの分かりやしい説明が求められるようになっている社会環境が強く影響しています。今回は日本の厚生労働省の「B型およびC型肝炎ウイルス感染者に対する治療の標準化に関する臨床的研究班」の策定した“C型慢性肝炎治療ガイドライン2008”に関しての話題です。 |
||||||||||
| 【C型慢性肝炎治療の変遷】 | ||||||||||
| 1. 1992年にC型慢性肝炎に対する抗ウイルス治療法としてインターフェロン治療が保健適応になりました。しかし、「遺伝子型1bの高ウイルス量」の患者さんではウイルス排除率は約5%と低率でした。 2. 2001年11月からはイントロンA(インターフェロンα2b)とリバビリンの併用療法が認可されました。「遺伝子型1bの高ウイルス量」の患者さんでもウイルス排除率は約20%と改善されました。 3. 2004年12月からは週1回の投与で治療可能なペグイントロン(ペグインターフェロンα2b)とリバビリンの併用療法が認可されました。これにより「遺伝子型1bの高ウイルス量」の患者さんでも48週間の投与で約50〜60%のウイルス陰性化率が達成されました。 4. 2005年12月からは「遺伝子型1bの高ウイルス量」以外の患者さんにもペグイントロンとリバビリンの併用療法、24週間投与が認可されました。約90%のウイルス陰性化率となっています。 |
||||||||||
| 【C型慢性肝炎の治療ガイドライン2008】 | ||||||||||
| 厚生労働省の研究班の策定した肝炎治療ガイドラインも2005年以来今年で4年目になりました。表を参照して下さい。 1. 基本的な考えは、患者さんのa.年齢、b.性別、c.ウイルスの型、d.ウイルス量、e.合併症等を考慮して、ウイルス排除をさせる治癒を目的とした治療をするか、ウイルス排除はあきらめて肝機能を維持して肝硬変が進行しないようにする治療を選択するかをよく検討することです。 2. 次に初回の治療なのか、以前医インターフェロン治療でウイルス排除ができず再治療を考慮しているかで治療内容が異なってきます。再治療はウイルスの型やウイルス量にかかわらずペグインターフェロン、リバビリン併用療法が基本です。 3. ウイルス量の多い患者さんの初回治療で治癒を目的とする場合には、ペグインターフェロン、リバビリンの併用療法が基本です。 4. ウイルス量の少ない患者さんでは、治癒を目的とした初回治療ではインターフェロン単独治療が基本です。実際には多くの患者さんが週1回投与の可能なペグインターフェロン単独治療法を希望されます。 5. 治癒を目的としない進展予防の場合にはインターフェロンの間欠、少量投与を試みます。この療法は在宅自己注射が可能となっています。 6. インターフェロン治療自体が困難な場合ではウルソ(ウルソデオキシコール酸)、強力ネオミノファーゲンシー等の投与、瀉血療法などを組み合わせます。 7. このガイドラインでは、遺伝子型1bの高ウイルス量の方で治療開始後ウイルスが中々消滅しなかった方では治療期間の延長が推奨されています。 |
||||||||||
| 【個々人の治療をどう決めるか】 | ||||||||||
| 今の時代は治療方針を決める際に、患者さんが医師などの医療関係者から十分に説明を受け、よく納得することが何より必要とされています。しかし、患者さんの限られた知識と理解力(医学的な知識の基板がないので限定されているはず)でわれわれ医療側と全く同じ基準になれるわけは実際にはありません。また、ペグインターフェロン、リバビリン併用療法の水晶年齢上限が65〜70歳であるように、患者さんの年齢によって治療が異なる場合も多いのですが、それも各患者さんの肉体の実年齢はバラバラです。従って治療を決める際に何より大切なことは、何でも気軽に相談できる所謂“インターフェロン治療の主治医”を持って、年齢、性別、ウイルスの型、ウイルス量、合併症など様々な条件を勘案し、最終的にもっとも大切である本人の希望をいれて治療方針を決定していくことです。当院でもなるべく医師から説明の時間は取るように努力はしておりますが、外来の限られた時間では中々満足な説明になっていないことも多いようです。そこで、院内の規約でインターフェロン治療の説明になれた看護師(インターフェロン治療コーディネーター)を養成し説明に当たってもらっています。詳しい説明をご希望の患者さんは医師またはコーディネーターまでご遠慮なくお申し出ください。 | ||||||||||
■C型慢性肝炎に対する初回治療ガイドライン■
|
||||||||||
| ■C型慢性肝炎に対する再治療ガイドライン■ C型慢性肝炎に対してIFNの再治療は初回治療の無効の要因を検討し、治癒目的の治療か、進展予防(発癌予防)を目指したALT値の正常化、あるいは安定化のための治療法を選択すべきである。 1.初回IFN無効例への再投与はIFN+リバビリン併用療法が、治療の基本である。 2.リバビリン併用療法の非適応例あるいはリバビリン併用療法で無反応例では、IFNの長期投与が望ましい。なお。IFNα製剤(Peg製剤を除く)は、在宅自己注射が可能。 3.IFN非適応例およびIFNでALT値の改善が得られない症例は肝庇護剤(SNMC、UDCA)、瀉血療法を単独あるいは組み合わせて治療する。 4.進展予防(発癌予防)を目指した治療のALT目標値はstage1(F1)では、持続的に基準値の1.5倍以下にコントロールする。stage2〜3(F2〜F3)では、極力正常値ALT≦30IU/Lにコントロールする。 5.リバビリン併用療法を行う場合には治療効果に寄与する因子である、年齢、性別、肝疾患進行度、HCVウイルスの遺伝子変異(Core領域70,91の置換、ISDR変異)などを参考にし、治療法を選択することが望ましい。 |
||||||||||
| (医師 小島 眞樹) | ||||||||||