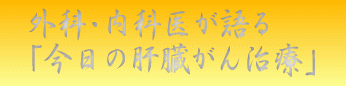
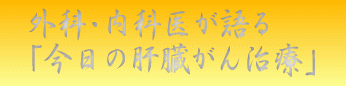
| 丂2008擭10寧18擔乮搚乯偵拀攇戝妛椪彴堛妛宯島巘偺暉塱寜愭惗偲摉堾偺彫搰崃庽暃堾挿偵傛傞乬姵幰偝傫偲偛壠懓偺偨傔偺曌嫮夛乭傪奐嵜偟丄摉擔偼栺240柤偺曽偵偛挳島偄偨偩偔偙偲偑偱偒傑偟偨丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅 | |||
| 亂娞娻傪撍偒巭傔傞亃 | |||
| 亂偼偠傔偵亃 丂傢傟傢傟偑壗偐傕偺傪扵偡偲偒偵偼偳偺傛偆側峴摦傪偲傞偱偟傚偆偐丠埮塤偵懳徾偲偡傞傕偺偵撍寕偡傞傛偆側偙偲偼傑偢偟傑偣傫丅椺偊昁偢尒偮偗傞傫偩偲丄擱偊忋偑傞傛偆側擬堄傪帩偭偰偄偨偲偟偰傕丄帠慜偺忣曬廂廤側偔扵偡峴摦偵弌偨偺偱偼嬌傔偰岠棪偑埆偄偙偲偑懡偄偐傜偱偡丅幚嵺偵偼杮傗僀儞僞乕僱僢僩偁傞偄偼偦偺摴偵挿偗偨恖偵傛偔榖傪暦偄偰偐傜枩慡偺弨旛傪偟偰扵偡峴摦偵堏傞偙偲偑晛捠偱偡丅娞娻傪撍偒巭傔傞偙偲傕摨條偱偡丅娞娻偼埮塤偵尒偮偗傛偆偲偟側偔偲傕丄崱傑偱偺摑寁偐傜嬌傔偰敪徢昿搙偺崅偄廤抍偑柧妋偵側偭偰偄傑偡丅懄偪俛宆丄俠宆偺娞墛僂僀儖僗偑枬惈偵姶愼偟偰偄傞曽偐傜崅棪偵敪徢偟偰偒傑偡丅偮傑傝丄娞娻傪撍偒巭傔傞偵偼僂僀儖僗惈偺娞墛丄娞峝曄偺曽偨偪傪廳揰偵傒偰偄偔偙偲偑嬌傔偰廳梫側偙偲側偺偱偡丅 亂崅婋尟孮傪埻偄崬傓亃 丂暯惉侾俉擭偺摑寁偱偼慡晹埵偺娻偺巰朣憤悢偼俁俁枩恖丅偦偺偆偪抝惈偱娞娻偼戞俁埵丄俀枩俀愮恖梋傝丄彈惈偱偼戞係埵丄侾枩侾愮恖梋傝偑朣偔側偭偰偄傑偡丅慡娻巰朣悢偺栺侾妱偺曽偑娞娻偱朣偔側偭偰偄傑偡丅偦偺娞娻偺栺俉妱偑俠宆枬惈娞墛偁傞偄偼俠宆娞峝曄丄栺侾妱偑俛宆枬惈娞墛偁傞偄偼俛宆娞峝曄偺曽偱偡丅娞娻傪撍偒巭傔傞偨傔偵傑偢俛宆丄俠宆娞墛僂僀儖僗偑枬惈偵姶愼偟偰偄傞曽乆傪埻偄崬傓偙偲偑廳梫偱偡丅偝傜偵丄抝惈丄崅楊丄傾儖僐乕儖懡堸摍偺場巕偑壛傢傞偲梋寁偵婋尟惈偑憹戝偡傞偙偲傕傢偐偭偰偄傑偡丅 亂娻傪梊杊偡傞亃 丂忋婰偺傛偆偵崅婋尟孮偑偼偭偒傝偟偰偄傞偨傔丄媶嬌偵偼俛宆丄俠宆偺僂僀儖僗娞墛偺崻愨偑娞娻偺梊杊偱偡丅尰嵼椉娞墛僂僀儖僗偼專寣偐傜偼傎傏姰慡偵彍奜偝傟丄俛宆娞墛偼曣帣姶愼梊杊偵傛傝怴婯偺敪徢偼嬌傔偰尷傜傟偰偄傑偡丅偙傟傜偵傛傝丄彨棃偼偐側傝尷掕偝傟偨姶愼徢偵側偭偰偄偔壜擻惈偑戝偒偄偲偄偊傑偡丅偟偐偟丄尰嵼擔杮崙撪偵偼俛宆丄俠宆暪偣偰栺俁侽侽枩恖偺僉儍儕傾偺懚嵼偑憐掕偝傟偰偄傑偡丅偙偺曽偨偪偺娞娻偺梊杊偑媫柋偺栿偱偡丅俠宆枬惈娞墛偺曽傪僀儞僞乕僼僃儘儞偱帯椕偡傞偲丄敪娻傪梷惂偱偒傞偙偲偑暘偐偭偰偄傑偡丅僀儞僞乕僼僃儘儞帯椕偱僂僀儖僗傪嬱彍偟娞婡擻偑埨掕偟偨曽偨偪偱偼敪娻儕僗僋傪尭彮偝偣傜傟傞偨傔丄側傞傋偔僀儞僞乕僼僃儘儞帯椕傪峴偭偰僂僀儖僗傪嬱彍偡傞偙偲偑朷傑傟偰偄傑偡丅俛宆枬惈娞墛丄俛宆娞峝曄偺曽偨偪傊偺僀儞僞乕僼僃儘儞帯椕偺敪娻梷惂偺岠壥偼巆擮側偑傜偦傟傎偳柧椖偱偼偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄僀儞僞乕僼僃儘儞帯椕傗堸傒栻偱俛宆娞墛僂僀儖僗偺憹怋傪幾杺偟偰娞婡擻傪埨掕偝偣傞偙偲偑丄傗偼傝敪娻偺梷惂偵桳岠偩偲怣偠傜傟偰偄傑偡丅 亂娔帇偡傞亃 丂娞娻傪梊杊偡傞偙偲偑壗傛傝戝愗偱偡偑丄晄岾偵偟偰枬惈娞墛偁傞偄偼娞峝曄偐傜夝曻偝傟側偄応崌偵偼偳偆偟偨傜椙偄偺偱偟傚偆偐丠偦傟偼懠偺娻偱傕摉慠尵傢傟偰偄傞偙偲偱偡偑丄側傞傋偔憗婜偵敪尒偡傞偙偲偵恠偒傑偡丅嬶懱揑偵偼丄倎丒乮嵦寣偱暘偐傞乯庮釃儅乕僇乕丄倐丒挻壒攇専嵏偺擇偮偺専嵏傪掕婜揑偵峴偭偰堎忢傪側傞傋偔憗偔擣幆偱偒傞傛偆偵偡傞偙偲偱偡丅庮釃儅乕僇乕偼枅寧丄挻壒攇専嵏偼俁乣俇儢寧枅偵孞傝曉偟偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅峏偵昁梫帪偵俠俿丄俵俼俬傪慻傒崌傢偣偰偄偒傑偡丅 亂恌抐亃 仜庮釃儅乕僇乕 丂庮釃儅乕僇乕偼俀庬椶偁傝傑偡丅俙俥俹乮傾儖僼傽僼僃僩僾儘僥僀儞乯偲俹俬倁俲俙嘦偱偡丅庮釃儅乕僇乕堿惈乮庮釃儅乕僇乕偑忋徃偟偰偄側偄乯偺娻傕栺俀妱偼偁傞偺偱堦奣偵偼尵偊傑偣傫偑丄楢懕偟偰應掕偡傞偙偲偱偦偺摦偒偐傜敾抐偡傞偙偲偑懡偄偱偡丅偮傑傝忋徃孹岦偵偁傞応崌偵偼梫拲堄丄偲偄偭偨敾抐傪偡傞偙偲偵側傝傑偡丅媡偵丄娻偲恌抐偑偮偄偰偐傜庮釃儅乕僇乕偑掅壓偟偨応崌偵偼帯椕偑忋庤偔偄偭偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅 仜夋憸恌抐 侾丏挻壒攇専嵏乮嵟嬤偼憿塭挻壒攇専嵏傕巤峴偟傑偡乯 俀丏倃慄俠俿丂 俁丏俵俼俬丂 係丏寣娗憿塭丂 俆丏俹俤俿-俠俿 丂夋憸恌抐偼偙偺傛偆偵奺庬偁傝傑偡偑丄壗偲尵偭偰傕拞怱偼挻壒攇専嵏偱偡丅傑偢丄崅婋尟孮偺曽乆偵偼傎傏俁儢寧偛偲偵挻壒攇専嵏傪庴偗偰偄偨偩偔傛偆偵偟偰偄傑偡丅偦偙偱娻傪媈偆傛偆側夦偟偄強尒偑摼傜傟偨応崌偵偼偦偺懠偺専嵏傪俀乣俁庬椶慻傒崌傢偣偰傛傝妋徹傪摼傞傛偆偵偟偰偄偒傑偡丅偳偺慻傒崌傢偣偱娻偑妋幚偵恌抐偱偒傞偲偺栺懇帠偼偁傝傑偣傫偑丄挻壒攇専嵏埲奜偵俠俿偁傞偄偼俵俼俬偺壗傟偐偱妋徹偑偁傞偙偲偑廳梫偱偡丅傑偨丄偁傞帪揰偱戝忎晇乮娻偱偼側偄乯偲偺敾抐偑側偝傟偨偲偟偰傕堷偒懕偒怲廳偵夋憸傪娷傔偰宱夁傪捛偭偰偄偐側偗傟偽側傝傑偣傫丅姵幰偝傫偵傛偭偰偼乪埲慜戝忎晇偲尵傢傟偨偺偵傑偩専嵏偑昁梫側偺偐乫偲尵傢傟傞曽偑偄傑偡偑丄枬惈偺娞幘姵偑偁傞曽偼巆擮側偑傜宲懕偟偰宱夁傪恌偰偄偔偙偲偑偲偰傕廳梫側偺偱偡丅 亂帯椕亃 丂娞娻偺帯椕偑懠偺憻婍偺娻偲戝偒偔堎側傞揰偼娞憻傪慡晹揈弌偱偒側偄偙偲偱偡丅偟偐傕丄娞娻偑偱偒傞忬懺偵側偭偨娞憻偼丄杮棃偺梊旛椡傪巊偄壥偨偟偨忬懺偱偁傞偙偲偑懡偔丄庤弍帺懱偑崲擄側偙偲傕彮側偔偁傝傑偣傫丅偦偙偱婛偵弎傋偨傛偆偵娔帇偵傛傝側傞傋偔娻偑彫偝偄撪偵敪尒偡傞搘椡傪偡傞偺偱偡丅娞娻偑俀侽噊埲壓偱扨敪偺応崌偼丄娞憻偺梊旛椡偑廫暘偵偁傞傛偆側傜偽丄傑偢庤弍傪姪傔偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅偦偺懠偺傕偺傪娷傔偰僈僀僪儔僀儞偑傑偲傔傜傟偰偄傑偡丅乮恾-1乯 亂傑偲傔亃 丂娞娻傪撍偒巭傔傞偨傔偵偼丄傑偢崅婋尟孮偐斲偐傪柧妋偵偡傞偙偲丅師偵側傞傋偔梊杊偡傞偙偲丅庮釃儅乕僇乕偲夋憸恌抐偲偱娔帇偟丄憗婜恌抐偺搘椡傪偡傞偙偲偵恠偒傑偡丅帯椕偼屄乆偺徢椺偛偲偵堎側傝傑偡偺偱庡帯堛偲傛偔憡択偟偰偄偒傑偟傚偆丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堛巘丂彫搰丂崃庽乯
|
|||
| 亂娞娻偵偼嶰埵堦懱偺帯椕懱惂偑戝愗亃 | |||
| 丂奜壢庤弍偑娞嵶朎娻偺嵟傕桳岠側帯椕庤抜偱偁傞偙偲偼娫堘偄偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄娻偑憗婜敪尒偝傟偰傕庤弍偱偒側偄偙偲偑偁傝傑偡丅媡偵娻偑恑峴偟偰偄偰傕愗彍偱偒傞偙偲偑偁傝傑偡丅偦偺嵎偼娞婡擻偱偡丅 娞嵶朎娻偵偼堓娻傗戝挵娻偲堎側傝丄亀娞婡擻亁偲偄偆亀娻偺恑峴搙亁埲奜偺梫慺偱帯椕庤抜傗帯椕岠壥偑戝偒偔嵍塃偝傟傞偲偄偆摿挜偑偁傝傑偡丅娞憻傪戝帠偵偟偰偔偩偝偄丅偦偺偨傔偵姵幰偝傫偼偐偐傝偮偗堛偲偺擇恖嶰媟偱丄娞憻偵傗偝偟偄惗妶廗姷傪恎偵偮偗丄宲懕揑側娞斴岇帯椕傪峴偆偙偲偑昁梫偱偡丅 娞嵶朎娻偺摿挜偺俀斣栚偼嵞敪棪偑崅偄偙偲偱偡丅庤弍偱娞嵶朎娻傪愗彍偟偨屻傕惗奤偺宱夁娤嶡偑昁梫偱偡丅搑拞偱傗傔偰偼偄偗傑偣傫丅偐偐傝偮偗堛偺巜帵傪庣偭偰丄掕婜揑偵専嵏傪庴偗偰壓偝偄丅 娞嵶朎娻偺摿挜偺俁斣栚偼帯椕朄偑懡嵤偱偁傞偙偲偱偡丅庤弍埲奜偱偼儔僕僆攇從庈弍偲娞摦柆嵡愷弍偑庡側帯椕朄偱偡丅拀攇戝妛晬懏昦堾偱偼儔僕僆攇從庈弍偼撪壢堛丄娞摦柆嵡愷弍偼曻幩慄壢堛偑扴摉偟偰偄傑偡丅偙傟傜偺帯椕庤抜傪嬱巊偟偰丄嵞敪屻傕娻偲偆傑偔偮偒偁偄壗擭傕尦婥偱夁偛偟偰偄傞曽偑偨偔偝傫偄傜偭偟傖偄傑偡丅 丂娞娻帯椕偵嵟傕戝愗側偺偼娞憻傪庣傠偆偲偡傞姵幰偝傫帺恎偺搘椡偲偦傟傪巟偊傞偐偐傝偮偗堛偱偡丅偦偙偵戝妛昦堾偑壛傢偭偨丄嶰埵堦懱偺帯椕懱惂偵傛傝丄傛傝傛偄娞娻帯椕偑壜擻偵側傞偲峫偊偰偄傑偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮拀攇戝妛丂椪彴堛妛宯島巘丂徚壔婍奜壢丂暉塱丂寜乯
|
|||