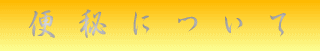
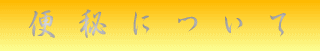
| 便秘は私達にとって身近な問題の一つですが、一般に便秘とは「3日以上排便がない状態、又は毎日排便があっても残便感がある状態」と認識されています。 | |
| 【便秘と薬】 | |
| ○便秘の種類 便秘にはさまざまなタイプがあります。ダイエット、環境の変化によるストレス、暴飲暴食、薬の副作用等によっても、一時的に便秘(一過性便秘)は起こります。又、腸管の病気によって引き起こされる便秘(器質性便秘)もあります。慢性的な便秘は一般に腸管機能の異常(機能性便秘)により起こりますが、これは更に弛緩性便秘、直腸性便秘、痙攣性便秘の3つのタイプに分けられます。弛緩性便秘とは、便を送り出す蠕動運動が弱くなる為に起こる便秘で、胃腸が下垂している人、腹筋力が低下している人に多く見られます。直腸性便秘とは直腸の神経が鈍くなり便が直腸に達しても便意が起きない場合を言います。排便を我慢しがちな人、浣腸を常用している人に多い症状です。痙攣性便秘は大腸の蠕動運動が強すぎて痙攣を起こし腸管内容物の通過障害で起こる便秘です。精神的ストレスが原因と考えられています。 ○便秘薬(下剤) 腸の内容物を増加させ柔らかくする薬物、あるいは腸の蠕動運動を促進させ排泄を容易にする薬物を便秘薬、又は下剤といいます。 塩類下剤・・腸管内に水分を移行させ腸内容物を柔らかくし増加させその刺激によって排泄を容易にします。酸化マグネシウム、硫酸マグネシウム等がこれに属します。多量の水と共に服用するとより効果的です。習慣性がすくないので長期使用が可能です。 膨張性下剤・・腸内で水分を吸収して膨張し、腸を刺激し蠕動運動を亢進させます。多量の水と共に服用します。習慣性がなく、作用が弱いので高齢者にも安心して使えます。カルメロース(バルコーゼ・他) はこのタイプの薬です。 浸潤性下剤・・硬くなった便内に水分を浸透しやすくし、便を柔らかくします。習慣性が少なく作用の弱い薬です。多量の水と共に服用すると効果的です。 尿が黄褐色から赤色になることがあります。薬にはカサンスラノール含有の配合剤(ビーマスS・他)があります。 大腸刺激性下剤・・腸粘膜を刺激し蠕動運動を亢進させます。センナ(アローゼン、センナ末)、センノシド(プルゼニド)、大黄等は作用が強いのですが習慣性があります。尿が黄褐色から赤色になることがあります。ピコスルファートNa(ラキソベロン他)は錠剤、液体があり使用性に富み習慣性も少なく幼少児、高齢者にも使えます。 その他に直腸内で炭酸ガスを発生させ蠕動運動を亢進させる炭酸水素Na配合坐薬(新レシカルボン・他)やグリセリン浣腸液も便秘薬として用いられています。 便秘は生活様式、食事療法、運動等で改善する場合もありますので、安易に薬に頼らず日常生活の見直しも大切かと思います。 (薬剤師 増田) |
|
| 【便秘時の食事は?】 | |
| 便秘を改善するには食事療法のみでは効果が薄く、要因と共に改善することが重要です。便秘の要因としては、不規則な食事・生活、運動不足、薬の副作用、下剤の乱用、食物繊維・水分・脂質の摂取不足、低栄養、ビタミン欠乏、神経障害、職業性(便意があっても排便に行きにくい職業)、便意を抑制する習慣、緊張・悲しみなどの精神的因子など様々です。これらの要因による便秘(上の文章を参照)は、その特徴の違いで食事を変えるポイントも違います。 弛緩性便秘では食物繊維と水分を多く摂取して便量を増やすこと(高齢者では食事の全体量が少なくて便秘の原因になっていることもあります)、冷水・炭酸飲料で腸の反射を促すこと(牛乳も有効です)、脂質を適度に摂って脂肪酸で大腸を刺激すること、香辛料や酸味類(果実に含まれる有機酸も含みます)を摂って腸内粘膜を刺激することがポイントです。運動は適度に行ない、決まった時間に便意がなくても排便に行く習慣をつけます。 痙攣性便秘では腸の痙攣抑制のため、弛緩性便秘とは逆で刺激の少ない食事にします。食物繊維は抑制まではしませんが、水溶性食物繊維(芋類、海藻類、果物類)を中心に通常量20〜25g/日とし、刺激性食品(酸味、香辛料、アルコール、カフェイン、炭酸飲料、エキス分)を避ける事、物理的刺激(固い食品、過食など)を避けること、脂質の摂取は控えること、過熱・過冷食品の摂取は控えること、食事量は確保することがポイントとなります。また運動は控えるようにします。腹部マッサージは無効です。 しかし、何よりも便秘はその要因となる生活の改善が第一です。人間の生活の基本とも言える規則正しい日常生活、日に3回の食事と排便のリズム、精神的ストレスの軽減が大切です。慢性便秘が長期間続いてもそれが原因で生命が危険になることは稀ですし、便秘で通院することもありませんが、個人の生活パターンが多様化している昨今、だからこそ自身で排便を管理できる方法を知る必要があるのではないでしょうか。 (管理栄養士 高野) |
|