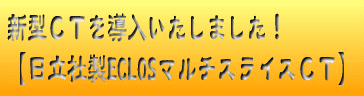
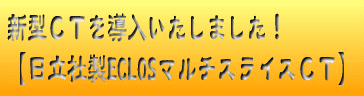
| 新型のCTを使用して検査を行った場合、患者さんにとってどんなメリットがあるのか、今までのCTと何が違うのか相川礼子医師にまとめてもらいました。 | ||
| CTスキャンという検査の器械があることをご存知の方は多いと思います。また、実際に検査を受けられた方もいらっしゃると思います。この器械はちょうど私が医者になったころ登場しました。 この時には、検査するたびに新しい発見があり、しかもあまりテキストも無く暗中模索の状態で毎日悪戦苦闘した思い出があります。それから約30年経過したのですが、ここ最近のCTの進化は素晴らしいものです。原理そのものが変わり、その活用方法、画像の解析、表現などどれをとっても隔世の感があります。そのような中、当院でも思い切って新しいCTを導入しました。何故かと申しますと、この装置はとにかく今までのCTと異なり、検査時間の短縮だけでなく情報を得たい臓器のみ描出したり、血管や骨だけを見る事も可能です。あるいは3D化と言って平面だけでなく立体的に臓器を見る事で全体像が把握しやすくなります。また、これは非常に驚くべき機能ですが、仮想内視鏡と言いまして、胃内視鏡、大腸鏡、気管支鏡と同じような画像が得られる事です。バリウムを使用しなくても同様の検査ができるようになりました。ですから、胃ないし大腸のバリウム検査のあと、バリウムを排出するのに一苦労しましたがその苦痛から解放されます。ただ空気が入っていませんときれいにわかりませんから、胃の場合には発泡剤を飲んで頂きます。また大腸の場合には下剤は必要ですし、また大腸への空気の注入も必要ではありますが、その後はCTの台上で10秒程度の息止めで検査は終了です。ですから、体動が困難な方でも検査可能となりましたし、検査後の処理もバリウムを使用しない事で格段に楽になりました。などなどいろいろな機能が付加されています。 今回導入したのは、マルチスライスCT ECLOS(16列)地元の日立メディコ社製です。茨城県では2台目という事で、我々も大いに張り切っています。 それでは一部検査の画像を示します。 |
||
| 1.肺の画像(1-1) | ||
肺に関してはかなり小さな腫瘤も検出できますが、逆に小さすぎて腫瘍か否か判断がつきかねる事もあり、その時には定期的な検査をして経過を追う事が必要です。またある程度の大きさのものがあれば、3次元画像を構成することで、リンパ節の腫大、周囲の動脈や静脈の走行、あるいは、仮想気管支鏡により気管支の内部の状態をある程度把握出来ます。
|
||
| 2.肝臓など腹部臓器の画像(2-1) | ||
肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓など腹部臓器の病変描出にも有用です。例えば肝臓では腫瘍そのものの検出だけでなく、肝臓の血管の支配領域がわかりますので、腫瘍の立体的把握が可能となります。膵臓などに関しても同様で、より小さい腫瘍を発見したいと思っています。
|
||
| 3.血管・骨(3-1,3-2) | ||
今までは血管が他の臓器と重なり詳細を見る事は困難でしたが、これからは血管あるいは骨だけを描出する事が画像処理する事で可能となりましたので、血管の動脈硬化(壁の石灰化など)や動脈瘤の検出に威力を発揮すると思います。また下肢の動脈の血流や狭窄の状態もわかりますので下肢の痺れや歩行時の痛みのある方は検査をお勧めします。
|
||
| 4.仮想内視鏡(4-1〜4-3) | ||
| 前述しましたが、バリウムを使用せずに胃、大腸の内腔が(粘膜が)ある程度わかるようになりました。例えば便の潜血反応が陽性で血便を指摘された時、まずは注腸検査と言って大腸にバリウムを注入し写真を10枚強撮影する検査があります。検査も体位交換して大変ですが、検査後バリウムの排泄が一苦労です。でもCTでは検査そのものの時間は十数秒です。4-1〜4-3は、大腸に2mmのポリープが2個あった画像です。バリウムを使わずCT検査だけで診断がつきました。 このように今度のCTでは、かなり色々な事がわかりますが、私も3名の放射線技師も初めての器械です。ですから1件1件の検査を大切に、勉強しながら進めて参ります。 ただ放射線被爆の問題はあります。低線量の器械と言っても被爆はします。その疾患が本当にCT検査を必要としているか判断して最小限の被爆量で検査ができるように常に考えていきたいと思っております。30年前のCTにおける初心に戻ってスタッフと頑張って参りたいと思います。
|
||
| (医師 相川礼子) | ||
| 【16例マルチスライスCTの特徴】 | ||
| 【撮影時間が短縮され、検査がより楽に】 息を止める時間が短く、より楽になりました。以前は2列の検出器でX線管球1回転で2スライスの画像を収集するのに対して、1回転で16スライスの画像を収集できます。 【2.高画質の画像で、より正確な診断が可能に】 薄いスライス画像の撮影が可能で、より高画質な画像や三次元画像の作成が可能になりました。鮮明な三次元の立体画像、任意の断面の良好な画像が得られます。 【3.X線の被曝をより少なく】 従来のCT装置よりもX線の被曝の量を少なくする機能を持っています。体厚や撮影部位に応じてX線量を自動的に制御します。特に被曝を注意を必要とする小児でも、決め細やかな対応ができます。 |
||
| (放射線課) | ||