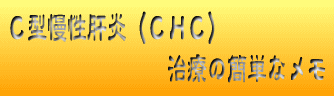
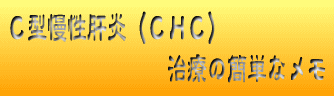
| 丂尰嵼丄帯椕傪偡偡傔傞懁偲偟偰丄CHC偲偟偰捠堾偟偰偄傞姵幰偝傫傊偺愢柧偑抐曅揑偵側傜偞傞傪摼側偄偙偲偵偄偮傕擸傫偱偄傑偡丅偙傟傑偱傕丄摉堾偱偺帯椕惉愌偼愜偵怗傟丄乽傂傠偽乿偱徯夘偟偰偒傑偟偨偑丄崱夞偼摉堾偺忣曬偺堦偮偲偟偰丄娙扨側丄偟偐偟惓妋側抦幆傪姵幰偝傫偵傕偭偰傕傜偆偨傔偵丄儊儌傪傑偲傔偰傒傑偟偨丅 | |||
| 亂僂僀儖僗娞墛亃 | |||
| 丂娞墛傪婲偙偡娞墛僂僀儖僗偵偼A,B,C,D,E偺俆庬椶偑偁傝傑偡丅A宆偲E宆娞墛偼媫惈娞墛偩偗偱丄枬惈壔偡傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅 丂B宆偼怴惗帣偐傜梒帣偺帪偵姶愼偡傞偲侾侽戙側偐偽偐傜丄枬惈娞墛偲側傝傑偡丅惉恖偱媫惈娞墛偵滊姵偟偰傕枬惈壔偡傞偙偲偼椺奜偱偡丅D宆偼B宆娞墛偵敽偭偰姶愼偡傞晄姰慡僂僀儖僗偱丄廳徢壔偟傑偡偑丄擔杮偱偼嬌傔偰婬偱偡丅C宆偼桝寣丄寣塼惢嵻丄拲幩婍嬶偺巊偄夞偟丄妎惲嵻偺夞偟懪偪丄徚撆偺晄姰慡側巋惵丄僺傾僗丄鐸帯椕偱寣塼傪夘偟偰姶愼偟栺俉妱偑枬惈壔偟傑偡丅惈峴堊偱傕帪偵姶愼偡傞偙偲偑抦傜傟偰偄傑偡丅 佱C宆娞墛僂僀儖僗乮HCV乯偺堚揱巕宆佲 丂俫俠倁偼堚揱巕偲偟偰妀巁偺RNA傪帩偮僂僀儖僗偱偡丅堚揱巕偺夝愅偑偡偡傒丄僂僀儖僗偺堚揱巕宆偼庡偲偟偰嘥宆丄嘦宆丄嘨宆丄嘩宆偑偁傝抧堟偵傛傝丄姶愼偟偰偄傞堚揱巕宆偵摿挜偑偁傝傑偡丅擔杮偱偼嘥宆偑俉侽亾傪愯傔偰偄傑偡丅偟偐偟丄帪戙偲偲傕偵堛椕峴堊偐傜妎惲嵻丄巋惵側偳偺斾棪偑崅偔側傝丄庒偄恖偱偼嘦宆偑憹壛偟偰偄傑偡丅擔杮偱偼偙偺擇偮偺宆偑戝晹暘偺偨傔丄堚揱巕夝愅傪偣偢偵寣惔宆偲偟偰侾宆偲俀宆偵暘椶偟偰幚梡忋偼巟忈偑偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄寣惔宆偼擇偮偺宆偺姶愼偑偁傞偲偒丄峈懱壙偑掅偄偲偒偵偼敾掕偑偱偒側偄偙偲傕偁傝傑偡丅 佱僂僀儖僗検佲 丂姶愼偟偰偄傞僂僀儖僗検傪應傞偨傔丄俼俶俙検傪應掕偟傑偡丅應掕偺惛搙傪偁偘傞偨傔丄婔偮偐偺應掕朄偑採埬偝傟偰偒傑偟偨丅 丂奺應掕朄偺應掕斖埻傪帵偟傑偡乮恾侾)丅尰嵼丄儕傾儖僞僀儉俹俠俼朄偑偛偔旝検偺僂僀儖僗傑偱専弌偱偒傞曽朄偲偟偰掕拝偟偰偒傑偟偨丅偄偢傟傕崙嵺扨埵乮IU)偱昞帵偝傟丄儕傾儖僞僀儉朄偱偺悢帤偼log傪偮偗偰丄椺偊偽6.40gIU/dl偲昞帵丄悢帤偼懳悢偺檖悢傪昞偟傑偡丅偟偨偑偭偰俆偐傜俀偩偗尭偭偰俁偵側傟偽僂僀儖僗偼侾侽侽暘偺侾偵尭彮偟偨偙偲偵側傝傑偡丅應掕尷奅埲壓偱傕僂僀儖僗偑徚柵偟偨偲敾抐偡傞偺偼擄偟偄偙偲偱丄僴僀儗儞僕朄偱偼丄掕検偼偱偒側偄偑丄掕検尷奅埲壓偱僂僀儖僗偑懚嵼偡傞偐偳偆偐傪傾儞僾儕僐傾掕惈朄偱敾掕偟傑偟偨丅偦傟偱堿惈偱偁偭偰傕丄尷奅偑偁傝丄帯椕廔椆屻偵嵞敪偡傞偙偲偑偁傝傑偡丅儕傾儖僞僀儉朄偱偼丄掕検偱偒側偄偑堿惈偲偼偄偊側偄応崌(<1.2logIU/ml+)偲昞帵偟傑偡丅偙傟埲壓偱僂僀儖僗偑徚幐偟偨偲偟傑偡丅偟偐偟丄偙傟偱傕嵞敪偡傞帠偑偁傝丄娞嵶朎傗懠偺嵶朎撪傗慻怐撪偵僂僀儖僗偑偄偰丄攔彍偝傟偰偄側偐偭偨堊偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅
|
|||
| 亂僀儞僞乕僼僃儘儞帯椕偵娭傢傞帠崁亃 | |||
| 佱僀儞僞乕僼僃儘儞(IFN)佲 丂僸僩偑僂僀儖僗偵姶愼偡傞偲丄懱偺拞偱儕儞僷媴傗慄堐夎嵶朎側偳丄偄傠偄傠側嵶朎偱IFN偑嶌傜傟丄傑偨丄IFN偺嶻惗偵娭傢傞嵶朎偵傛偭偰條乆側I俬俥俶偑偁傝傑偡丅俬俥俶偺徻嵶側嶌梡婡彉偼偄傑偱傕夝柧偝傟側偄晹暘偑偁傝傑偡偑丄僂僀儖僗偵姶愼偟偨嵶朎偵偲傝偙傑傟丄僂僀儖僗偺憹怋偵昁梫側僂僀儖僗偺僞儞僷僋傪嶌傟側偄傛偆偵偟偰憹怋傪梷偊丄傑偨丄柶塽嵶朎傪巋寖偟偰姶愼偟偨嵶朎傪攋夡偡傞偙偲偵傛傝僂僀儖僗傪攔彍偟傑偡丅 佱堛栻昳偲偟偰偺俬俥俶佲 丂尰嵼丄偦偺側偐偱俬俥俶兛丄俬俥俶兝偑堚揱巕憖嶌偵傛偭偰嵶嬠傗嵶朎攟梴偐傜丄戝検偵惗嶻偝傟丄僂僀儖僗娞墛帯椕栻偲偟偰梡偄傜傟偰偄傑偡丅 丂侾俋俋侽擭戙弶傔偵巊傢傟偨俬俥俶倛偼婜懸偵斀偟偰丄僂僀儖僗傪攔彍偟丄娞墛傪廔鄰偱偒偨偺偼俆亾慜屻偱偟偨丅偦偙偱丄帯椕惉愌傪偁偘傞偨傔丄俬俥俶偑挿帪娫懱撪偵偲偳傑傞傛偆偵偟偰丄崅暘巕壔崌暔乮億儕儅乕乯偱偁傞億儕僄僠儗儞僌儕僐乕儖乮俹俤俧乯傪俬俥俶偵寢崌偝偣傞偙偲偵偟傑偟偨乮儁僌壔乯乮彜昳柤丗儁僌僀儞僩儘儞丄儁僈僔僗丄椉幰偺俹俤俧偺暘巕検偑儁僌僀儞僩儘儞侾俀俲俢丄儁僈僔僗係侽俲俢偲堎側傝丄岠壥偺敪尰偲暃嶌梡偺弌尰偵偼峫椂偡傋偒帠崁偱偁傝傑偡乯丅 佱儁僌壔偺儊儕僢僩佲 丂崅暘巕偵側偭偨俹俤俧俬俥俶偼拲幩晹埵偐傜備偭偔傝媧廂偝傟偰寣拞偵堏峴偟偰備偒丄寣塼撪偱俬俥俶偑峺慺偱暘夝偝傟傞懍搙偼偍偦偔側傝丄彊乆偵寣拞擹搙偑崅傑傝丄栺俈擔娫寣拞偵偁傝丄拲幩偼廡堦夞偱椙偄偙偲偵側傝傑偡丅偦傟偱丄姵幰偝傫偼偛帺暘偺搒崌偵崌傢偣偰丄寛傑偭偨梛擔偵拲幩傪庴偗傞偙偲偵側傝傑偡丅帯椕奐巒偟偰偐傜俉廡娫傎偳偱丄寣塼撪偺擹搙偑堦掕偵曐偨傟傞傛偆偵側傝傑偡丅 佱儕僶價儕儞乮俼俛倁乯惢嵻偲偺暪梡乮憤昳柤丗儗儀僩乕儖丄僐儁僈僗乯佲 丂埲慜偐傜峈僂僀儖僗嶌梡偑偁傞偙偲偑抦傜傟偰偄偨俼俛倁偼扨撈偱偼娞墛僂僀儖僗偵岠壥偑彮側偐偭偨偺偱偡偑丄俬俥俶偲堦弿偵巊偆偲俬俥俶偺岠壥偑岦忋偡傞偙偲偑抦傜傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅 佱俼俛倁偺嶌梡婡彉佲 丂俼俛倁偼撪暈栻偱丄彫挵忋晹偱媧廂偝傟丄怘帠偺偁偲偺曽偑傛偔媧廂偝傟傞偙偲偑傢偐偭偰偄傑偡丅媧廂偝傟偨俼俛倁偼娞嵶朎偵庢傝崬傑傟丄儕儞巁壔偲偄偆夁掱偱俼俛倁嶰儕儞巁偲側傝丄僂僀儖僗偑偙傟傪庢傝崬傓偲僂僀儖僗偺妀巁乮俼俶俙乯偺崌惉偑偱偒側偔側傝丄僂僀儖僗偺憹怋傪梷惂偟傑偡丅俼俛倁偼娞嵶朎偩偗偱側偔丄愒寣媴傗嬝嵶朎偵傕庢傝崬傑傟丄側偑偔偲偳傑偭偰丄暃嶌梡偲偟偰昻寣傪偍偙偟偰偒傑偡丅 佱俬俥俶帯椕偺幚嵺佲 丂偙傟傑偱丄俬俥俶偺帯椕婜娫丄搳梌検丄偝傜偵偼俼俛倁偲偺暪梡丄嵞帯椕偺壜斲側偳偱懡偔偺恻梋嬋愜偑偁傝傑偟偨丅尰嵼偼崙嵺揑偵傕俹俤俧俬俥俶亄俼俛倁偺係俉廡娫偐傜俈俀廡娫搳梌偑昗弨偲側偭偰偄傑偡丅帯椕偵傛傞僂僀儖僗乮倁乯偺斀墳帪婜偵傛傝師偺傛偆側梡岅偑梡偄傜傟偰偄傑偡丅 俼倁俼丗係廡埲撪偵僂僀儖僗偑徚幐偡傞偙偲乮憗婜斀墳乯 俴倁俼丗侾俀廡埲忋偐偐偭偰偐傜僂僀儖僗偑徚幐偡傞偙偲乮抶墑斀墳乯 俤倁俼丗係俉廡偺帯椕廔椆帪揰偱僂僀儖僗偑徚幐偟偰偄傞偙偲 俽倁俼丗係俉廡偺帯椕廔椆屻丄俇儢寧娫僂僀儖僗偺堿惈壔偑懕偔偙偲丄俠宆娞墛偼廔鄰偟偨偲傒側偟傑偡丅 俤俛俼丗帯椕廔椆帪俼俶俙梲惈偱偁傞偑丄俙俴俿乮俧俹俿乯丄俙俽俿乮俧俷俿乯偑惓忢偱偁傞偙偲乮恀偺惓忢抣偼侾侽乣俀侽戜偱偡乯 俽俛俼丗帯椕廔椆屻俼俶俙偼梲惈偺傑傑偩偑俇儢寧埲忋俙俴俿丄俙俽俿偼惓忢抣偑懕偄偰偄傞偙偲 俶俼丗慡偔帯椕偵斀墳偟側偄 嵞擱丗俤倁俼屻俼俶俙偑弌尰偟丄娞婡擻傕堎忢偵側傞 佱俹俤俧俬俥俶亄俼俛倁帯椕偺惉愌佲 丂昗弨揑側帯椕偱丄帯桙偲傒側偝傟傞俽倁俼偺棪偼俫俠倁偺侾宆偺崅僂僀儖僗検偺僌儖乕僾偱俆俀亾丄偦傟埲奜偺僌儖乕僾偱偼俉係亾偲側偭偰偄傑偡乮暯惉俀侽擭搙岤惗楯摥徣戝嶃戝妛偺帒椏乯丅帯椕惉愌偼摑寁傪庢偭偨廤抍偵榁恖偑懡偄偐丄抝彈斾偼偳偆偐偱堎側傝傑偡丅 佱帯椕偵娭學偡傞帠崁佲 惈偲擭楊 俇俆嵨埲忋偺彈惈偺俽倁俼偼俁俁亾偱丄俇俆嵨枹枮偺彈惈偺俆俇亾偵斾傋摑寁妛揑偵桳堄偵掅偄惉愌偱偡丅 俇俆嵨埲忋偺抝惈偺俽倁俼偼俁俋亾丄俇俆嵨枹枮偼係俋亾 佱俼俶俙堿惈壔帪婜偲俽倁俼棪佲 丂侾俀廡埲撪偵堿惈壔丗俽倁俼偼俇俈亾 俴倁俼孮丗俽倁俼俀俉亾 佱墑挿帯椕乮俈俀廡乯偺惉愌佲 丂俴倁俼偺孮偱偼俈俀廡傑偱帯椕傪墑挿偟偰俽倁俼俆俈亾偲側傝丄係俉廡偺俀俉亾偵懳偟偰桳堄偵岦忋偟傑偟偨丅偄傑偺偲偙傠帯椕奐巒偟偰俁俇廡埲忋係俉廡傑偱偵俼俶俙偑徚幐偟偰傕丄俽倁俼偼偊傜傟偰偄傑偣傫丅偟偐偟丄嵟嬤偼俁俉廡偱俼俶俙偑堿惈壔偟偨応崌偵偱傕俽倁俼偵側偭偨偲偄偆帠椺傕偁傝丄俈俀廡偺僗働僕儏乕儖偼懕偗偰偄偔傋偒偱偟傚偆丅偙偺応崌丄帯椕係乣俉廡偱俼俶俙検偑帯椕奐巒帪偺侾侽侽暘偺侾埲壓偵尭彮偟偰偄側偗傟偽側傝傑偣傫丅 佱嵞擱偟偨応崌偺嵞帯椕佲 弶夞帯椕偲嵞帯椕 丂摉堾偺惉愌偱偼丄俤倁俼偱偺嵞帯椕偺俽倁俼偼俈侾亾偱偟偨丅乮傂傠偽146崋乯 嵞乆帯椕 丂摉堾偱偼侾侽擭娫丄俆夞偺帯椕偵傛傝俽倁俼偑摼傜傟偨働乕僗傕偁傝傑偡丅 佱俬俥俶帯椕偑廔椆偟偨屻佲 俬俥俶帯椕侾俆擭搙偺娞僈儞敪惗棪 俽倁俼孮丗俈丏係亾 旕俽倁俼孮丗俁侾丏俆亾 偲偺廤寁偑偁傝傑偡丅娞墛偑廔鄰偟偰傕俆擭娫偼擭俀夞丄偦偺屻傕擭侾夞偺挻壒攇専嵏丄俠俿専嵏偑昁梫偱偡丅 娞幘姵偵娭楢偟偰偺巰朣棪 俽倁俼孮丗侾丏俉亾 旕俽倁俼孮丗侾俆丏侾亾 |
|||
| 亂暃嶌梡偵偮偄偰亃 | |||
| 丂埲壓偼俹俤俧俬俥俶偺暃嶌梡傪儊乕僇乕偺弌偟偰偄傞愢柧彂偺昞侾偱傒偰傒傑偡丅暘巕検偑戝偒偔側偭偨偨傔偵丄俬俥俶偺暘晍偼庡偵娞憻偲寣塼偵尷傜傟丄廬棃偺俬俥俶惢嵻傛傝傕擼嵶朎傊偺塭嬁偼偡偔側偔丄惛恄徢忬偺弌尰偼彮側偔側傝傑偟偨丅傑偨丄敪擬丄姦婥丄娭愡捝側偳偺暃嶌梡徢忬偑壐傗偐偵側傝傑偟偨丅尵偄偐偊傟偽丄儁僌壔偝傟偨俬俥俶偼戝偒側俹俤俧偺暘巕偵曪傒崬傑傟傞傛偆偵側偭偰偄偰丄俬俥俶偼備偭偔傝偲寣塼偺拞偵曻弌偝傟傑偡丅偙偺偨傔丄廬棃偺俬俥俶偱宱尡偝傟偨暃嶌梡偼偢偭偲壐傗偐偵側偭偰偄傑偡偺偱丄摉堾偱偼暃嶌梡傪娤嶡偡傞栚揑偱帯椕奐巒偺帪偵堦攽擇擔偺擖堾偲偟偰偄傑偡丅 丂偐偮偰偼丄帯椕奐巒偲偲傕偵姵幰偝傫偑擸傑偝傟傞偺偼僀儞僼儖僄儞僓偵偐偐偭偨偲偒偺傛偆側崅擬丄埆姦愴溕偱偟偨偑丄俹俤俧俬俥俶偱偼俁俉搙傪墇偊傞敪擬偼偁傑傝宱尡偝傟傑偣傫丅撪暈偺夝擬嵻偱廫暘偵懳墳偱偒傑偡丅 丂俹俤俧俬俥俶亄俼俛倁帯椕拞丄婥晅偐側偄偲廳戝側寢壥傪彽偔偙偲偑偁傝丄恄宱傪巊偆偺偼枙徚寣塼偺曄壔偱偡丅敀寣媴偺尭彮乮岲拞媴悢俆侽侽埲壓乯丄昻寣乮僿儌僌儘價儞俉丏俆埲壓乯丄寣彫斅悢俆枩埲壓偱偼巊梡拞巭傪峫偊傞偨傔丄尨懃偲偟偰枅廡丄寣塼専嵏傪偟偰埨慡傪妋擣偟傑偡丅傑偨丄帯椕拞偵僂僀儖僗偼徚幐偟偨偺偵俙俴俿丄俙俽俿偺抣偑惓忢壔偟側偄偲偒偑偁傝丄懡偔偼俬俥俶偺暃嶌梡偺偨傔偱丄帯椕偑廔椆偡傞偲惓忢抣偵側傝傑偡丅 佱廳戝側暃嶌梡佲 丂婬偱偼偁傝傑偡偑捈偪偵帯椕傪拞巭偟側偗傟偽側傜側偄偺偼娫幙惈攛墛偱偡丅奝丄懅愗傟偑偁傟偽堛巘偵偡偖揱偊偰偔偩偝偄丅娫幙惈攛墛偑婲偒偰偄偨傜偡偖偵帯椕偼拞巭偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅傕偲傕偲丄歜懅傗攛慄堐徢偲偝傟偰偄傞曽偺応崌偼帯椕傪偍偡偡傔偟傑偣傫丅傑偨丄帯椕堄梸偺掅壓丄梷烼丄帺嶦傪峫偊傞側偳偺惛恄徢忬偑偁傞偲偒偼偆偮昦偺壜擻惈偑偁傝丄帯椕偼拞巭偟丄惛恄壢偺恌嶡傪庴偗傑偡丅偆偮昦偱偼側偔偲傕偐側傝偺姵幰偝傫偑慡恎寫懹姶丄晄柊丄晄埨丄怘梸晄怳側偳朤栚偵偼傢偐傝偵偔偄帺妎徢忬偑偁傝傑偡丅傑偨懡偔偺僸僩偑懱廳尭彮傪宱尡偟傑偡丅偙偺傛偆側帪偵栻嵻傪尭検偡傞偙偲傕偁傝傑偡丅暃嶌梡偱偁傞偙偲傪傛偔愢柧偟傑偡丅 丂偦偺懠丄愱栧堛偵恌嶡傪庴偗側偗傟偽側傜側偄暃嶌梡偲偟偰丄峛忬態婡擻堎忢乮槾恑偁傞偄偼掅壓乯丄娽掙弌寣乮僀儞僞乕僼僃儘儞栐枌徢乯丄婃屌側旂怾偲偟偰丄姡釢側偳偑偁傝傑偡丅傑偨丄摐擜昦偺埆壔偑宱尡偝傟傑偡偺偱丄偙傟傜偺帯椕傪揙掙偟傑偡丅 丂暃嶌梡偼帯椕偺拞抐偵偮側偑傝丄寢壥偲偟偰娞墛姰帯偺婡夛傪幐偆偙偲偵側傝傑偡偺偱丄壗側傝偲庡帯堛偵偛憡択偔偩偝偄丅姵幰偝傫偑帯椕傪拞抐偟側偄傛偆偵偡傞偵偼偁傞掱搙偺宱尡偺偁傞堛巘偺傕偲偱帯椕傪奐巒偟丄埨掕偟偨忬懺偱嬤強偺偐偐傝偮偗偺堛巘偵帯椕傪偍婅偄偟偰偄傑偡丅帯椕傪拞抐偡傞姵幰偝傫傪彮側偔偡傞偙偲偼堛巘偺偮偲傔偱偡丅丂 丂帯椕偵偼傓偐側偄忬懺偼擠怭丄廳搙偺怱憻昦丄恡憻昦丄偆偮昦丄攛婥庮側偳偑偁傝傑偡丅婥娗巟歜懅偺姵幰偝傫偵偮偄偰偼傛偔憡択偄偨偟傑偡丅 丂暃嶌梡偵傛傞栻嵻偺尭検傗堦帪拞巭偱丄栻嵻偺寣拞擹搙偑掅壓偟偨傝丄僛儘偵側偭偨傝偟傑偡偺偱丄偦傟側傝偵帯椕岠壥偵塭嬁偑偁傝傑偡丅懡偔偺応崌丄帯椕婜娫偺墑挿偑昁梫偵側傝傑偡丅
|
|||
| 摉堾偺帯椕惉愌 | |||
| 丂俀侽侽係擭侾俀寧偐傜俀侽侽俉擭侾俀寧枛傑偱偵摉堾偱昗弨帯椕乮儁僌僀儞僩儘儞亄儗儀僩乕儖乯傪奐巒偟偨徢椺偼俀侽俀椺乮抝侾侾俀丒彈俋侽乯偱丄暯嬒擭楊偼抝俆俇丏俁嵥丄彈俇侾丏侾嵥偱偡丅弶夞帯椕偼俋侽椺乮係俆亾乯丄嵞帯椕偼侾侾俀椺乮俆俆亾乯偱偟偨丅 丂惉愌偼慜弎偟偨岤惗楯摥徣偺僨乕僞偲摨偠孹岦偵側偭偰偄傑偡丅恾俀偼俀侽俀椺偺帯椕偺棳傟偱偡丅帯椕傪廔椆偟偨俉侽椺偵偮偄偰暘愅偟傑偡偲丄慡懱偺俽倁俼棪偼係俋亾偱抝惈偲彈惈偺俽倁俼棪偵偼嵎偑傒傜傟傑偣傫偱偟偨偑丄俇侽嵥偱嬫暘偟偰斾妑偟傑偡偲丄俇侽嵥埲忋偺彈惈偺俽倁俼棪偼掅偄孹岦偵偁傝傑偡乮昞俀乯丅傑偨丄僂僀儖僗偺寣惔宆偵偮偄偰偼丄埲慜偐傜尵傢傟偰偄傞傛偆偵侾宆偺俽倁俼棪偼係俆亾偱俀宆偺俇俀亾偵斾傋偰掅偄孹岦偵偁傝傑偡丅俬俥俶偺婛墲偺桳柍偵傛傞俽倁俼棪偼婛墲桳傝偑係俈亾丄柍偟偑俆俀亾偱傎偲傫偳嵎偼偁傝傑偣傫偑丄婛墲楌偺偁傞曽偱丄慜夞偺俬俥俶帯椕偱俫俠倁俼俶俙偑偄偭偨傫偼徚幐偟嵞擱偟偨曽偲丄俼俶俙偺徚幐傪尒側偐偭偨柍岠偺曽偱偼桳堄偵柍岠偺曽偺俽倁俼棪偑掅偔側偭偰偄傑偡乮昞俁乯丅傑偨丄帯椕傪奐巒偟偰偐傜俫俠倁俼俶俙偑徚幐偡傞傑偱偵梫偟偨婜娫偵傛偭傝俽倁俼棪偼桳堄偵堘偄偑桳傝丄係廡埲撪偺俽倁俼棪偼侾侽侽亾偱偄偨乮昞係乯丅偙傟傜偺寢壥傛傝丄俇侽嵨埲忋偺彈惈丄僂僀儖僗寣惔宆偑侾宆丄慜夞偺俬俥俶搳梌婛墲偑柍岠丄俼俶俙偑侾俀廡傑偱偵徚幐偟側偄曽偼岠偒偵偔偄孹岦偵偁傝傑偡丅岠壥側偟偲敾掕偝傟偨俶俼俁係椺偲岠壥偑側偔搳梌傪拞巭偟偨俀係椺偺偆偪丄懠偺俬俥俶傗俬俥俶帺屓拲幩偺帯椕傪奐巒偟偨曽偑俁侽椺丄郻寣傗嫮儈僲帯椕傪奐巒偟偨曽偑俈椺偲側偭偰偄傑偡丅 丂傑偨丄俀侽俀椺偺侾俀寧尰嵼偺帯椕忬嫷乮昞俆乯偵偍偄偰丄婛偵拞巭丒拞抐椺偑係俉椺乮俀俁丏俉亾乯偵側偭偰偄傑偡丅棟桼偼懠幘姵敪徢傗夦変偑俁椺丄岠壥偑側偄偺偱拞巭偲偟偨偺偑俀係椺丄棃堾偣偢偑係椺丄偦偟偰暃嶌梡偑侾俈椺偲側偭偰偄傑偡丅暃嶌梡偱偼丄偆偮丒偆偮孹岦丄敪怾丄憕醳姶偑懡偔傒傜傟傑偟偨乮昞俇乯丅岲拞媴傗寣彫斅偺尭彮丄僿儌僌儘價儞偺尭彮偼偐側傝偺姵幰偝傫偱尒傜傟傞暃嶌梡偱偡偑丄拞巭棟桼偵擖偭偰偄側偄偺偼丄偙傑傔側尭検丒憹検側偳偱偳偆偵偐偟偺偄偩傕偺偲巚傢傟傑偡丅僈儞梊杊偺偨傔偺彮検挿婜帯椕傕悇彠偝傟偰偄傑偡丅拞巭丒拞抐椺傪彮側偔偡傞偙偲傕戝偒側壽戣偲巚傢傟傑偡丅
|
|||
| 乮堛巘丂憡愳払栫乯 | |||