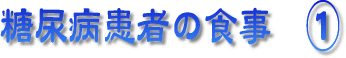
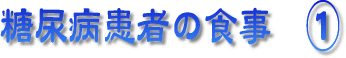
| 糖尿病は膵臓から分泌されるインスリンの作用不足により起こる慢性の高血糖を主徴とする疾患で、飽食時代の現在のおいて患者数は右肩上がりに増加しています。糖尿病の治療には食事、運動、薬物の3つの療法があります。食事療法はどのような治療をしている人でも必ず行わなければならない治療法です。 糖尿病の食事は第一に適正な体重を保ちながら、日常生活に必要な分だけ食事をして余分に食べないことです。第二に体に必要な栄養素(炭水化物、タンパク質、ミネラル、食物繊維)を過不足なく食事で摂るということです。食品についていえば、食べていけないものはほとんどありませんし、糖尿病に特によい食品もありません。毎食の食事に意識を向け、いろいろな食品を食べることで、バランスは自然ととれて行きます。 簡単にいろいろな食品を食べると言っても、食事が偏っていることに気がつかない人もいます。ご自分の日常良く食べる食品を振り返ってみてください。「糖尿病患者のための食品交換表」という本では食品を6つのグループに分けて、適正量を写真で分かりやすく掲載しています。①穀物、いも、とうもろこし、れんこんなど炭水化物の多い野菜、豆類(大豆を除く)②果物③魚介、肉、卵、大豆・大豆製品、チーズ④牛乳、乳製品(チーズを除く)⑤油脂、マヨネーズなど油脂性食品、ベーコン・落花生など脂質高含有食品⑥野菜、海藻、きのこ、こんにゃくという様に分類しています。①②は炭水化物を多く含み、③④はタンパク質を、⑤は脂質を多く含みます。調味料はその他として別枠に捉え、アルコール、果物缶、干し果物、ジャム、菓子パン、菓子、清涼飲料は糖尿病には好ましくない食品と位置づけられています。毎日各グループをまんべんなく食べられていますか?何か思い当たる点は見つかりましたか? 食環境を見ると、もっと気づくことがあるかもしれません。一人で食事をする生活で食事時間が短く血糖が急上昇しやすい、逆に大勢・外食が主で食事時間がだらだらと長く糖質の吸収が長時間になってしまうという時間の問題。食事が大皿盛りだと、自分が全部でどれだけ食べるかわからない、野菜は食卓にたくさん並んでいるのに実際はそれほど食べていないなどの問題も隠れており、食事を分析しただけでは分からないこともあります。 食事は本人の食行動を改善させなければならず、初めはストレスを感じる事もあります。また、ストレスの割には結果が見えにくいことから、薬の方が安易で、食事療法になかなか取り組めない方、諦めてしまう方も見受けられます。「習慣の改善はまず一週間から」と自分を勇気づけ、行動を改善していくうちにやがてその行動が新たな習慣となって備わっていくのだと思います。 |
|
 |
|
| (管理栄養士 高野) | |