

| B型肝炎ウイルス(以下HBVと略します)の感染は地球上に普く見られますが、特にアジアやアフリカでは高い感染率を示しています。世界全体では約3億5千万人のHBV持続感染者がいると推定されていますし、日本では約150万人いるとされています。またこのウイルスの長期持続感染の後に、一部の感染者(10%程度)から慢性肝疾患(慢性肝炎、肝硬変、肝ガン)が出現していますが、これが医療における重要な課題の一つとなっているのはご承知のことと思います。この欄ではHBVの遺伝子分類について述べます。 HBVの遺伝子は約3200個の塩基が繋がってできていますが、その分類の仕方は、各感染者からHBVの核酸を精製して、その塩基配列(並び順)を決めます。そして互いに同じ位置の塩基をそれぞれ比較しますと全てが同じではなく此処彼処が違っています。その違いが互いに8%(約250個)以上異なっている場合を違った遺伝子(ゲノタイプ)としています。現在ではゲノタイプAからHまでアルファベットをつけて8種類に分類されています。ゲノタイプを分類する意義は、各々の地域で多くのHBV陽性者のゲノタイプの分類を知ることにより、民族の移動などが大まかに推定できますし、またHBVは人から人へ感染した場合、感染源のHBVゲノタイプと被感染者のゲノタイプの比較によりその感染経路が解明出来ることがあります。一方個人レベルでは、長期間の持続感染後に肝臓病へと進展する速度が、感染したHBVゲノタイプにより異なるので、将来への経過の予測、あるいは治療を行なっている場合では薬剤の治療効果の予測などで、これらにゲノタイプが医療への応用として役立つと考えられています。 HBV感染は世界中でみられますが、地域によりHBVゲノタイプの種類及びそれぞれの頻度が偏って見られます。たとえばゲノタイプAとDは欧州と北米に、ゲノタイプBとCはアジアに、そしてゲノタイプE・F・Hはアフリカや中南米に、それぞれ占める割合が多くなっています。日本の場合では、ゲノタイプBとVの2種類の感染が維持され、前者が約20%、後者が約80%を占めていますが、詳しく見てみますと地方によってゲノタイプBとCの割合が異なります。即ち九州や中国地方等の西側では殆どがゲノタイプCですが、関東から東北に掛けては徐々にゲノタイプBの割合が増えていきます。一方で、沖縄地方はゲノタイプBで占められ、本土とは異なっています。近年、欧米などに感染しているゲノタイプA(成人で感染しても感染者の10%程度が持続感染に移行します)が少し増加傾向にあり、感染の拡大に注意すべきです。 次にゲノタイプと肝炎との間にどのような関連があるでしょうか。日本のHBV感染の殆どは、ゲノタイプBとCのどちらかに分類されますので、この両者を比較してみます。成人で感染すると、多くは自覚症状なく治癒しますが、一部の人は典型的な急性肝炎となります。その中でも症状の重い劇症肝炎におけるゲノタイプBの割合(41%)は持続感染者での割合(20%)に比べて多く、ゲノタイプCより重症化する傾向があります。いっぽい持続感染者ではウイルス量の指標となっているHBe抗原(HBe抗原陽性ですとHBV量が多い)はゲノタイプBの方がゲノタイプCよりも早く(若い時期に)陰性化し、ウイルス量が若年期から低い状態が続きます。この故かゲノタイプBの感染者では、慢性肝疾患に進行する速度が遅く、慢性肝炎、肝硬変、肝ガンへと進行するにつれ、ゲノタイプCの割合が高くなる、という疫学的調査結果となっています。このように、持続性感染者の自然経過ではゲノタイプCが慢性肝疾患に進展する割合が高いのですが、慢性肝疾患に対する治療に関してはゲノタイプ別で違いがあるのでしょうか・現在、慢性肝疾患の治療に抗ウイルス作用や免疫増強作用を示すインターフェロンやウイルス増殖に要する酵素の阻害剤であるラミブジンなどが使われています。これらの薬剤を一定期間使用後、治療効果にウイルス量の指標であるHBe抗原の陰性化率をとるとゲノタイプBの方がゲノタイプCよりも2倍程高い、すなわちゲノタイプBの方が薬剤に対して反応性が良いという結果が得られています。そのため、治療に際しゲノタイプを見ておくことは意味があろうかと思います。今後も投与方法や薬剤の種類など治療方法も改良されていますので、ゲノタイプCにも効果が一層上がるような治療法が期待されると考えます。 |
|
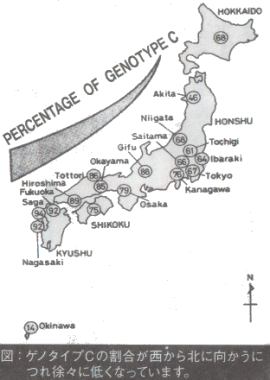 |
|
| (研究室長 津田 文男) | |