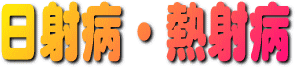
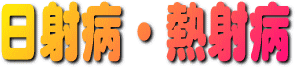
| 強い日差しの中に長時間いると体温が上昇し、気分が悪く、めまい、頭痛、吐き気などを起こしてきます。汗も出しきって、皮膚は乾燥し、息苦しくなってきます。時に失神することもあります。この状態を日射病と呼んでいます。 一方、高温、多湿、無風といった環境の中で激しい労働や運動をしていて、体温調整ができなくなった状態を熱射病と呼んでいます。 どちらも高温による障害で、今日では熱中症という言葉にまとめられています。 熱中症は高温の外部環境と、激しい運動による体の内部からの熱で体温の調節機構が異常を来し、体温の上昇により、体の諸臓器、器官がまっとうに働かなくなります。老人や幼児では体温の調節機能が万全でなく、自身は運動をしていなくとも、もっぱら暑い外部環境だけで熱中症に陥ります。 高温環境で体温が39〜40度にも上昇すると、細胞の酵素の働きが障害され、細胞自身が死んでしまい、代謝経路が壊され、生体の生活活動の系統が破綻し、時に死亡することもあります。 熱中症になると、頭痛、疲労感、めまい、吐き気などが始まり、筋肉の痙攣を起こすこともまれではありません。老人ではもともと、体温調節能力が衰えている上に、心臓、循環器の障害があって、病状は若者にくらべ深刻です。前記の症状に加え、顔面蒼白、多量の発汗、起立性低血圧で立ち上がれなくなり、精神状態も不穏になります。40度を越す発熱もあります。 熱中症に陥ったら、素早い治療が決め手です。救急車を手配し、その間に患者を涼しい環境に移し、衣服を脱がし、風を送り、冷たい水で体を拭き、霧吹きで水を体に吹きかけ気化熱で体温を下げます。脇の下などを氷や冷却剤で冷やします。呼びかけたりして意識があるかを確かめ、意識があれば冷水、あるいはスポーツドリンクなどを飲ませます。ふくらはぎなど全身ではない痙攣があればその部位を冷やし、食塩水、あるいはスポーツドリンクを飲ませます。血管が拡張して脈拍が微弱だったり、手足が冷たかったりしたら、足を高めにし、四肢のマッサージをします。 熱中症の予防には外部環境に応じた運動を指導することです。精神主義に偏したしごきや、水の補給を禁じたトレーニングを指導している例がありますが、全く無意味で有害です。 老人は渇感が鈍くなり水分補給が少なかったり、頻尿を恐れて自ら制限していることもありますが、飲水を心がけてください。 |
|
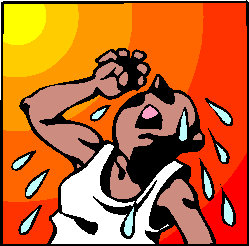 |
|
| (医師 相川 達也) | |