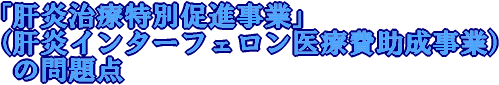
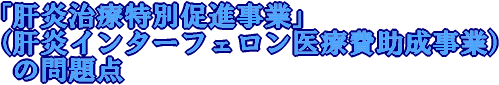
| 平成20年4月から開始された表題の事業(以下助成事業)で、20年度に助成を受けた患者さんは44731人で、目標の10万人には遠くおよびませんでした。 肝ガン発症を抑制するには早期に、肝炎ウイルスを排除し肝炎を沈静化しなければなりません。肝炎患者さんが治療を早く受けられるようにするには、制度の問題点を、診療の現場から考えてみました。 そもそも肝炎は敗戦後の民間血液銀行に頼った売血制度を中心に急速に拡がり、覚醒剤を買う金のために繰り返し売血する不健康な売血者から輸血用の血液汚染はさらに拡がっていきました。また、注射針、注射筒を消毒せずに繰り返し使用した医療機関からも感染者が出ました。更に、肝炎ウイルスに汚染された血液製剤が止血の目的で大量に供給され、危険が指摘されたあとも回収されずに使用が続けられて感染者を増やしました。わが国の肝炎は様々な事象が絡み合って、おこされた医原病です。 厚労省は肝炎研究7カ年戦略(2008年6月20日)を立て、今後の目標として、B型肝炎の臨床的治癒率を30%から40%、C型肝炎の根治率を50%から75%に上げるなどの目標を掲げました。そこで、肝炎治療の第一線にいる立場から、この事業の問題点を挙げてみました。 1.B型肝炎患者への対策が不十分である。 助成事業で対象はインターフェロン医療費の助成をうたっていますから、ウイルスの増殖を抑える核酸アナログ製剤を使うB型肝炎患者さんははずされています。 2.再治療を認めていない。 1回のインターフェロン治療で肝炎ウイルスを排除できる成功率は治療をやり遂げられた患者さんで50%ですが、副作用などで脱落してしまう方が20%近くあり、治療開始したヒトすべてを母数にすると排除率は40%前後です。脱落してしまう患者さんに対する治療にはインターフェロンを減量したり、治療を延長したり、様々な対策がありますが、治療期間が最長72週と規定されていて、再治療を認めないため、75%までの成績向上は新薬の提供がないので、難しいでしょう。 3.副作用などで、2ヶ月以上休薬すると助成は認められなくなりますが、医学的には根拠がありません。 4.二種類のペグインターフェロンが市販されているが、効果に差がないのに適応対象を分けていて、現場は混乱する。 5.インターフェロンの価格は高すぎる。 6.患者さんは職場をやめて、高齢化してから治療を受ける場合があり、働きながら治療を受けられる、政策的な配慮が必要です。 7.前国会で廃案になった前与党の法案説明にウイルスを排除するという本人にも有利なことだから、一定の自己負担は必要と書いているが、肝炎の背景を知れば、この意見は誤りです。 現在、国会では選挙で廃案になった「肝炎対策基本法案」が再提案されるようです。肝炎は私病ではなく、医原病であると、国の責任を認めるとしています。その理念が貫かれることを期待しましょう。 |
|
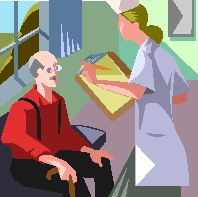 |
|
| (医師 相川 達也) | |