

| ■はじめに | |
| 最近では毎年3万人以上の方が肝癌で亡くなられ、この数字は肺癌、胃癌、大腸癌による死亡数に次いで多くなっています。また、患者さんの高齢化が進行していると言われています。そこで当院での最近5年間の新規発症の肝癌症例の特徴をまとめ、今後の診療に際して患者さん方にお知らせすることと致しました。 | |
| ■目 的 | |
| (1)第一線の医療機関としての当院で、新規発症の肝癌はどの様な集団から発症しているか。 (2)癌の発生率はどの程度か。 (3)定期的な観察下にあった患者さんと、そうではなかった患者さんとで特徴が見られるか。 |
|
| ■対象と調査期間 | |
| 2004年1月1日から2009年6月日までに当院に通院した症例が対象です。 [主な基礎疾患] (1)B型慢性肝疾患(慢性肝炎、肝硬変):約120名 (2)C型慢性肝疾患(慢性肝炎、肝硬変):約680名、 (3)アルコール性肝障害 (4)非アルコール性脂肪性肝炎(NASH) (5)原発性胆汁性肝硬変(PBC):約80名 残念ながら、(3)と(4)の群の詳細な人数はつかめませんでした。 |
|
| ■結 果 | |
| (1)表1に全体の結果を示します。診断された症例の基礎疾患と、その後受けた治療が分かるように表にまとめました。 ①5年間で50例(概算で年率1~2%)の新規発症の肝癌が見られた。 ②B型肝炎の症例は若年で肝癌になっていた。 ③アルコール、NASHの症例では肝癌のサイズがより大きかった。 ④全体で33例(66%)が手術を含む局所療法を受けた。 ⑤定期的な経過観察外の症例では治療出来ないほどの進行症例が多かった。 (2)生存率 生存率を表2に示します。 ①当院での手術は20例(40%)であり、全国統計での29%よりも多かった。 ②手術例での5年生存率が良好であった。但し、全国統計の手術例での5年生存率約は52%であり、それよりは低値であった ③陽子線症例での生存率が経過観察群と比して良好とは言えなかった  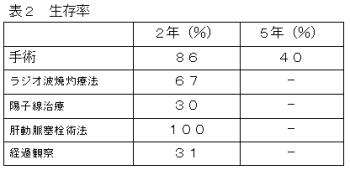 |
|
| ■考 察 | |
| (1)肝癌はB、C型関連の症例が全体の82%、NASHその他が18%であり、ウイルス関連以外の症例が他の統計と比して若干多かった。今後、背景因子の解析(B型の既往等)が必要と考えられた。 (2)手術例は20例(40%)と、全国統計(29%)と比して比率が多かったことから、当院の肝癌早期診断の努力は機能していると判断された。 (3)しかし、手術例での5年生存率が低かったことから予後不良因子(基礎疾患の状態、大きさ、個数)のより詳細な検討が必要と考えられた。 |
|
| ■まとめとお知らせ | |
| (1)少し難しい表現があったかもしれません。大切なのは慢性的な肝疾患がある患者さんは定期的な画像診断を受けていただくことで手術をはじめとした治療が受けられる機会が多かったということです。通院が長くなるとつい定期的な検査を怠りがちですが、患者さん、医療者双方の努力で是非経過観察をきちんと持続していきましょう。 (2)精密検査、手術等が必要な方へ 肝癌が疑われて精密検査が必要な方や肝癌の診断がほぼ間違いのない方たちにとっては手術療法を視野に入れた専門医療機関への受診を希望される場合もあろうかと思います。昨年の2月からコアクリニック金曜日午後外来において、筑波大学消化器外科(肝癌を手術する外科)の大河内信弘教授、福永潔講師の診療が行われており、当院と筑波大学とで緊密な連携をもって診療に当たっていますのでご活用下さい。(希望者は外来主治医と相談し予約をお願いいたします) |
|
| (医師 小島 眞樹) | |