

| 今年の4月から、肝炎治療費助成制度の第二弾ともいえる改定が行われ、広い範囲にわたって肝炎患者さんに対する治療援助が行われます。できれば、ひろばに具体的な制度の変更点、改善点などを書こうと、行政の発表を待っていましたが、こうして書いている3月20日の時点では、全体の姿が見られません。ただし、今度の改正で、これまで助成の対象外であった、B型肝炎治療の内服薬の核酸アナログ製剤(バラクルードなど)が対象になることは確実なので、B型肝炎の現在の姿をご紹介することとしました。 B型肝炎の治療を、C型 肝炎と比較するときに最も違うところは、ウイルスを排除できたという、単一の基準が作れないということです。それはB型肝炎ウイルスが様々に変化して(遺伝子が変異して)、病態を複雑にしているからです。 |
|
| ■B型肝炎ウイルスマーカー | |
| B型肝炎ウイルス(HBV)に感染しているという印(マーカー)には、血液(正確には血清)の中にHBVが作り出したHBs抗原、HBe抗原、また、ウイルスの増殖とウイルスのタンパクを合成することに必要な遺伝情報をになっているHBV-DNAがあります。また、これらのマーカーに対応するかたちで、感染を受けたヒトの体の免疫反応でできたHBs抗体、HBc抗体、HBe抗体などがあります。これらはそれぞれに意味があり、HBV感染による、生体の状態を理解する手助けになります。HBV-DNAの塩基配列はウイルス毎に違いがあり、お互いに8%以上の差があるときに、それぞれ異なった遺伝子型と分類します。遺伝子型はAからHまでが知られています。遺伝子型は世界の各地域で異なり、民族の移動などを推定することが出来ます。日本人で一番多い遺伝子型はC型です。個々の患者さんのHBV-DNAの塩基配列を比較することで、感染経路を特定することもできます。また、HBVは宿主の免疫反応に曝され、その存在を守るように、時間とともに遺伝子上の塩基配列を変化させていきます。 | |
| ■感染時期と病態 | |
| ヒトがHBVにいつ感染するかによって、そのヒトの病態が異なります。感染時期には、大きく二つの場面があります。第一には幼児期の感染です。HBVの感染を受けた母親から生まれる時に感染する母児間感染が代表的ですが、小児期の予防注射の際に、注射針を変えずに回し打ちをしたり、医療機関などで使用した注射針、注射筒が不完全な消毒であったために感染した可能性も推定されています。もう一つは成人の感染です。 〈幼児期の感染〉 幼少期の感染では直ぐにはウイルスが排除はされず、肝臓には異常がなく、健康キャリアとしてウイルスとヒトとの平和共存のままでヒトは成長してゆきます。この時期を免疫寛容期といいます。そして、やがて宿主が思春期にかかる頃から免疫をになうリンパ球がHBVに感染している肝細胞へ攻撃を開始し、免疫寛容期は終結します。この免疫圧力により、HBV野生株のHBe抗原の生成にかかわっているコア遺伝子の変異が起こり、HBe抗原は減少し、HBe抗体が目立ってきます。HBVもHBe抗原を産生しない株が優勢となり、この株を変異株と呼んでいます。野生株と変異株の置き換わる状況は様々で、この置き換わるときに肝細胞も変性、壊死を起こして、肝機能検査値も上昇し肝炎が起きます。この肝炎の変動する時期を免疫的排除期と呼んでいます。そして、やがて炎症は沈静化し、HBe抗原は陰性となり、HBe抗体が陽性となります。これをHBe抗原のセロコンバージョンと言います。変異株は野生株に比べ増殖能は低く、肝炎も活動が収まります。この時期を低増殖期と呼んでいます。かつてはこの状態で肝炎は沈静化し、治療目標が達せられたと考えられていました。しかし、一部の感染者では肝機能異常が続いて、慢性肝炎から肝硬変へと病状が進行することもあります。肝硬変への移行は年間2〜3%とされています。肝ガンの合併もこの時期から見られるようになり、慢性肝炎からは年間1%ですが、肝硬変からは年間3〜10%で肝ガンが見られています。B型の肝硬変症のヒトでの肝ガン発症の頻度はHBVの感染のないヒトの100〜300倍とされています。 長期間観察していると、野生株も変異株もともに肝硬変、肝ガンの危険性においては変わらないこともわかってきました。最近は、新たなHBVの感染が減って、B型の慢性肝疾患は変異株をもったヒトの方が数としては多くなっています。 〈成人の感染〉 これまでは成人での感染経路は輸血などの医療行為による場合が多かったのですが、現在圧倒的に多いのは性行為感染と、覚醒剤などの回し打ちによる感染です。感染の結果、急性肝炎を発症したり、あるいは、感染自体を自覚しないままのこともありますが、どちらの場合も、自然治癒するとされています。しかし、中には少数ながら(1%前後)劇症化し、死の転帰をとります。この場合、感染したHBV株は野生株よりもHBe抗原を産生しない変異株が多いことが注目されました。変異株はキャリアの場合も慢性肝炎の重症化の原因になっています。 |
|
| ■潜伏感染 | |
| 急性肝炎はHBs抗体が出現して治癒したとされますが、その肝炎の治ったヒトの肝臓を生体肝移植として提供すると、提供を受けたヒトが重症のB型肝炎になり、不幸な転帰をとることがあります。また、B型肝炎が治癒したヒトが抗ガン剤など強力な免疫抑制効果のある薬剤を使用された時に、B型肝炎が再燃することも経験します。このことから、HBVに感染すると、ウイルスは肝細胞内に長くとどまっていて、完全には排除されないと考えられるようになりました。これをHBVの潜伏感染と呼んでいます。潜在したHBV感染は移植や、免疫抑制剤を使用したときばかりでなく、HBV(HCVも)が血液には証明されていない肝硬変や肝ガンの隠れた原因になっている可能性も否定できません。私たちはこのHBV潜伏感染をチェックするために抗HBc抗体を測定しています。測定法としては以前から使われている凝集法を使い、値が高いときには、現在もHBVが感染している可能性があると考え、痕跡的にでもHBV-DNAが存在しないか、ヒトの肝細胞にHBV遺伝子が組み込まれていないか慎重に検査を行わなければなりません。さらには他のウイルスの感染はないか検索を続けます。 このようにHBVによる慢性肝疾患は複雑な経緯をとって病態を変化させています。今日、B型肝炎の治療はインターフェロンか核酸アナログ製剤が使われるようになり、今後、病気の進展を阻止してくれるものと期待されています。この点は次回に説明いたします。 |
|
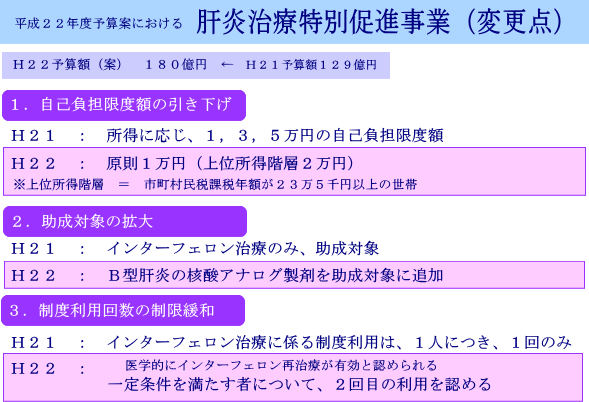 |
|
| (医師 相川 達也) | |