

| 2010年4月からB型慢性肝疾患に対する治療助成事業の対象治療薬として核酸アナログ製剤が認められました。すでに、当院の患者さんの中にはラミブジン、アデフォビル、エンテカビルを服用されている方々があり、4月からは自己負担が軽減されることとなります。 | |
| ■核酸アナログ製剤の働き | |
| 肝炎に使われる核酸アナログ製剤とはどんな働きをするのでしょうか。 よく知られているのは、HIVの治療薬として広く使われ、エイズで亡くなる方を激減させることができた画期的な薬剤と同じ系統の薬剤です。 今回のB型肝炎ウイルス(HBV)による慢性肝疾患のガイドラインで、第一選択薬とされたエンテカビル(バラクルード)の作用について簡単にご説明しましょう。HBVが肝細胞内でその遺伝子であるDNAが複製されるときには、いったんRNAに遺伝情報が渡され、それからウイルス自身が持っている逆転写酵素を使って新たなDNAを複製していきます。バラクルードはこの逆転写酵素の遺伝子に似た構造を持っていて、酵素の産生を妨害することで、新たにHBVが増殖することを抑制します。しかし、その作用はウイルスを完全に排除するわけではありません。肝臓の細胞核内にはウイルスの増殖の際に複製の中間体として働く、cccDNAが残っていて、薬剤を中止すると、血中にHBV-DNAが再出現してきて、肝炎が再燃することがあります。 |
|
| ■C型肝炎治療との違い | |
| HBV治療は、完全にウイルスを排除することで肝炎の終熄を目的とするC型肝炎ウイルス(HCV)治療とは、はっきりと違います。母児感染で感染した患者さんは思春期になると、肝炎が始まり、その時にHBe抗原が消失し、HBe抗体が増加します。この時、HBVは野生株から変異株が優勢となり、多くの患者さんは肝機能検査も正常化して、臨床的には治癒したと考えられてきました。核酸アナログ製剤にしても、インターフェロンにしても、治療目的は自然治癒の状態に持ち込むこととしています。自然治癒した患者さんの多くは血中のHBV-DNAは検出限界以下となりますが、時に、肝機能が正常でHBe抗原が見られなくとも、HBV-DNAが陽性のことがあり、長期間観察していると肝炎が再燃して、病態が悪化します。 現在の治療ガイドラインでは以下のように規定されています。この場合、B型慢性肝疾患であることだけで、HCV治療の時のような肝硬変か慢性肝炎かは問いません。 表1.厚生労働省研究班による治療標準化ガイドライン(35歳未満) 表2.厚生労働省研究班による治療標準化ガイドライン(35歳以上) ここで、年齢の要件が入ったのは、核酸アナログ製剤が性細胞に対する安全性が確立していないことと、歳までは自然治癒の可能性があり、投薬の時期を慎重に見定めることも重要であり、HBe抗原陽性の場合はインターフェロンを1年間使って治療目標に早く到達しようというのが目的です。 |
|
| ■治療期間と服薬期間 | |
| バラクルードは2006年に使用が認められたばかりで、その長期の効果についての成績はありません。それで、これよりも先に使用されていたラミブジンの成績を参照すると、肝ガンの発生、肝硬変の悪化を治療の終了としたときに、薬剤を使わなかった人たちより、統計的に勝れていたことが報告されています。バラクルードは、ラミブジンでよく見られた肝炎の再燃が圧倒的に少なく、安全性が高いことは確認されていますから、これを第一選択薬としたことは合理的です。これまでの経験からバラクルードを使用すると、HBV-DNAは測定限界以下となり、肝機能も正常化しますが、ここで直ぐに服薬を中止すると、再燃を見るため、患者さんの病状の程度を見ながら、個々に対応しているのが現状です。文献を当たってみると、いつまで使うかは、議論が分かれ、例えばラミブジンの場合にはHBe抗原がHBe抗体に変わってから、6ヶ月間つづけた場合、30歳以下で再発の頻度は12.3%と低いのですが、30歳以上では53・6%と高率となり、高齢者では更に長い服薬が必要であるとする報告があり、ひとつの目安になると思われます。また、もっと厳しく、自然治癒と同じ状態になった時を使用の終了の目安としても、これは絶対的な基準ではなく、薬剤の服用を止めてからも、定期的な肝機能検査と画像検査を受けなければなりません。また、腹水や黄疸のある進行した肝硬変症は適応外とされていますが、この病態の方に使用を納得してもらっての経験ではHBV-DNAが測定限界以下になり、トランスアミナーゼも落ち着いて、予想された寿命よりも延命できたこともありました。患者さんの立場に立って、よりよい選択をしたいと考えています。また、HBV-DNAの他に、治療の効果を見るマーカーとして、肝生検が必要ですが、cccDNAの測定なども出来れば更に確実に治療がすすめられることでしょう。 | |
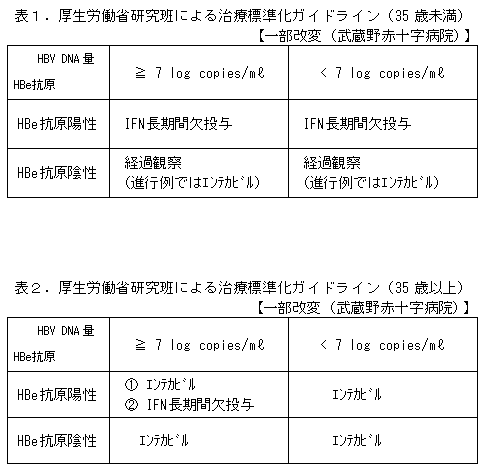 |
|
| (医師 相川 達也) | |