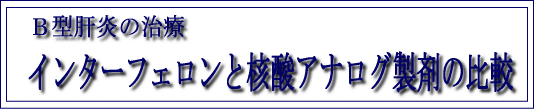
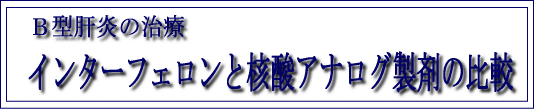
| 現在、B型肝炎に使われている薬剤はインターフェロンと核酸アナログ製剤です。両者の長所、短所を表にまとめてみました。インターフェロンは直接ウイルスに作用する力は弱いのですが、生体の免疫反応を調整して、ウイルスに感染している肝細胞を排除することで、ウイルスを除去します。核酸アナログ製剤はウイルスの増殖に関わるウイルスの酵素の働きを妨害して、ウイルスの量を減らします。ウイルスの排除か増殖の抑制か、目的を決めて治療法を選択します。(表) わが国ではB型慢性肝炎の治療に当たって、患者さんの年齢、HBe抗原の有無、ウイルス量で薬剤の選択基準を示しています。しかし、HBV-DNA量、ALT値について、ある一点の評価ですが、長期に観察していると、これらの値は動揺することが多く、現在安定しているかに見えても、肝炎は意外と進行した状態であることも経験します。肝炎の進行状態をどう判断するかは、個々の事例で判断すべきでしょう。各国で実施されている、ガイドラインを厳格に実施すると、長年観察している患者さんの自然経過に当てはめた時、10〜15%の人が適切な治療を受ける機会を失ってしまうという問題も提起されています。また、わが国の健康保険では、まだ従来型のインターフェロンのみが適応とされ、世界の標準とされているペグインターフェロンの使用が認可されていませんから、早急にガイドラインは改訂されなければなりません。 B型肝炎の治療効果の判定は血液検査でHBV-DNAが測定できなくなることと、ALT(GPT)が正常化することが上げられています。これに加えて40年前、B型肝炎の発見のきっかけとなったHBs抗原の血液内の量(値)が低下すると肝細胞内で、HBVの増殖の鋳型となるcccDNAが減少していることが知られてきて、よい指標になると最近注目されてきました。
|
|||
| (医師 相川達也) | |||