| 去る10月30日に開催しました勉強会には台風にも拘わらず、大勢の皆様にお越しいただきありがとうございました。しかし、時間が押していたため、充分にご説明できなかった点も多々ございましたので、再度ひろばの紙面をお借りして、何故高血圧を是正しなければならないのか再確認いたしたいと思います。また、塩分制限と一口に言っても、なかなか難しいものがありますので、当院の管理栄養士から献立などについて追補させていただきます。 |
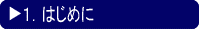 |
日本高血圧学会で作成された高血圧治療ガイドライン2009によりますと、30歳以上の男女の半数近くが、収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上、あるいは降圧剤内服中で、日本の高血圧者の総数は3600万人とも4000万人とも言われています。
血圧が高いほど、脳卒中、心筋梗塞などの心臓疾患、腎臓病に罹患する率が高く、特に心臓病は全年齢層で血圧が高い人ほど、罹患率、死亡率が高くなっています。しかし若い人ほど未治療の人が多く8?9割の方が高血圧に対して何の対策もとっていませんし、その他の年齢層でも約半数の方が、十分な降圧がされず管理不十分と言われています。
|
 |
心臓は収縮と拡張をくり返して血液を全身に送り出しています。動脈の中の圧はそれに応じて上下し、心臓の収縮で最高になった時の値が最高血圧、又は収縮期血圧で、心臓の拡張により最低になった時の値が最低血圧、又は拡張期血圧です。
|
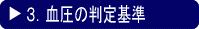 |
血圧に関してはガイドラインが日本高血圧学会により決められており、最新版が2009年に出されています。(表1)
血圧は1回だけの測定では高血圧の診断がつかないことが多く、何回かの平均値で決められます。また、収縮期血圧と拡張期血圧とはそれぞれ独立した要素なので、異なる分類に属した時には高い方の分類に入れることになっています。
|
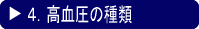 |
大きく分けて本態性と二次性とがあります。
本態性とは原因がわからないもので、高血圧の90%はこちらです。生活習慣、遺伝が影響するのですが、運動不足、ストレス、アルコールの飲み過ぎ、肥満、塩分のとり過ぎなどが原因となります。
二次性とは表2に示したように、何らかの病気が原因で高血圧となるものです。特に多いのが腎臓病や内分泌の異常です。
|
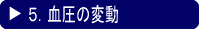 |
本態性高血圧といっても状態により血圧は種々変動します。それは、特殊なパターンがあり表3にありますように代表的な5種類が知られています。
これらのパターンを24時間血圧計で確認することは治療上重要であるばかりでなく、ご自分の生活リズムと血圧の変化を知ることにより、合併症を防ぐ効果もあります。
24時間血圧計で測定した血圧の変動グラフをお示しします。
グラフ①は正常の方です。このように、一回毎の変動はありますが昼の平均は129/82、夜は119/74、1日は123/79と正常範囲です。但しこの方の場合、受診時には何時も150/90で、白衣高血圧と言えます。しかし、白衣高血圧は将来本当の高血圧になる確立が高いと言われています。
グラフ②は、夜間高血圧の方です。血圧は夜間には低下し、それによって動脈硬化の進展等が抑えられるのですが、この方は昼も夜も150/85前後の平均値です。
|
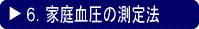 |
出来るだけ上腕で測定して下さい。測定の条件は表4に示しました。測定の変動の大きい方は、できるだけ長期間測定し、受診時に記録をお持ち下さると、非常に参考になります。
|
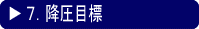 |
年令及び合併症の有無により降圧目標(表5)が決められて居ます。高齢の方でも適正な血圧のコントロールにより健康な生活ができると証明されていますので、降圧は必要です。
次回(後編)は、高血圧の中でも特に心疾患について、そして高血圧の予防をご説明いたします。 |
|
|
|
|

