

| 栄養士なのに専門的な指導をしないと力量不足を認めなくてはいけないのかもしれませんが、私は糖尿病の栄養指導において糖尿病食品交換表の使い方をほとんど指導しません。それは、もし自分が糖尿病患者で、毎回の食事に交換表を用いて計算しなければならないとしたら、率直に面倒だと思うからです。 糖尿病食品交換表では食材が6つの表に分類され、1単位80kcalとして、1単位ごとの重量が記載されています(調味料、酒・ジュース、菓子、外食は別表です)。自分の適切な摂取エネルギーを知り、単位化し、6つの表に振り分けていくのです。 こう聞くと難しいように思えますが、糖尿病食品交換表に記載されている1200kcalと1840kcalにおけるエネルギー配分例を比較して見ると、違ってくるのは表1(穀物・芋・豆)と表3(魚介・肉・卵・大豆)、表5(油脂)だけです。表3は2単位増減するだけですし、表3が増量すれば調理法でおのずと表5も増加します。エネルギー増減のカギを握るのは表1なのです。つまり、自分に合った主食と芋・豆の量を知れば食品交換表が理解できなくても血糖コントロールはある程度できると思うのです。 さて、アメリカではカーボカウントという糖尿病食事療法が主流です。食後の血糖上昇はエネルギー量ではなく炭水化物量に由来するという根拠から、食品の炭水化物を計算して食事をとるという方法です。炭水化物以外は厳密に計算しないので、メイン料理の量を増やしたり、揚げ物を人並みに食べることも難しくありません。どちらにせよ主食の御飯やパン・麺類は計量して適量を知っておくことが糖尿病食事療法の最低限ポイントと言えそうです。 例えば普通の御飯量180gを半分にするとどうなるか計算してみます。1日3回、御飯を半分にした場合エネルギーは480kcal下がります。脂肪を1kg減らすには7000kcalの消費が必要と言われていますから、生活活動が変わらなければこれだけで1カ月2kg減量する計算になります。炭水化物量としては100g減っていますから、減量が必要ない糖尿病の方なら減らしたエネルギー分で炭水化物量の少ないおかずを食べることができます。 これを例にして栄養指導すると、食事交換表に抵抗感のある患者さんでも、自分でできそうだと思ってくれるようです。食事療法は血糖コントロールや食後高血糖が良好となり、続けられるものでなければなりません。栄養指導の短い時間でポイントを理解し、すぐに実践できる具体性と簡単さが必要だと思うのです。 |
||
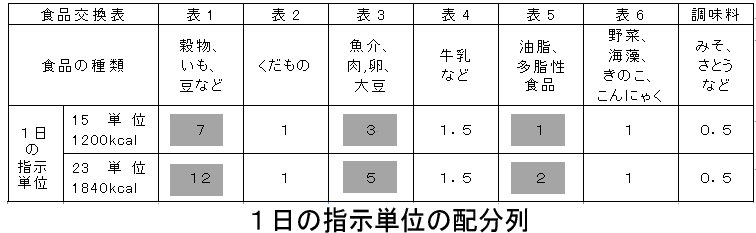 |
||
| (管理栄養士 高野) |