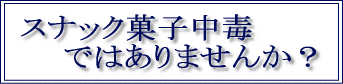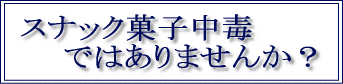スナック菓子はついつい手が伸びますよね。と栄養士らしからぬ言葉ですが、このスナック菓子に依存性があるのを意識した事はありますか?子供はもとより、成人でもスナック菓子に依存する傾向があり、今や疾病の一因となっている可能性があるのです。
スナック菓子が止まらなくなる原因の一つは、スナック菓子に含まれるうまみ調味料です。原材料の欄には「アミノ酸」や「たんぱく加水分解物」などと記載されています。一般名は「グルタミン酸ナトリウム」「イノシン酸ナトリウム」「グアニル酸ナトリウム」です。
うまみ調味料は1960年代に微生物を用いる製法が開発され、安く大量に製造できるようになり、広く使用されるようになりました。当時は化学調味料と呼ばれていました(現在もこの呼称を使用する事があります)。1980年代のグルメブームで一時は負のイメージのあった化学調味料ですが、うまみ調味料と呼称を変え、現在ほとんどの加工食品に含まれているといっても過言ではありません。
さて、近年30年は飽食の時代と言われています。飽食の時代に生まれ、飢餓を知らない世代が親となり、出産・養育期を迎えています。うまみ調味料入りの食品で育ってきた親が、自然の旨味だけでおいしいと思える食事を作れるはずがありません。添加された濃い旨味は日本人の味覚を鈍化させています。自然の旨味は繊細で、添加された旨味に慣れた人にとっては物足りなさを感じるのです。また、スナック菓子には保存料としてリン酸塩が添加されています。リン酸塩は亜鉛の吸収を阻害するので、スナック菓子を多く食べていると亜鉛不足から味覚障害になる可能性もあるのです。
また、現代はストレス社会とも言われます。ストレスにより交感神経が亢進した状態では、グリコーゲンが分解され血糖が低下し空腹感を感じます。そんな時に手軽に間食できる食品として、スナック菓子は現代のニーズに合っているのです。
子供の場合、教育現場で食育が行われています。食育においておやつの時間は食事の一部と位置づけられ、内容もおにぎりや果物など食事同様に構成されます。おやつの時間はお菓子の時間ではないのです。対して成人では食育に触れる機会がありません。自分で意識しないとその頻度に気付かず、堆積して健康の害になることがあるのです。一度、口に入れるすべての食品を見直してみてください。 |
 |
|
|
|