

| 血小板とは、血液中に含まれる細胞成分の一つで、その作用は、血管が損傷した時に、その部分に集まって傷口を塞ぎ、出血を止める働きをしています。怪我をした後に自然に血が止まるのは、血小板が正しく機能している証拠と言えます。 血小板は、骨髄中の巨核球という大きな細胞の細胞質がちぎれた破片からできる直径が2ミクロン程度の小さな細胞で、骨髄を出てから10日間ほど血液中に存在して体内を循環し、最後は脾臓で壊されます。 血小板の異常には「数の異常」と「凝固機能の異常」の二つがあります。血小板の数が通常よりも少なくなり、10万/μl以下となる状態を「血小板減少症」、血小板の数が多くなり、40万/μl以上となる状態を「血小板増加症」といいます。凝固機能の異常には、血小板の中に含まれている各凝固因子の欠損や発現の異常、あるいは血小板そのものの機能異常により、血液が固まりにくくなるものです(血小板の数が減少したり、その機能が低下したりすると、出血が止まりにくい、ちょっとしたことで青あざができる、鼻血が出やすい、歯肉から出血しやすい、などの症状がでてきます)。 数の減少の原因は、血小板の産生能力の低下によるものと血小板の寿命の短縮によるものの二通りに大きく分けられます。骨髄での血小板の産生能力の低下をもたらす疾患として、再生不良性貧血・急性白血病などがあります。また、寿命の短縮をもたらす原因疾患として、血小板の破壊の亢進による、肝硬変・バンチ症候群・全身性エリテマトーデスなど、利用の亢進による、播種性血管内凝固症候群などがあります。 逆に、血小板の数が多くなりすぎると、血液が固まりやすくなり、血液が固まってできた血栓が血管をふさいで、脳梗塞や心筋梗塞などの危険性が高まります。その原因疾患として骨髄機能自体の異常である一次性増加症(本態性血小板血症・真性多血症・慢性骨髄性白血病など)と二次性増加症があります。 肝臓は、血小板を増やす働きのある物質を製造していて、肝臓の働きが悪くなると、この物質(トロンボポエチン)を作る能力が低下して血小板の数が減少します。また、慢性の炎症により肝臓組織の繊維化が進み、肝臓内の循環血液量が減少すると、脾臓の循環血液量が増加し、脾臓の血小板を破壊する機能が亢進して血小板の数が減少します(これを利用して、肝臓組織の繊維化進展度の評価法に使われています)。このように、肝臓の障害の程度と血小板の数は大きく関係しています。 |
||
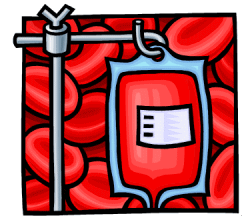 |
||
| (臨床検査技師 堀江) |