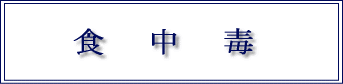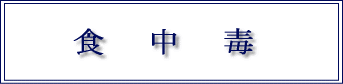これからの季節は食中毒が増えてきます。当然冬季にもみられるのですが特に夏は暑く湿気が多いので、原因となる細菌が増えやすく食中毒の発生が多くなります。それでは食中毒とは何でしょう。
食中毒は原因となる物質により、大きく4つに分類されています。
|
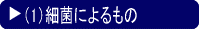 |
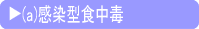 |
摂取した食物の中の細菌が腸管で増殖して生じるので症状が出るまでにある程度時間があります。短い腸炎ビブリオで12時間、サルモネラで12~48時間、カンピロバクターやエルニシアとなると2?7日後に発症しますので、何が原因か判らなくなることもあります。
主な菌とその特徴です。
①サルモネラ菌:生肉、食肉加工品、鶏卵、淡水魚、ペットが感染源。75度、1分以上の加熱で死滅、卵や生肉は4度以下で保存、卵の殻に付着していることもあるので、卵は容器に入れて保管するように。熱に弱い分乾燥に強く冷凍食品の中でも数年生きることができます。
②腸炎ビブリオ: 近海の魚介類、汚染された調理器具、特に夏季に多いので、初夏から秋にかけての近海物の魚には注意が必要です。特にエラ、腸、鱗にかくれていますので調理での注意が必要です。真水、加熱に弱く、65度、1分以上の加熱で死滅。
③カンピロバクター:生肉(特に鶏肉、牛レバー)75℃、1分以上の加熱で死滅、低温、冷蔵庫の中でも繁殖します。ペットにも注意が必要ですので、ペットとキスはしないように。
④エルニシア菌:牛乳、乳製品、食肉などの冷蔵品とペット。75度、1分間の加熱で死滅、低温細菌で冷蔵庫の中でも繁殖するので冷蔵庫を過信しないように。増殖速度は遅いので早めに食しましょう。充分加熱すれば問題ありません。
これらの感染型食中毒の症状は一般的に腹痛、嘔吐、激しい下痢など急性胃腸炎症状と発熱で特にサルモネラは長期に排菌するので注意が必です。 |
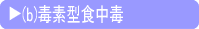 |
食品中で増殖した原因菌が産出した毒素を摂取して起こるので症状が出るまでの時間が短いのが特徴です。
①黄色ブドウ球菌:これは誰でも持っている常在菌で、特に傷口や鼻腔にみられます。ですから、おにぎりやサンドイッチ、弁当などを菌のある素手で扱ったときに危険です。この菌に汚染されていても、外観も臭いも味も変わらず、菌が出した毒素で中毒します。菌そのものが消えても、出された毒素のみ残って中毒になることもあります。食品中で熱に強い毒素を出しますが、低温では発育しません。調理中は顔をいじらないようすることと、一寸したささくれや手荒れにも菌が付着するので、おにぎりを握るときには手袋やラップを使用して下さい。食べる頃にちょうど毒素が出てしまいますから。
②ボツリヌス:缶詰、瓶詰め、真空パック等空気の無いところに潜伏しています。非常に致死率が高く、30~80%は死亡します。この菌は、嫌気性菌のため真空の包装の中でも増殖し熱にも消毒液にも強い芽胞というものを作ります。しかも急性胃腸炎の症状だけでなく、神経毒があり神経麻痺や呼吸筋麻痺を起こすため致死率が高くなりますが、減少はしています。ただ乳児性ボツリヌス症はハチミツに含まれていることがある芽胞の摂取で発症しますので、乳児は(1歳未満)は食べないで下さい。 |
 |
①病原性大腸菌(0-157など):これは井戸水、生肉、ハンバーグ、生野菜などから検出されています。この菌は感染型と毒素型(ベロ毒素と言います)の両方の性質を持つ中間型で、しかも少量で発症します。出血性大腸炎や溶血性尿毒症症候群を起こすと致命的です。水中でも10日前後生息しますが、加熱に弱いので75度で1分以上の加熱が必要です。生肉を扱うときはまな板、包丁すべて別にします。
②ウェルシュ菌:肉などタンパク質の食品が原因で、肉の唐揚げや、カレー、シチューなど常温で放置すると増殖し、エンテロトキシンという毒素を出し中毒を起こします。10度~60度の範囲に置かないことです。症状は急性胃腸炎の症状で下痢、腹痛、嘔吐です。 |
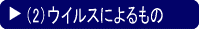 |
 |
| 生牡蠣などの食品、水が感染源。85度以上で1分間加熱することで死滅。ノロウイルスは牡蠣等二枚貝の食品内で増殖するのではなく、患者の腸内で繁殖し便や吐物に排出されます。冬に多発しここ数年ではノロウイルスによる食中毒が最も多くみられます。罹患された方も多いと思いますが激しい嘔吐と下痢、腹痛などでぐったりして受診されます。感染力が高く、家族内感染もみられますし、集団発生のニュースも時々報じられます。これはウイルスが経口感染だけでなく、飛沫感染、粉塵感染も起こすからです。しかし、基本的には生の二枚貝を食べないことと、手洗いを充分にする事で防げます。 |
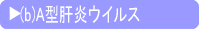 |
| 水、野菜、魚介などが感染源。 |
 |
アジア、インドなどの流行地では生水、我が国ではイノシシ、シカ、ブタの生肉など。
これらも広義の食中毒ともとれますが、今回は省略します。 |
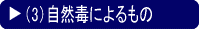 |
| これは動植物が有する毒素を経口摂取して起こるもので、動物性ではフグ毒、貝毒があり、植物ではキノコやトリカブトなどの野草、ジャガイモの芽のソラニン,そしてかび毒などです。 |
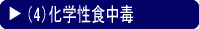 |
| これには不許可の食品添加物、有機水銀など有害金属の環境汚染によるもの、農薬、毒劇物の誤えんなどがあります。何れも急性中毒と慢性中毒とがあります。 |
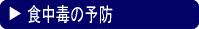 |
| 個々にも述べましたがこの時期多いのはカンピロバクターやサルモネラ菌、ウェルシュ菌、病原性大腸菌などで、これらの中毒は次のことで充分に防げます。 |
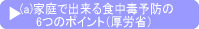 |
①食品の購入:新鮮なもの、消費期限を確認して購入
②家庭での保存:購入後すぐに冷蔵庫、冷凍庫での保存
③下準備:手を洗う、調理器具は清潔に
④調理:充分に加熱、細菌は75度で1分以上
⑤食事:手を洗う、室温に長く放置しない
⑥残った食品:きれいな容器で保存し再加熱する |
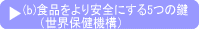 |
①清潔に保つ
②生の食品と加熱済みの食品とを分ける
③良く加熱する
④安全な温度に保つ
⑤安全な水と原材料を使う
消化器症状が出たときには、早めに受診してください。場合によっては死に至ることもありますので、寝冷えだろうと軽く考えないで下さい。また、食品で心当たりがあるときにはそれを持参してください。原因が判ることがあります。またご家族での対応は糞便や吐物から二次感染を起こすことがありますので、吐物は手袋で処理したり、十分な手洗いが必要です。 |
 |
| 私たち生き物は何かを食べなければ生きていけません。そして、食べることによって命を落とすことは避けなければなりません。食中毒は、相手が見えなくても食習慣を変えることや調理法を注意する事で充分防げます。しかし、同じ見えないものでも放射能は違います。空気が汚れ、水が汚れ、食物が食卓が汚染されそして故郷が、やがては国が滅びるかもしれません。私たちは今後、どのようにこの問題に向き合うかの知識と覚悟が必要と思います。 |
|
|