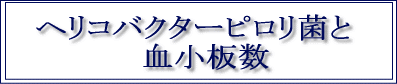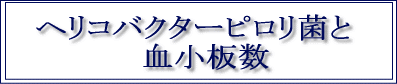慢性肝炎に対するインターフェロン治療が開始してから、約20年が経過しました。治療が上手くいった患者さん、残念ながら完治には至らなかった患者さん、さまざまだと思います。なぜ、同じお薬による治療を受けたにも関わらず、成功・不成功の差が生じるのでしょうか?
1番の理由は、ウィルス量の問題です。そして2番目の理由は、ウィルスのタイプです。同じC型肝炎であっても、インターフェロンが効きやすいタイプのウィルスと、手強いタイプのウィルスとに分類されます。でも、同じタイプのウィルスで、しかも同じぐらいのウィルスの量なのに、患者さんによって治療の成果には差が出てしまいます。個人差だと言えばそれまでですが、科学的になにか理由はないのでしょうか?
わが国における感染症の代表的なものとしては、C型肝炎以外にピロリ菌感染があげられます。このピロリ菌は、胃潰瘍に限らずいろいろな病気を引き起こすことがわかっています。特発性血小板減少性紫斑病(ITP)という、血小板が普通の人よりも低下してしまう原因不明の病気があります。このITPの患者さんのうち、ピロリ菌に感染している一部の患者さんでは、ピロリ菌を退治する「除菌」という治療によって、血小板数が増加することが証明されています。つまりピロリ菌は、骨髄で血小板がつくられ全身の血管の中で働く際に、なんらかの影響力を持っていることがわかっています。
話しをもとに戻しましょう。同じタイプのC型肝炎ウィルスで、しかも同じぐらいのウィルス量でも、患者さんによって、インターフェロン治療の成果に差が出てしまうのはなぜでしょうか?3番目の理由として、投与できたインターフェロンの量が多いか少ないか、という問題が挙げられます。
インターフェロンの治療の経過中には、貧血傾向になったり、食欲が低下したりして、注射するインターフェロンの量を減らさざるを得ない患者さんが少なくありません。血小板数に関しても同様です。治療開始後に血小板が極端に減ってくると、さまざまな弊害が出てしまうと予想されるため、投与する薬剤の量を減らす必要があります。
さてピロリ菌が、血小板の動態に何らかの影響を及ぼしていることは、先に説明しました。そして、インターフェロンの治療中に血小板が低下する患者さんが少なくないことも、説明しました。ということは、同じタイプのC型肝炎ウィルスで、しかも同じぐらいのウィルス量でも、患者さんによってインターフェロン治療の成果には差が出てしまう理由のもう一つの原因として、ピロリ菌感染の「ある・なし」が影響しているということは、考えられないでしょうか?ピロリ菌に感染していると、そうでない患者さんに比べて、治療中の血小板が低下しやすい可能性があるからです。
2008年以降に、相川内科でインターフェロン治療を受けられた患者さんの血小板数の下がり方を、ピロリ菌の有無で別けて解析した結果、ピロリ菌に感染していると血小板数が下がりやすいという事実がわかりました(図)。つまり、ピロリ菌を退治してからインターフェロンの治療を開始すれば、血小板が下がりにくく薬剤をなるべく減量しないですむ、という可能性が考えられます。
これはまだ研究の途中であり、もっと多くの患者さんのデータを分析しなければ、正確な結論は出せません。しかし、まず胃カメラ検査をうけて、自分の胃にピロリ菌がいるか?いないか?を事前に検査することは、きわめて有用だと思われます。インターフェロン治療を検討している患者さんは、胃の検査なんて関係ない!と思わずに、積極的に胃カメラ検査を受けてみて下さい。
|
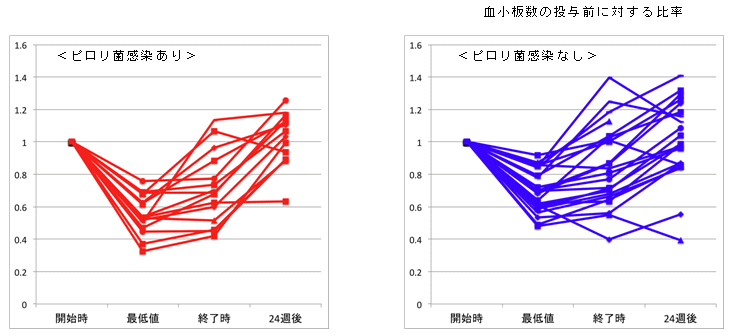 |
|
(医師 池澤和人) |
| (この研究は2011年10月の日本肝臓学会総会で発表しました。) |
|
|