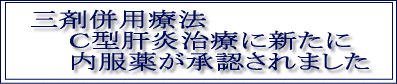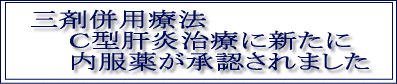昨年暮れに新しいC型慢性肝炎に対する内服薬が我が国でも承認され、保険診療で使えるようになりました。
C型肝炎の治療にはウイルスを排除する生体の反応を一層高めるインターフェロンと、これと併用するとインターフェロン作用を増強する、リバビリンが用いられてきました(PEG-RBV)。しかし、ウイルスを排除して肝炎が終息する状態(SVR)になるのはたかだか、60%でありました。今回承認されたテラプレビルは肝炎ウイルスの遺伝子に直接作用して、C型肝炎ウイルス(HCV RNA)の増殖を抑える初めての抗ウイルス剤です。すでに、2009年から欧米10カ国の医療機関で検討され、有効性が確認されています。
このクスリは単独で使用するのではなく、以前からのPEG-RBV治療と一緒に、三剤併用として使われてきました。いくつかの文献からみてみましょう。
この薬剤の長所は
1.50%以上の患者さんのHCV RNAが4週以内に速やかに消失します。
2.従ってこのクスリの服用期間は12?24週で終了します。
3.初めて治療を受ける患者さんのSVR率は89%以上でこれまでになく高率でした。
4.過去に治療が成功しなかった患者さんで、一度、HCV RNAが消失して再燃した患者さんでは83%のSVRが得られています。一度もHCV
RNAが消えなかった、従来再治療の成功はないとされている患者さんでもSVRは33%の成績でした。
そして、短所は
1.副作用での中断率が20%と高い、
2.そのうち皮膚症状が高率に見られ、発疹が局所的な時、これを軽度、一律の広がりで全身の50%以内の時、中等度、それ以上を重症と三段階にわけています。中等度までは治療継続可能とされますが、我が国の経験を見て判断したいものです。
3.貧血も希ではなく、併用しているリバビリンの影響もあり、時に輸血、赤血球の産生を促進するエリスロポエチンを使用しています。
4.その他、胃腸症状で食欲がなく、体重減少などこれまでのPEG-RBV治療と同じ問題があります。
確かに、これまでの治療法の水準を超すクスリですが、副作用も決して軽くありませんから、従来法と今回の三剤併用のどちらにするかはウイルスの遺伝子型、ウイルスのインターフェロン感受性遺伝子、患者さん自身の遺伝子解析を考慮して、ベストの方法を選択すべきです。
|
|
|
|