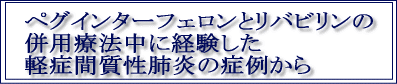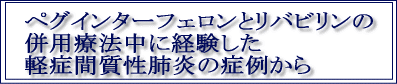| 【はじめに】 |
C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療は現在週1回投与が可能なペグインターフェロンとリバビリンの併用療法が標準的治療として確立されています。最近では肝硬変(代償期)の方への適応拡大も認められています。現在では適切な治療が行われれば約60%の方々が治癒する時代になっています。また、行政面からのサポートも得られるようになり、以前では医療費の面で治療に踏み切れなかったような方々でも、現在では治療が可能になっています。
このように、インターフェロン治療はC型慢性肝炎を治す有効な治療ですが、様々な副作用も有しています。治療を専門医療機関が担う謂われです。今回はインターフェロンの副作用としては比較的稀な間質性肺炎を経験しましたのでご紹介します。 |
| 【治療に伴う一般的服作用】 |
治療の時期を、治療初期(1週間以内)、治療中期(2?12週間)、治療後期(3ヶ月以降)と分けて、それぞれに現れやすい副作用に対処します。
a.初期の副作用
①インフルエンザ様症状(発熱、悪寒、全身倦怠感、頭痛、関節痛など)
②食思不振、吐き気
③注射部位以外の発疹、痒み
b.中期の副作用
①全身症状(微熱、倦怠感)
②消化器症状(腹痛、吐き気、便秘、口内炎など)
③精神症状(不眠、不安、躁鬱病)
④間質性肺炎(乾咳、呼吸 困難、運動時の息切れ、微熱など)
⑤目の症状(網膜症、目の痛み)
⑥心臓の症状(不整脈、心不全など)
⑦糖尿病の悪化
c.後期の副作用
①脱毛
②甲状腺機能異常(動悸、
発汗、むくみなど)
治療の全期間を通じて、貧血、白血球、血小板、肝機能の検査値の変動はいつでも生じる可能性があります。 |
| 【間質性肺炎】 |
前項でご紹介しましたように、インターフェロン治療の副作用は種々あります。ご紹介する症例は治療開始3ヶ月過ぎから息切れを訴えたのです。
この方は喫煙歴のある40代の男性です。高ウイルス量であったためペグインターフェロンとリバビリンの併用療法を開始しました。治療開始から3ヶ月ほどして息切れを訴え始めました。それと共に図のようにKL-6が上昇しました。貧血の進行はないのに息切れだけが悪化したため、採血結果、胸部X線、肺CTからやはり軽度の間質性肺炎と診断しました。幸い治療の中止で、その後約2ヶ月ほどかけて全ての検査所見が改善しました。間質性肺炎は比較的重篤な副作用なのですが、この方の場合、原因薬剤の中止のみで症状が改善しました。 |
| 【今後の治療に役立てるべきこと】 |
インターフェロン治療の副作用としては稀とされている間質性肺炎ですが、その特徴は以下のようにまとめられています。
①発症頻度は1%未満(0.01~0.3%との推計)
②いつでも生じ得るが、最初の12週に多い
③症状は労作時呼吸困難、乾性咳嗽、発熱、易疲労感、関節痛、筋肉痛、食欲不振等
④原因薬剤の中止で改善することが多く、平均8週間程度かかる
⑤発症例の約7~10%が死亡している
インターフェロン治療を受けている患者さんは、従来では説明できないような息切れがあった場合には担当医に遠慮なくご相談ください。 |
| 【まとめ】 |
| 間質性肺炎については厚労省からも再三注意喚起がなされてきました。このためインターフェロン治療に際しては、早期発見のためには患者さんの自覚症状の訴えを注意深く聞くことが何より重要ですが、早期診断に役立つKL-6の定期的な測定も重要です。また、疑ったときには画像診断、専門医への紹介も大切です。今回は大事には至らずに済みました。今後も悪い慣れの出ないように細心の注意を以て治療に当たらせて頂きたいと思っています。 |
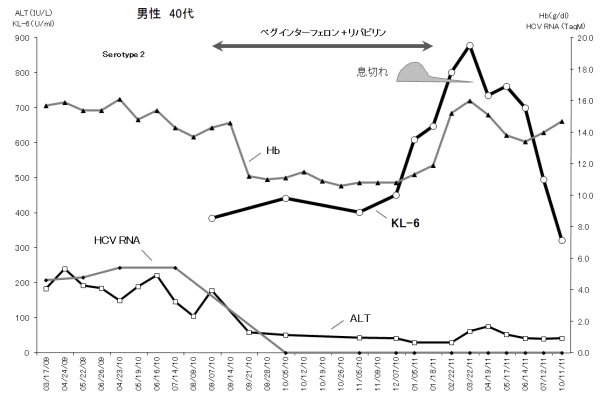 |
|
|