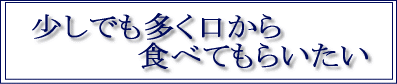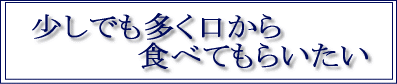当院の3階にある厨房は朝から夜まで賑やかです。包丁の音、水の音、お皿の音、機械の音。「たくさん食べてもらえるように」と、日々食材を相手に奮闘しています。
誰でも自分の作った料理の評価は気になります。厨房の方達は、食器洗浄の際、誰がどれくらい残したか覚えており、全く面識のない患者さんでも、残食が多いと病状を心配して、私に尋ねてくることもあります。入院患者さんによっては、食欲不振が続き低栄養(食事からのエネルギー摂取不足により、体を作るべき栄養素がエネルギーに使われてしまう状態)になり、体力不足で治療も進まない「負の循環」に陥ります。厨房では、患者さんがそうならないよう、患者さんの状態によって硬い食材を抜いて調理したり、嗜好に合った個別メニューを作ることも行っています。
入院食では義歯が合わない、噛む力が弱い等の理由で「刻み食」という食事形態があります。通常の食事を刻むだけなので、香り・味は変わらないのですが、刻むと見た目が損なわれ、「おいしそう」という食欲が湧きにくくなります。刻んで盛り付けることは長年行われてきました。しかし、刻めば食べやすくなるわけではないことが、最近では頻繁に言われています。ヒトは食べ物を噛んで細かくすると同時に唾液と混ぜ、柔らかい塊にしてから飲み込んで(嚥下して)います。調理後の食事を刻むだけでは、口の中に入れた途端にバラバラと崩れ、塊になりにくいのです。
そこで、最近はソフト食・やわらか食など呼び名は様々ですが、調理の段階で食事を柔らかくするような方法が採られるようになってきました。肉や魚を玉ねぎや山芋、卵、油脂、ゼリー化増粘多糖類などと混ぜ合わせ、「歯茎で噛める」「舌でつぶせる」硬さに仕上げるものです。食事自体が柔らかいので刻む工程はありませんし、飲み込むための塊にし易いというわけです。
当院でも院長指示の元、これらの調理法を取り入れられないかと厨房の方達と工夫を始めました。まずは刻むとボソボソして最も食べにくくなる肉・魚をハンディブレンダーという機械や寒天を使い、テリーヌ状になるように仕上げています。次に喉に詰まりやすい芋類をマッシュして、茶巾絞りのように仕上げ、見た目にも食欲に訴えるよう心掛けています。失敗もありますが、毎食「舌でつぶせる硬さ」を念頭に、食欲不振の患者さんに少しでも食欲の湧く、食べやすい料理をと考え、調理しています。
病院で働く他の職種から食事を見ると、料理の見た目・味に代表される「質」だけが食事摂取量を左右させるわけではありません。「量」が多い、食事に費やす「時間が短い・長い」事も大切な要因です。今後は、少量で良質の栄養を摂れるような献立の作成と、食事に費やす時間・周りの環境等を、患者さんに携わる多くの職種「チーム・相川」で考えていきたいと思っています。
|
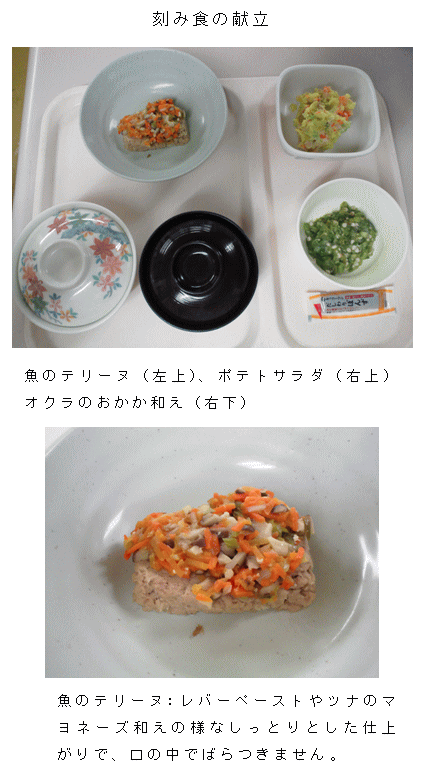 |
|
|
|