| 動脈硬化の検査をする患者さんから、「血液サラサラの検査ですか?」とよく聞かれるのですが、当院で行っている動脈硬化の検査(FORMの検査)とは、baPWV(上腕―足首間脈波伝播速度)とABI(上腕・足首血圧比)を計測する検査を行うことによって血管の働きを調べる生理検査のことをさしています。 |
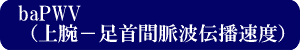 |
心臓の拍動によって生じる、心臓から足の末梢血管に向かって伝わっていく振動(脈波)の伝わる速さを測定します。この伝導速度で動脈壁の硬さ(血管弾性)を推測することができ、それにより動脈硬化の程度を評価します。これがbaPWV(上腕―足首間脈波伝播速度)です。たとえば、ビニールホースの端を叩いて、その振動がもう一方の端に伝わる時、硬いビニールホースと柔らかいビニールホースで伝わる速さを比べると、硬いビニールホースの方が速く伝わります。血管においても同様で、脈波の伝わる速度が速い=血管壁が硬いということになります。
baPWVでは、その対象となる血管は大動脈の一部、大腿動脈、腓骨動脈(ふくらはぎのところを走行する動脈)などの比較的細い血管が対象となります(図参照)。
(なお、baPWVは年齢によってその標準値が若干変わってきます) |
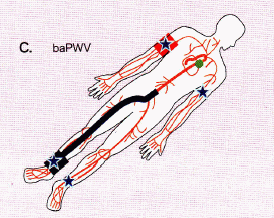 |
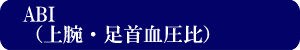 |
上腕と足関節(足首)の収縮期血圧(最高血圧)を測定して、その比を次の計算式で算出し、その値を用いて末梢動脈疾患の診断の指標とする検査です。
ABI=足関節最高血圧÷上腕最高血圧(左右の高い方)
通常の生体において、末梢側にある足首血圧の方が、心臓に近い方にある上腕血圧より高いのですが、動脈硬化によって、末梢の動脈に閉塞や高度の狭窄がおこる閉塞性動脈硬化症(ASO)が存在していると、足関節の最高血圧が低くなり、ABIの値が低値となります。これによってASOの診断や重症度の指標にすることができます。 |
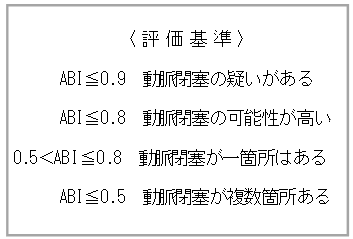 |
|
|

