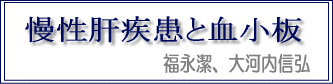
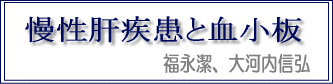
| 1.血小板数でわかること | |
| ① 門脈圧亢進症と脾機能亢進症 門脈は胃や腸からの血液を肝臓に運ぶ血管です。その圧力は5~10mmHgです。心臓から全身に血液を運ぶための動脈の圧(いわゆる血圧)は70~120mmHg ですから、かなり低いことが分かります。門脈圧亢進症とはこの門脈の圧が高くなることです。門脈圧亢進症をきたす主な疾患は肝硬変、特発性門脈圧亢進症、肝外門脈閉塞症、Budd-Chiari症候群の4つで、このうち肝硬変が80%を占めます。肝臓が硬くなると血液が流れ込みにくくなるため、門脈の圧が高くなるのです。門脈圧亢進症になると様々な症状が現れます。腹水と食道静脈瘤が主なものです。肝硬変の患者さん全員に腹水や食道静脈瘤が発症するわけではありませんが、腹水や食道静脈瘤があると門脈圧亢進症があると判断します。 さて、門脈圧亢進症にはもう一つ重要な症状があります。それは脾機能亢進症です。脾臓からの血液も門脈を通って肝臓に入るため、門脈圧亢進症になると脾臓にも負担がかかります。そのため脾臓が腫れ、その機能が強すぎる状態となり、亢進症と呼ばれます。脾臓の機能の一つは寿命を迎えた白血球、赤血球、血小板を破壊することですから脾機能亢進症ではこれらの血球が過剰に壊され、血液中の血球が減少します。特に血小板の低下が臨床的に問題となります。 |
|
| ② 血小板数と肝線維化 慢性肝炎が進行すると肝臓は徐々に硬くなり、肝硬変になります。肝臓が硬くなるということは肝臓に線維が増えてくるということです。血小板数はこの肝線維化の進行具合を的確に示すといわれています。肝臓の線維化が進むに従って、血小板数が低下します。血小板数が10万を下回るようになると、慢性肝炎から肝硬変へ進展したと考えます。 |
|
| 2.脾臓摘出術とは? | |
| ① 目的 a 脾機能亢進症の改善:インターフェロンの副作用予防 肝硬変では血小板の低下を認めますが、血小板減少のある患者さん全員に脾臓摘出術を行うわけではありません。なぜなら、肝硬変で血小板数が低下していても出血傾向などの症状はほとんど起こらないからです。血小板が少なくても日常生活を送るためには問題はないのです。また、脾機能亢進症では白血球減少や赤血球減少(貧血)も起こることがありますが、それによる重大な症状も起こりません。しかし、インターフェロン治療を行う場合は異なります。インターフェロンには血小板減少という副作用があるので、もともと肝硬変で血小板が少ない場合、インターフェロンを十分投与することができないことがあるのです。そのため、インターフェロン投与に先行し、脾臓を摘出することがあります。これにより、血小板減少を改善し、インターフェロン治療を完遂することが可能となるのです。現在、脾機能亢進症に対する脾臓摘出術のほとんどが、C型肝炎に対するインターフェロン治療を行うことを目的としています。 b 門脈圧亢進症の改善:胃静脈瘤の治療 脾臓摘出術で治療する病気に胃静脈瘤があります。胃静脈瘤は食道静脈瘤と同様の疾患で、門脈圧亢進症の症状の一つです。現在、ほとんどの食道静脈瘤は内視鏡で治療することができますが、胃静脈瘤は内視鏡による治療が難しい場合があります。そのときは脾臓摘出術を行います。脾臓を摘出すると門脈圧が下がり、胃静脈瘤が改善するのです。また、この門脈圧が低下する効果を期待して、生体肝移植の時に脾臓を摘出することがあります。 |
|
| ② 方法 大きく分けて開腹手術と腹腔鏡手術の二つの方法があります。脾臓は左上腹部の背中側にあります。開腹手術で脾臓摘出術を行うためにはみぞおちから臍までの切開が必要です。肝硬変の患者さんの脾臓は大きく、たくさんの脆い血管がとりかこんでいることが多いので、大量出血しやすく、手術には大変気をつかいます。 腹腔鏡手術は腹腔鏡という内視鏡をお腹の中に入れ、その画像をモニターで見ながら手術をする方法です。創が小さいことが良い点ですが、この手術を行うには特別な技術が必要です。脾臓が大きい場合にはこの方法では手術できないこともあります。 |
|
| ③ 効果 脾臓摘出術により、血小板数が上昇します。一時期10~50万にまで上昇することもありますが、最終的には10~20万程度に落ち着きます。血小板数が上昇するので、インターフェロン治療を行うことが可能になります。また、脾機能亢進症を伴う肝硬変患者さんに脾臓摘出術を行うと肝機能が改善するという報告がこれまでに数多く出されています。その理由はいくつか考えられていますが、私たちは血小板に肝機能改善効果があるのではないかと考え、研究を進めています。 |
|
| ④ 問題点 脾臓摘出術後に起こる問題点は二つあります。感染症と門脈血栓症です。脾臓は免疫機能を司る臓器なので、脾臓を摘出すると感染防御が障害され、感染症にかかりやすくなります。わが国における脾臓摘出後に起こる感染症の頻度は成人で0・3~4・3%と、欧米と比べ少ないのですが、その発症は急激で、敗血症、髄膜炎を発症し、高い確率で死亡に至ります。その原因菌の8割が肺炎球菌であり、予防のためには肺炎球菌ワクチンの接種が有効です。 門脈血栓症が生じると肝臓へ流入する血液が少なくなり、最悪の場合、肝不全となります。脾臓摘出後は定期的な検査を行い、門脈血栓症の早期発見、早期治療を行う事が肝要です。血栓を溶かしたり、血液が固まりにくくなる薬剤で治療します。 |
|
| 3.部分脾動脈塞栓術(PSE) | |
| 手術ではありません。細い管(カテーテル)を用いて行う治療です。上腕または大腿の動脈からカテーテルを挿入し、脾臓の動脈まで送り込み、血管を詰める物質を流し込みます(塞栓)。この塞栓により脾臓の動脈の血流を止めて脾臓を壊死させ、その機能を低下させます。当初は脾臓全体の血流を止めていましたが、重篤な合併症を起こすことが分かったため、現在は脾臓の一部分を塞栓しており、そのために『部分的』という名前がついています。 | |
| 4.トロンボポチエン | |
| トロンボポエチンは血小板を増やすホルモンです。このホルモンは主に肝臓で産生されます。肝硬変で血小板数が低下するのは脾機能亢進症が原因であると説明しましたが、一方、肝機能の悪化により肝臓からのトロンボポエチンの産生が減少し、血小板が低下するという可能性も指摘されています。 最近トロンボポエチンと同じ作用を持つ薬が臨床で使われ始めました。エルトロンボパグという薬です。C型肝硬変症の患者さんを対象とした試験によると、この薬を服用することで9割以上の方の血小板数が10万以上となりました。現在、この薬は特発性血小板減少性紫斑病という病気のみが保険適応となっているため、肝硬変症の患者さんに使用することはできませんが、今後、使用できるようになることを期待したいと思います。筑波大学ではこの薬を服用することで肝機能の改善が得られないかどうかを調べるための臨床試験を行う予定です。 |
|
|
|