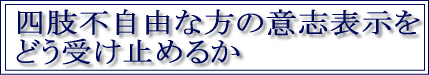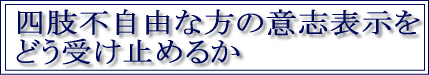訪問看護に伺う中で、強く「生きる」という言葉がぴったりのとても美しい女性がいらっしゃいます。お歳は○○歳。四肢不自由で寝たきりですが、週一回の訪問看護に伺った際には、声をかけるとはっきりとした口調で「どうぞお入りください」と迎えて下さいます。お話をしながら経過観察、各部の洗浄をしていると、気分によっては得意の唄を聞かせて下さったり、時には、先に旅立たれたご主人の自慢話に花を咲かせて下さいます。殆ど動かない体の不自由さや辛さを感じさせない程です。
ヘルパーさんによる食事の介助や看護師の力を必要としながら、弱音を吐かずにいらっしゃる姿に私達も感動し、勇気をいただいています。また、息子さんの細かい心配りと愛情が、より一層安心感を与えていらっしゃる様です。
この様な素晴らしい方にお会いする度に、私達は心と身体で状況を把握し、患者さんの不安や訴えを見逃すことなく対処していかなければと強く感じます。そして訪問看護の技術を高めるためにも努力し、訪問後は、主治医と連絡をとり情報を提供し病状の変化に対する指示をいただきながら、患者さんとの関わりを大切にしていきたいと思います。
|
|
|
 |
肢体不自由とは「医学的には、発生原因のいかんを問わず、四肢体幹に永続的な障害のあるもの」とあります。これには、軽度から重度まで様々な等級がありますが、今回はより重度である四肢体幹を著しく障害された「寝たきり状態」の方に焦点を絞って書いてみたいと思います。
*
Cさんは四肢体幹の自由がなく「寝たきり状態」でした。ただ、話すこと、理解することはできます。「顔が痒い」「目ヤニを拭いて」「水が飲みたい」「汗を拭いて」…と毎日多くの訴えがみられました。不安感が強い時は訴えの回数も増え、ナースコールが多くなりました。ある日、Cさんと職員が「何度もコールしないで下さい(職員)」「自分でできないから頼んでいるんだ(Cさん)」と険悪な会話をするのを耳にしました。その時、私は『Cさんは「自分でやりたい」と一度も口にしたことはないけれど、できることなら自分のことを自分でやりたいのだ』と改めて気付きました。そこで、療法士たちと相談し、Cさんが好きな時に水を飲めるように長いストローをベッド脇に設置したり、ナースコールのスイッチを口で引っ張るように改良したりしました。すると、Cさんの不安感は少し落ち着きコールの回数も減りました。
*
Fさんは四肢体幹の自由はなく、話すことも理解することも困難でした。意思表示できないのでは?とついつい思いがちです。しかし、verbal(言語的)なコミュニケーションが出来ない方と接する時、私はより意識して表情や体の反応をみるように、見落とさないようにしています。うなずきや目線、表情の緩み具合、体の緊張、呼吸などにより、「調子がよい」「痛いからいやだ」などといった意思を汲み取ります。いつも同じ姿勢では体も痛くなるだろうと、体をベッドの端に起こし背中を擦ると表情が緩みますし、寝ている姿勢が安楽でいられるようにクッションやタオルなどで接触面を増やせば体の緊張も緩みます。
*
私が療法士として今までに障害を抱えた方との関わりを通じて、どんな方であっても必ず意思表示があることを経験してきました。私たち人間の意思表示はワンパターンではなく、無数に存在するものであるのだと思います。とりわけ肢体不自由という障害を抱えている方の意思表示に私たち療法士は慎重に耳を傾け、反応に注意を払わなければなりません。なぜなら、本当の意思を汲み取れたとき、互いの信頼関係が確立され、達成へと歩み始めることができるからです。
|
|
|
|