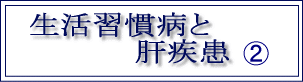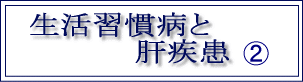食生活の変化からの考察
《1肝疾患の増加の背景》
前回は社会構造の変化という視点から肝機能障害を考察しました。改善策はとにかく運動することでした。今回は食生活の変化からの肝機能障害の増加を考察したいと思います。
《2我々の先祖は何を食べてきたか》
A:米が食生活の中心
日本列島で稲作が行われるようになった時代は今から約2300年前に始まる弥生時代です。それまでの縄文時代、あるいはそれより前の時代は狩猟、採集による生活をしていました。約2万人と推定される縄文人の食生活は遺跡の発掘からかなり詳細に判明しています。つまり、主な食料はトチ、クリ、ドングリなどの堅果類や、ヤマイモなどの根茎類であり、魚肉、獣肉は補完的に食していたようです。栄養素は、炭水化物が主で、タンパク質、脂質の含有率は少ない食事でした。その後水田耕作が行われるようになると食料が安定して供給されるようになり人口が急速に増加しました。弥生時代初期には約60万人の人々が生活していました。但しこの時代の水田の収率は現代に比較すると悪く、一人一日せいぜい米一合程度であったと推計する研究者もいます。不足分は狩猟、採集で補われました。その後中世までに日本人の食生活がほぼ確立され、一人一日四合の米を中心として魚介類で不足を補うようになり、太平洋戦争の敗戦まで基本的には同じ食生活でした。つまり、炭水化物中心の食生活だったのです。
B:摂取カロリー、炭水化物、脂質の経年変化
宮沢賢治没後の昭和9年に発表された雨ニモマケズの有名な一節、「一日に玄米四合と味噌と少しの野菜」で長らく我々平均的な日本人は生活してきました。一日の摂取カロリーに占める炭水化物の割合は実に約81%であり、脂質からはわずかに9%程度でした(摂取カロリー1903?、昭和21年)。太平洋戦争後の高度経済成長で摂取カロリー、脂質の割合も増え続けて昭和50年には2226?、炭水化物63%、脂質22%に達しました。その後は高度経済成長の終わった昭和60年には摂取カロリー2088?、炭水化物60%、脂質25%となり、それ以降摂取カロリーは徐々に減少しているものの、その比率の変化は殆ど見られておりません。
C:犯人はだれだ?
現在、脂肪肝の患者さんは益々増加しています。今まで見てきましたように、それらの発症が脂質の摂取量と密接に関連していますが、それだけならば、脂肪肝は昭和50?60年頃をピークとして現在は減少に転じていなければなりません。実情はそうなっていません。脂肪肝増加の犯人は一体だれなのか、という問題が十分に解決してはいないのです。脂肪肝増加の犯人は赤肉、加工肉摂取量と密接に関連していると指摘する研究者がいます。あと、単純糖質つまり、糖質の加わったジュース類、果物、菓子の過剰摂取も脂肪肝に繋がります。おそらく、食生活ではこのような要素が複合して脂肪肝の増加に繋がっているのです。それにストレス社会から逃れるためについつい過剰に摂取してしまうアルコールも大きな原因です。
《3処方箋》
脂肪の過剰摂取をせず、アルコールは日本酒換算で一日一合以下にすること。早食いはせず、時間を掛けて食事すること、腹八分目が基本です。そうはいっても忙しい現代社会でゆっくり食べてなんかいられないと思っているあなた、急いだって余り変わりません。それに健康で長く活躍することを選んだ方が結局は社会に貢献することになるのだと達観することが大切なのではと思います。我々の祖先は毎日必ず食事があるとは限らないような時代もくぐり抜けてきました。現代人は食べ物に感謝しながら食事することが少なくなってしまったので、よく噛まず(よく味合わず)流し込むような食生活を送っている人も珍しくない悲しい状況です。食べ物が目の前にあることに感謝しながら味わって食事が出来れば、結局食べ過ぎることも減るのではないかと思います。
|
|
|
|