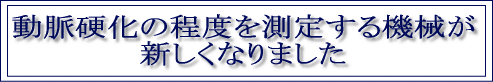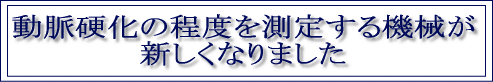丂偙偺偨傃丄摉堾偺摦柆峝壔傪専嵏偡傞婡夿偑怴偟偔側傝傑偟偨丅
丂廬棃偺婡夿偼丄怱憻偺攺摦偵傛傞寣娗偺怳摦乮柆攇乯偺揱傢傞懍搙乮柆攇揱攄懍搙 PWV乯傪應掕偟偰摦柆峝壔偺掱搙偺巜昗偲偡傞曽朄偱偟偨丅
丂崱夞怴偟偔摉堾偵摫擖偝傟偨婡夿偼丄PWV偐傜CAVI偲偄偆巜悢傪嶼弌偟偰摦柆峝壔偺掱搙偺巜昗偲偡傞曽朄偱偡丅
亂CAVI偺専嵏曽朄偺摿挜亃
嘆應掕懳徾偲偡傞寣娗偼怱憻偐傜懌庱傑偱
應掕偡傞柆攇揱攄懍搙乮PWV乯偼丄柆攇偺僗僞乕僩偱偁傞怱憻曎偺奐曻偟偨帪偐傜丄懌庱偵摓払偡傞傑偱偺丄昗弨朄偲偝傟偰偄傞戝摦柆尨朄偵懄偟偨應掕曽朄偲尵傢傟偰偄傑偡丅乮廬棃偺曽朄偼丄懳徾寣娗偺巒傑傞晹埵偑晄柧椖偱丄偳偪傜偐偲偄偆偲壓巿偺寣娗傪斀塮偟偰偄傞偲尵傢傟偰偄傑偟偨乯
嘇寣埑埶懚惈傪梷偊傞
CAVI偼丄寣埑偵塭嬁傪庴偗側偄惗懱偺暔惈傪尰偡兝朄偲偄偆棟榑偵婎偯偄偰嶼弌偝傟偨巜悢偲側傝傑偡丅乮廬棃朄偱偼丄寣埑偺曄壔偵傛偭偰應掕抣傕曄壔偡傞偲尵傢傟偰偄傑偟偨乯
嘊寣娗斀幩恄宱偺塭嬁傪梷偊偨應掕曽朄
寣埑傪應掕偡傞帪丄椉庤椉懌庱傪嵍塃暿乆偵應掕偡傞偙偲偱丄寣娗斀幩恄宱偵傛傞寣娗偺偗偄傟傫偺斀墳傪梷偊偰偄傑偡丅
|
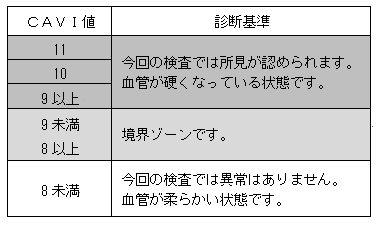 |
丂摦柆峝壔搙傪昡壙偡傞応崌丄2偮偺巜昗偱専嵏寢壥傪昡壙偟旐専幰偵愢柧偟傑偡丅
丂1偮偼丄嵍偺昞偺傛偆偵俠俙倁俬抣偵懳偡傞昡壙偱偡丅
丂2偮傔偼丄壓偺擭楊僌儔僼偱昞偡傛偆偵丄寣娗偺憡摉擭楊偱偡丅
丂寣娗擭楊偼丄寣娗偺榁壔偺搙崌偄傪帵偡偵偼旕忢偵愢摼椡偺偁傞巜昗偱偡偑丄廳梫側偺偼應掕寢壥偑偄偒抣乮寣娗忈奞偑婲偙傞儕僗僋偑崅偔側傞俠俙倁俬抣乯傪挻偊偰偄傞偐偳偆偐偱偡丅
|
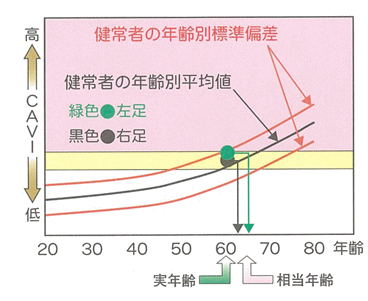 |
乻 寣娗擭楊敾掕僌儔僼 乼
丂崱夞偺俠俙倁俬應掕抣乮廲幉乯偲旐専幰偺幚擭楊乮墶幉乯偺岎嵎偡傞強偵娵報仠傪儅乕僋偟傑偡丅
丂丂憡摉擭楊偼丄寁應抣偐傜幚擭楊偲昗弨曃嵎傪峫椂偟偰媮傔丄壓栴報慄偱憡摉擭楊傪帵偟傑偡丅
丂丂嵍塃偺俠俙倁俬傪應掕偟偨応崌偵偼塃懌傪崟娵仠丄嵍懌傪椢娵仜偱昞帵偟偰偄傑偡丅
|
|
|
|
|